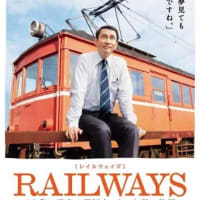千日回峰行は、滋賀県の比叡山延暦寺の修行である。天台宗HPから転記する。
「相応和尚により開創された回峰行は、文字どおり、比叡山の峰々をぬうように巡って礼拝する修行です。この行は法華経中の常不軽菩薩(じょうふぎょうぼさつ)の精神を具現化したものともいわれます。常不軽菩薩は、出会う人々すべての仏性を礼拝されました。回峰行はこの精神を受け継ぎ、山川草木ことごとくに仏性を見いだし、礼拝するものです。
回峰行者は、頭には未開の蓮華をかたどった桧笠をいただき、生死を離れた白装束をまとい、八葉蓮華の草鞋をはき、腰には死出紐と降魔の剣をもつ姿をしています。生身の不動明王の表現とも、また、行が半ばで挫折するときは自ら生命を断つという厳しさを示す死装束ともいわれます。
千日回峰行は7年間かけて行なわれます。1年目から3年目までは、1日に30キロの行程を毎年100日間行じます。定められた礼拝の場所は260箇所以上もあります。4年目と5年目は、同じく30キロをそれぞれ200日。ここまでの700日を満じて、9日間の断食・断水・不眠・不臥の“堂入り”に入り、不動真言を唱えつづけます。
6年目は、これまでの行程に京都の赤山禅院への往復が加わり、1日約60キロの行程を100日。7年目は200日を巡ります。前半の100日間は“京都大廻り”と呼ばれ、比叡山山中の他、赤山禅院から京都市内を巡礼し、全行程は84キロにもおよびます。最後の100日間は、もとどおり比叡山山中30キロをめぐり満行となるものです」
千日回峰行を2回満行した高僧が酒井雄哉師である。12年籠山行の後、日本を歩き回り、世界を歩き回り、比叡山北嶺大行満大々先達大阿闍梨総一和尚長寿院住職・酒井雄哉は筋金入りの尊敬できる風来坊である。「大阿闍梨(あじゃり)、道なき未知を語る」(国土交通省近畿地方整備局、毎日新聞社主催)の酒井雄哉権大僧正の講演記録から抜粋した。
「一口に千日回峰といってもいろいろな決まり事があり、日程が定められている。(4、5年目に行う)200日の回峰を例に取ると、まず残雪の中を雪をかき分けて歩き始める。「暖かくなったなあ」と思うと桜のつぼみが1輪、2輪と咲きだす。桜に囲まれて歩いていると、行をしているのか、桜見物しているのか分からない。 桜吹雪が舞い、新緑の季節を経て、雨期(梅雨)が来る。人間はずうずうしいもので、(行をしていても)なるべくぬれないようにと考えるが、一度泥道にずぼっとはまりこんだら「やっぱり駄目か」と雨が平気になる。やがて蒸し蒸しする夏が来て、朝露で冷蔵庫の水をひっくりかえしたようにひんやりとすると「秋かな」と思い、山が紅葉に変わりだしたころに200日が終わる。
千日回峰行では、700日の回峰が終わった後、9日間不眠、不臥、断食、断水でお経を唱える「堂入り」がある。1秒ずつ体力を消耗していく行で、自分で自分の体をどう調節するかが問題となる。
2日目になると唇が裂け、4日目になると手に紫斑が出てくる。5日目にうがいが許されるが、これはのどにたんがたまると窒息してしまうためだ。断水で体が乾燥し、水に執着をもっているせいか、水を受け取ったら手ががたがたと震えてしまう。煩悩がマグマのように爆発するのだ。吐き出さずに飲んでしまったら行は終わってしまう。たかが一杯の水に惑わされるとは、人間ってたいしたことないと思う。うがいの水は、いわば修行の道具立てかもしれない。
6・7日目になると手がどんどん冷たくなり、幻想が出てくる。お堂の中にいるのに、外にいる自分の姿が見えてくる。何かすーっと吸い込まれるような、いい気持ちになってきて、「このまま連れていかれたら、ええな」と考える。思えば死の行程(臨死体験)にあったのかもしれない。しかし最終的に「自分は何だろう」「何をしにここにきたのだろうか」と考えだし、学校を出て、これだけの行を行ううえで、大勢の人に支えられたことが思い出されてくる。その人たちに何をもって報いるかと考えると「もういいや」という気持ちは消え、行をちゃんとやった姿をみせなければと考えが変わる。そうして9日間が終わる。
堂入りが終わった後、衰弱した体力を戻すためにか27日間静養しなさいといわれる。何事も回復には3倍の時間がかかる。子どもの問題でも、50年間の間に起きたことなら、根本的に解決するには150年かかることをまず覚悟すべきだ。
戦後、親は生きるために一生懸命働いた。高度成長になると、みんなお金を持つようになり、執着するようになった。醤油を貸し合ったような長屋の暮らしは無くなり、心のゆとりもなくなった。そろばんを両手に暮らしているような、何かというとお金お金というのが今の社会。それで殺人事件が起こる。悪い人だけでなく、いい人も悪いことをする」
昭和から平成に変わる頃、父が死亡し、母が他界し、身軽になった私は企業の転勤要員になったのである。辞令という紙切れで動き回る風来坊家族である。東京そして滋賀県彦根市に落ち着いた。その頃に、比叡山の千日回峰行を知り、研究し、のめり込んだ思い出がある。滋賀銀行けいぶんの参禅会に七年通い、帰りには回峰道を細切れで歩き、踏破した。そして律院に叡南俊照師を訪ね、近江八幡の伊崎寺・仰木里覚性律庵で故光永澄道師に会い、飯室谷では酒井雄哉師の笑顔を頂戴し、教えを知ることが出来た。金万能の世間は不合理であることに気が付き、金儲けの為の借家住まいにおさらばして、父母の死んだ自宅に戻り、ささやかな仕事の合間に援農ボランティアが出来るおおらかな心を獲得することが出来、老後に不安がないのである。多くの金がなくてもなるようになるのが人間社会である。
![]()