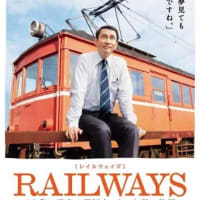境野勝悟氏の「禅の人間学」という番組をNHKの「心の時代」で見た。キリスト教の学校の教師が禅修業をした体験談である。西洋の一神教(契約宗教)と東洋の多神教(自覚宗教)を同時に修行した事になり、混乱したことだろう。
場所は静岡県三島市にある臨済宗妙心寺派の龍沢寺である。山本玄峰老師が指導者であった。
白隠禅師の「隻手音声」との宿題を携え、日々の作業をこなし、座禅に励んだ。両手で叩けば音が出るが、片手では音が出るわけがない。その音を聞けと言われれば、いったい何のことだろうと考えてしまう。その質問にとらわれてしまう。初期には頭で理屈を考え、話を作り褒めてもらおうとする。しかしことごとく、すべてを否定される。一年間否定されつくすと、答えは無くなってしまうが、顔つき・立ち居振る舞い・発想法・態度は師家や禅僧と同様な無駄の無く、美しい型にはまってしまう。面接の時には、答えられなく、ただ微笑むだけになる。その時に合格点をもらえるようである。理屈より主体的な自己責任の行動が大切なのである。
門前で土産物屋を営む弟子の「おさん婆さん」との対話が面白い。
白隠 「両掌相打って音声あり、隻手に何の音声かある」
おさん 「白隠の隻手の声を聞くよりも両手を打って商いをせん」
白隠 「商いが両手叩いてなるならば隻手の音は聞くにおよばず」
おさん婆さんは免許皆伝なのである。悟っているのである。
他人と比較する相対評価は程々に、あるがままの自分で利他の行動をすれば楽に生きられる。あるがままの自分の宿題を携え生き続けることが禅なのかもしれない。禅問答になった。
最新の画像[もっと見る]