最近封切りの映画「WOOD JOB」の原作本です。
映画化されるとかの話題なった本とかはなかなか図書館の書架にはないのですが、これは映画の題名とあまりにも違うので気が付かれなかったのか、書架に並んでいたので早速ゲット。
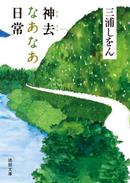
横浜の高校生が卒業後もやることなくフリーターでもしていようかと思っていたら、教師と母親の陰謀?でいきなり三重県の山奥に連れていかれて林業に携わる。林業就業者を養成する「緑の雇用制度」に勝手に申し込まれたみたいです。
ずぶの素人が林業に徐々に慣れてきて、村にも親しんでくるとともに村の人々にも受け入れられてくる1年を描いています。
個人的なことですが、職場の同僚の親族の葬式があって、三重県の飯高村まで行ったことがあります。今は編入されて松阪市になっていますが、当時久居からどんどん山の中に入って行って、峠を越せば奈良県と言うところ。国道も冬期は凍結のため通行止めで峠を越えることができないというような山の中でした。道がわからなくて葬式はどこでやっているのかと村の人に聞いたら「この道をまっすぐ2キロぐらい行くと三差路があるのでそこを右に行くとわかる」と答えられた時にはびっくり。私は20メートル先の家で葬式があっても知りません。
そんな辺鄙なところに都会人がいきなり行ったらカルチャーショックで茫然自失するしかありません。
それでも主人公の先輩にして指導者役の「ヨキ」のハチャメチャにしてスーパーマンのような姿はなんとかっこいいことか斧一本で伐採を行い木から木へ飛び移る。ターザンかですが、主人公の勇気を優しくではないのですが、ちゃんと見ています。親方の清一さんも思慮深く魅力的で、一緒のチームの人たちもやさしく接してくれます。そんなこんなでなれない山奥の暮らしにも徐々に馴染んでいくのですが、日本の現在の林業の厳しさもよく描写されています。
題名にもある「なあなあ」とは神去村の方言。「ゆっくり行こう」とか「まあ落ち着け」と言うような意味ですが、そこから派生していろいろな意味に使われるようになり、日常会話のあらゆる場面で、この「なあなあ」で済んでしまうような…
三重県側から奈良へ抜けるあたりの紀伊半島は山深く、諸戸産業とか速水林業とかの全国的にも知られている大山林地主もいます。参考資料を見ると尾鷲市周辺がモデルのようですが、山里はいくつもあって同じような文化があると思います。
春から夏、そして秋と季節の移り変わりとともに山仕事があり、夏祭りがあり、川で水遊びし、山火事の恐ろしさと命がけの消火作業、そして秋祭りがある。神去祭りは諏訪の御柱祭りを思わせるのですが、千年杉を切り出しそれに乗って山の斜面を滑り降りてくるというインディジョーズ真っ青のさらにありえないような展開で笑ってしまいます。
これも個人的なことですが、かみさんの実家は岡崎の山奥、今は亡き額田町ですが、携帯の電波は通じず、シカや猿が出るというところですので、山の生活の描写には妙に納得してしまいます。幸いなことに山道とを歩いていってもヒルとかダニに遭遇したことはないのですが、草いきれの中を歩いていると何が出てきてもおかしくありません。側溝に沢蟹がいて蛍が飛んでいるというと美しいのですが、そればかりではないのが現実です。
主人公のこれからはどうなっていくのか、淡い恋はどうなるのかと中途半端と言えば中途半端な終わり方ですので続編が期待できます。見ていないのですが映画の出来はどうなんでしょうか。小説は面白かったですね。
映画化されるとかの話題なった本とかはなかなか図書館の書架にはないのですが、これは映画の題名とあまりにも違うので気が付かれなかったのか、書架に並んでいたので早速ゲット。
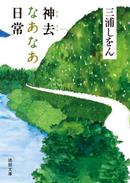
横浜の高校生が卒業後もやることなくフリーターでもしていようかと思っていたら、教師と母親の陰謀?でいきなり三重県の山奥に連れていかれて林業に携わる。林業就業者を養成する「緑の雇用制度」に勝手に申し込まれたみたいです。
ずぶの素人が林業に徐々に慣れてきて、村にも親しんでくるとともに村の人々にも受け入れられてくる1年を描いています。
個人的なことですが、職場の同僚の親族の葬式があって、三重県の飯高村まで行ったことがあります。今は編入されて松阪市になっていますが、当時久居からどんどん山の中に入って行って、峠を越せば奈良県と言うところ。国道も冬期は凍結のため通行止めで峠を越えることができないというような山の中でした。道がわからなくて葬式はどこでやっているのかと村の人に聞いたら「この道をまっすぐ2キロぐらい行くと三差路があるのでそこを右に行くとわかる」と答えられた時にはびっくり。私は20メートル先の家で葬式があっても知りません。
そんな辺鄙なところに都会人がいきなり行ったらカルチャーショックで茫然自失するしかありません。
それでも主人公の先輩にして指導者役の「ヨキ」のハチャメチャにしてスーパーマンのような姿はなんとかっこいいことか斧一本で伐採を行い木から木へ飛び移る。ターザンかですが、主人公の勇気を優しくではないのですが、ちゃんと見ています。親方の清一さんも思慮深く魅力的で、一緒のチームの人たちもやさしく接してくれます。そんなこんなでなれない山奥の暮らしにも徐々に馴染んでいくのですが、日本の現在の林業の厳しさもよく描写されています。
題名にもある「なあなあ」とは神去村の方言。「ゆっくり行こう」とか「まあ落ち着け」と言うような意味ですが、そこから派生していろいろな意味に使われるようになり、日常会話のあらゆる場面で、この「なあなあ」で済んでしまうような…
三重県側から奈良へ抜けるあたりの紀伊半島は山深く、諸戸産業とか速水林業とかの全国的にも知られている大山林地主もいます。参考資料を見ると尾鷲市周辺がモデルのようですが、山里はいくつもあって同じような文化があると思います。
春から夏、そして秋と季節の移り変わりとともに山仕事があり、夏祭りがあり、川で水遊びし、山火事の恐ろしさと命がけの消火作業、そして秋祭りがある。神去祭りは諏訪の御柱祭りを思わせるのですが、千年杉を切り出しそれに乗って山の斜面を滑り降りてくるというインディジョーズ真っ青のさらにありえないような展開で笑ってしまいます。
これも個人的なことですが、かみさんの実家は岡崎の山奥、今は亡き額田町ですが、携帯の電波は通じず、シカや猿が出るというところですので、山の生活の描写には妙に納得してしまいます。幸いなことに山道とを歩いていってもヒルとかダニに遭遇したことはないのですが、草いきれの中を歩いていると何が出てきてもおかしくありません。側溝に沢蟹がいて蛍が飛んでいるというと美しいのですが、そればかりではないのが現実です。
主人公のこれからはどうなっていくのか、淡い恋はどうなるのかと中途半端と言えば中途半端な終わり方ですので続編が期待できます。見ていないのですが映画の出来はどうなんでしょうか。小説は面白かったですね。















