
実は本展までエルンスト・バルラハという名を全く聞いたことがなかった。日本でも今回のような大規模な回顧展は初めてだそうである。ドイツ表現主義の仕事はドイツと第2次大戦期同盟国であった日本では比較的早く紹介されたそうである。しかし、ナチスドイツの「頽廃芸術」攻撃で、ヨーロッパにおける彫刻分野での紹介、発掘は遅れ、また日本でも彫刻までは紹介されなかった。もちろんドイツ表現主義を代表するキルヒナーは絵画以外にも版画や彫刻も手がけていたが、彫刻の紹介は少ない。そしてバルラハ。近代彫刻というとロダンとその弟子、ブールデル、マイヨール、デスピオらに焦点が当てられ、ドイツの近代彫刻ーバルラハはもちろん、コルヴィッツなど ー に光があてられることは少ない。しかし、ナチスドイツの恣意的なレッテル貼りによって不遇の制作を余儀なくされた作家は多い。ノルデやディックス、カンディンスキーなども。そして1938年ナチスの伸長する時代に失意のまま世を去ったバルラハ。
バルラハの彫刻を一口で言い表すことなどできないが、まず木彫作品に見いだせる中世ゴシックの影響は見逃せ得ない。筆者はバルラハの木彫にリーメンシュナイダーの人間に対する深い観察眼 ー それは教会彫刻を手がけたキリスト教主題であっても人間の魂により近づいたとも呼ぶべき洞察力の発現に他ならない ー を見た気がしたのだが、ロダン、ブールデルらの言わば人間=生及び動の讃歌的な作品とは対局をなす重い、暗い、静謐な作品群にそれは表れている。
リーメンシュナイダーの彫刻は、こちらが作品を見ているのではなくて、作品の側が、私たちを見ていると表現したのは高柳誠だが(『中世最後の彫刻家 リーメンシュナイダー』五柳書院)、バルラハの彫刻も伏し目がちのかたい表情とはうらはらに、こちらの気配を作品の方こそ感じているようである。
ノミの跡一つ一つにはバルラハの人生の痕跡、いや、両大戦期の暗いドイツの雰囲気やあるいはナチスの度重なる迫害に抗おうとした一彫刻家の悲しみや怒りがこめられているのかもしれない。
代表作「ベルゼルケル(戦士)」や「苦行者」はもちろん荒れた都会の雰囲気に嫌気がさしロシアの農村を旅した後いくつも制作したロシア農民らの姿といい、どの作品も見るものがこちらから主体的な力でもって見ることをやめるのを許さないほど引き込まれること間違いない。
やはり彫刻はいい。
バルラハの彫刻を一口で言い表すことなどできないが、まず木彫作品に見いだせる中世ゴシックの影響は見逃せ得ない。筆者はバルラハの木彫にリーメンシュナイダーの人間に対する深い観察眼 ー それは教会彫刻を手がけたキリスト教主題であっても人間の魂により近づいたとも呼ぶべき洞察力の発現に他ならない ー を見た気がしたのだが、ロダン、ブールデルらの言わば人間=生及び動の讃歌的な作品とは対局をなす重い、暗い、静謐な作品群にそれは表れている。
リーメンシュナイダーの彫刻は、こちらが作品を見ているのではなくて、作品の側が、私たちを見ていると表現したのは高柳誠だが(『中世最後の彫刻家 リーメンシュナイダー』五柳書院)、バルラハの彫刻も伏し目がちのかたい表情とはうらはらに、こちらの気配を作品の方こそ感じているようである。
ノミの跡一つ一つにはバルラハの人生の痕跡、いや、両大戦期の暗いドイツの雰囲気やあるいはナチスの度重なる迫害に抗おうとした一彫刻家の悲しみや怒りがこめられているのかもしれない。
代表作「ベルゼルケル(戦士)」や「苦行者」はもちろん荒れた都会の雰囲気に嫌気がさしロシアの農村を旅した後いくつも制作したロシア農民らの姿といい、どの作品も見るものがこちらから主体的な力でもって見ることをやめるのを許さないほど引き込まれること間違いない。
やはり彫刻はいい。















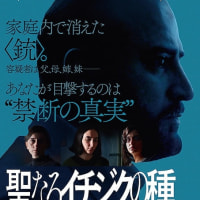


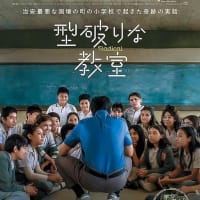






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます