
秋篠宮家に対する批判的な報道が減らないように思える。紀子妃が女帝のごとく君臨しているだの、長女眞子がいつまでもフィアンセであった小室圭さんとの関係を断ち切れないだの、次女佳子は奔放な発言が目立つなどと。その逐一の信憑性と影響については詳しくは分からないが、その社会的・政治的意味が明らかになるのは後年、原武史さんのような学者が幅広い資料を渉猟、綿密に分析して跡づけてからであろう。
近代の天皇・皇室・神道研究の第一の担い手、原武史さん(放送大学教授)の大部『皇后考』(2015年 講談社)は、明治以降3代の皇后についての論考だが、その多くを割いているのが大正天皇嘉仁の妃であった節子(さだこ)の生涯についてである。明治天皇睦仁の皇后美子が容姿により妃に選ばれた先例に対し、多くの妾を抱えるそれまでの宮中のあり方から、西洋的な一夫一婦制が目指された故、容姿より、強く、健康な身体=男の子をたくさん産める、女性が選ばれたのである。容姿的には節子に優っていた妃候補(伏見宮貞愛第一皇女禎子(さちこ))がいたが、健康ではないとして「皇太子婚約解消事件」として、却下され、九条道孝皇女節子が皇太子妃となった。1879年(明治12)、節子15歳。「黒姫」と呼ばれるほど肌の色が濃かったが、健康重視の結果であった。
宮中の思惑通り、節子は男子を4人ももうけた。第一子裕仁が昭和天皇、(秩父宮となる)雍仁(やすひと)、(同高松宮)宣仁(よしひと)、(同三笠宮)崇仁(たかひと)である。既知のとおり、裕仁には明仁(1933年生)、(同常陸宮)正仁(1935年生)の二人の男子ができた。しかし、現天皇徳仁(なるひと、1960年生)に次いで、冒頭の秋篠宮文仁(ふみひと、1965年生)に悠仁(ひさひと)が生まれる2006年まで41年もの間男子が生まれなかったのである。浮気性で病弱だった嘉仁が皇室行事ができなくなって、節子は「神がかり」的となり、嘉仁の治癒を神に願うとともに、自らを神功皇后になぞらえていく。神功皇后とは、仲哀天皇の妃であり、応神天皇の母とされるが、現代の通説ではその存在は否定されている。しかし『日本書紀』によれば、自ら朝鮮半島に渡って軍の指揮をとり、「三韓(新羅、百済、高句麗)征伐」をなしたとされる。しかし、人物そのものの存在も疑われるくらいであるから「征伐」の年代、態様ともに疑義を挟む研究が多い。応神天皇が成人になるまで摂政を務めたとされる神功皇后に自己を引き寄せ、嘉仁に裕仁摂政が誕生した後には、隠然たる権力をほしいいままにする。長男である裕仁を疎んじ、次男雍仁を溺愛、嘉仁死後皇太后となってからの日中戦争後は、ひたすら「勝ち戦」を神に頼む。その神がかりの強さに怖さを感じた女官も。病気療養に専念していた秩父宮雍仁の静養先に近い沼津の御用邸に長逗留するも、頻繁に出かけ、祭神を祀る神社に幾度も詣でて、ライ病(ハンセン病)療養所を訪れ、「防ライ運動」に熱心に取り組み、養蚕事業に理解が深かった姿は、光明皇后も想起させる(ただし、療養所を訪れても患者に接することはなかった)。それほどまでに神功皇后をはじめとして、遡ってはアマテラス、光明皇后など過去の皇室関係の偉人の女性などに自分を重ねようとした人物だった。しかしあれほどまでに戦争を鼓舞した戦犯意識は皆無で「戦中期の言動に対して自ら責任をとるという発想はなかったのである」(553頁)。
ところで「天皇の戦争責任」とは一般的に言われるが、そこには「皇室全員の戦争責任」であることを含んでいる。特に対米戦争開戦強硬派であった高松宮宣仁は帝国軍人、軍艦に皇后として初めて乗船し喜んだという皇后良子(ながこ)、銃後の施設への慰問に訪れた各妃ら、そして自ら軍神になぞらえた感もある貞明皇太后。厚いベールに包まれるとされる宮中のそれぞれの人の思惑、行動などを膨大な資料を持って明らかにしていく様はスリリングでもある。あれだけ「勝ち戦」に拘っていた貞明皇太后が、裕仁のポツダム宣言受け入れ時には、抵抗せず、あっけらかんとしているあたり、空襲がある東京におらず、戦時の窮乏も知らず、戦火も戦禍も経験しなかった場所にいた人間の無知、無見識、非常識からと考えると腹立たしさも浮かんでこないほどだ。
原さんは、鉄道オタクとしても有名で、鉄道史その他関連本もたくさん著している。そのスジの凝り性からか、皇室の御召列車の記述の際には、「○○線の○○駅から○○駅までで、現在の特急○○の」と言ったような説明が出てくるが、特急の名称まで要らないんじゃないかと思うが、そこがやはり原さんにとって大切なところなのだろう。笑ってはいけない。












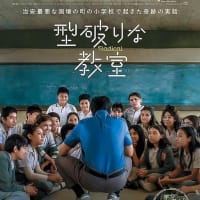












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます