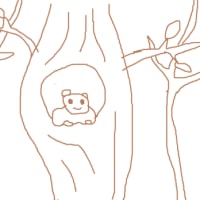子路さんのハナウタには、ピシャリと「そんなことではダメだ」とおっしゃられた先生は、ご自身はどんな歌をうたっておられたんでしょう。
子かん編の一番最後にこういうのがありました。先ずは、岩波文庫版で見てみます。
唐棣(とうてい)の華(はな)、偏(へん)として其(そ)れ反(はん)せり。
豈(あ)に爾(なんじ)を思(おも)わざらんや。
室(しつ)是(こ)れ遠(とお)ければなり。
唐棣(にわざくら)の花、ひらひらかえる。
お前恋しと思わぬでないが、
家がそれ遠すぎて。
孔子先生は、楽器もされるし、歌もうたう。独唱だけではなくて、合唱する時も、みんなのハーモニーを大切にする歌い方を工夫されたということでした。
どんなことを歌うのか、その歌詞が気になるところでした。
孔子さんたちの必読書「詩経」は、古代のいろいろな詩が載っているそうで、みんなが教養としてそれを学んでいます。この詩はそこに載っていない作品なんだそうです。
例によって、たいした内容がそこに書かれているとは思えない。
ただ、ひらひら落ちる花びらを見ていて、あなたが恋しいなどと思ってしまう。けれども、二人の距離が離れすぎていて、どうにもならないものがある。でも、あいかわらず恋しい、そういう内容のようです。

子(し)の曰(い)わく、未(いま)だこれを思(おも)わざるなり。夫(そ)れ何(なん)の遠(とお)きことかこれ有(あ)らん。
先生は[この歌について]言われた。「思いつめていないのだ。まあ、本当に思いつめさえすれば、何の遠いことがあるものか。」
というふうに言われたそうです。
岩波文庫も、わりと頑張って雰囲気を出そうと努力しているみたいです。

下村湖人さんはどんなふうに訳しておられるんでしょう。
民謡にこういうのがある。
ゆすらうめの木
花咲きゃ招く、
ひらりひらりと
色よく招く。
招きゃこの胸
こがれるばかり、
道が遠くて
行かりゃせぬ。
先師はこの民謡をきいていわれた。――
「まだ思いようが足りないね。なあに、遠いことがあるものか」
ゆすらうめの木
花咲きゃ招く、
ひらりひらりと
色よく招く。
招きゃこの胸
こがれるばかり、
道が遠くて
行かりゃせぬ。
先師はこの民謡をきいていわれた。――
「まだ思いようが足りないね。なあに、遠いことがあるものか」
* 私は孔子が「ほれて通えば千里も一里」という日本の民謡を知っていたら、とそれが惜しくてならない。
漢文の三行の詩を、下村先生は八行に書いておられます。こんな詩になって、好きな人は遠いから、結ばれることはない、という悲観的な内容になっていました。
でも、先生は、そうではなくて、恋しい気持ちがあったら、とことん遠くても突き進んでみなさい。それが恋しい自分を素直に表現することではないのか。自分に忠実に生きてみよ! と励ましてくださっている。
そうか。強い思いをもって、恋しい人にぶつかりなさい。花がひらひらおちる自然の摂理の中で、人が人恋しく思うのは当たり前のことで、どんなに遠くても、自らの気持ちを優先させなさい、ということでした。

恋しかったら、恋しい彼女にどこまでも行ってみなさい!
孔子先生がそんなことをおっしゃったなんて、何だか不思議です。本当にこれ、「論語」なんだろうか? そう思って抜き書きしました。