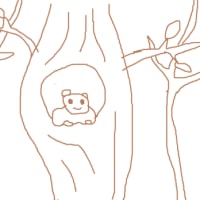さて、今日のテーマはなんですか? 持ててるフリなのか、本当に持てたのか、それはわからないけれど、歌の世界では持てていますね。
砂山の砂に腹這(はらば)ひ
初恋の
いたみを遠くおもひ出(い)づる日
……これは作り上げた歌の世界です。でも、こんなのが作れるから、やはりセンスがありますね。
初恋と砂山なんて、なかなか組み合わせられません。初恋につながるものといえば、もう私たちはパターン化されていて、つまらないイメージしか出てこないけれど、ズバリ「砂山」を持ってきて、「腹ばい」になってしまうんですよ。私たちなら「腹ばい」にはなりません。
もっと胸が高鳴り、ジャンプして、小躍りして、もっとわざとらしい表現をいっぱい書くでしょう。でも、彼はそんなのは書きません。
しかも、それはいたみをともなうものだった。もっともっと私たちは傷つかないと、啄木世界へ入っていけないのかも……。いや、味わえたら、それでいいですね。
放(はな)たれし女のごときかなしみを
よわき男の
感ずる日なり
……放たれし女とはどんな女の人なんだろう。男から別れさせられた女、離縁された女ということだろうか。百年の間に時代は変わった。放たれるのはたいてい男になってしまった。そして、今、大半の男は、つかんでももらえず、ずっと放たれたまま、このまま死んでいくのだろう。
かくして日本は、老人と孤独な三十代、四十代をかかえる、小さな国へと進むのでしょう。百年は国の形を変えるものなのですね。
きっと22世紀は、日本は小さな、産業集積地になっていくでしょう。それはそれでいいかもしれない。けれど、世界はこのまま人口爆発がつづくだろうか。それもわからないです。
啄木の時代の男は、平和でいいですね。でも、命を張って戦いに出ていたのでしょうね。それが今とは違うところです。これは進歩だと思うのだけれど、何だか不幸な感じがするのはどうしてかなあ。いや、今は啄木たちの時代より平和に関してはしあわせというのが正しいかな。
女あり
わがいひつけに背(そむ)かじと心を砕(くだ)く
見ればかなしも
……そんな「恋の奴隷」みたいな女の人、昔はいたんですね。歌では知っていますが、なんだか面倒だなと思うのは私だけでしょうか。いや、こんな人は啄木の時代でも理想であり、フィクションでしょう。
ふがひなき
わが日(ひ)の本(もと)の女等(おんなら)を
秋雨の夜(よ)にののしりしかな
……こっちが本当です。やはり女の人は、啄木の思い通りに動いてはくれないのです。それで、ダダをこねてる啄木君でした。かわいらしいなあ。
文庫本の注では、ロシア革命のように、女の人たちも立ち上がれと言いたかった、という解釈です。これから8年後に富山で米騒動が起きて、女性たちは立ち上がるのですから、時期はすでに来ていて、啄木はそれを予見していたというところかな。これも恋の歌ではないですね。ザンネンでした。
先んじて恋のあまさと
かなしさを知りし我なり
先んじて老ゆ
……まるで2年後の自らの死を予感しているような、それを書かずにはおられない、ものすごく焦って生きている啄木が、ふともらしたため息のような歌です。人に先んずることが大好きだった彼は、人生そのものもあっという間に終わらせてしまいます。
それを思うと、ザンネンで仕方ないけれど、彼には彼の充実感はあったと思うし、後の私が悔やんでもどうにもならないことです。結核はみんながなる可能性があって、みんな短い人生を終えていくのが当たり前でした。
だから、啄木自身にそれほどの悔いはなかったでしょう。そういうものだと思っていたし、人生は短く、その中でどれだけやれるかがすべてでした。今はあまりに長い老後があるという恐怖があって、自分がいつおかしくなったり、寝たきりになったり、介護されたり、楽しい老後がイメージできないのです。
どっちがいいかな。短いからせいぜい頑張る人生と、だらだら盛り上がりのない、最後が不安だらけの人生。私はバカモノだから、どんなにみじめでもいいから、ダラダラ生きて行けたらいいなと思っていますけど……。
★ 今日は、奥さんがいなくて、さびしい夜をすごしています。だれとも会話をせず、パソコンに向かっているだけなので、それこそダラダラです。いい加減に諦めて、明日の朝、何か書こうと思います。失礼しました。
砂山の砂に腹這(はらば)ひ
初恋の
いたみを遠くおもひ出(い)づる日
……これは作り上げた歌の世界です。でも、こんなのが作れるから、やはりセンスがありますね。
初恋と砂山なんて、なかなか組み合わせられません。初恋につながるものといえば、もう私たちはパターン化されていて、つまらないイメージしか出てこないけれど、ズバリ「砂山」を持ってきて、「腹ばい」になってしまうんですよ。私たちなら「腹ばい」にはなりません。
もっと胸が高鳴り、ジャンプして、小躍りして、もっとわざとらしい表現をいっぱい書くでしょう。でも、彼はそんなのは書きません。
しかも、それはいたみをともなうものだった。もっともっと私たちは傷つかないと、啄木世界へ入っていけないのかも……。いや、味わえたら、それでいいですね。
放(はな)たれし女のごときかなしみを
よわき男の
感ずる日なり
……放たれし女とはどんな女の人なんだろう。男から別れさせられた女、離縁された女ということだろうか。百年の間に時代は変わった。放たれるのはたいてい男になってしまった。そして、今、大半の男は、つかんでももらえず、ずっと放たれたまま、このまま死んでいくのだろう。
かくして日本は、老人と孤独な三十代、四十代をかかえる、小さな国へと進むのでしょう。百年は国の形を変えるものなのですね。
きっと22世紀は、日本は小さな、産業集積地になっていくでしょう。それはそれでいいかもしれない。けれど、世界はこのまま人口爆発がつづくだろうか。それもわからないです。
啄木の時代の男は、平和でいいですね。でも、命を張って戦いに出ていたのでしょうね。それが今とは違うところです。これは進歩だと思うのだけれど、何だか不幸な感じがするのはどうしてかなあ。いや、今は啄木たちの時代より平和に関してはしあわせというのが正しいかな。
女あり
わがいひつけに背(そむ)かじと心を砕(くだ)く
見ればかなしも
……そんな「恋の奴隷」みたいな女の人、昔はいたんですね。歌では知っていますが、なんだか面倒だなと思うのは私だけでしょうか。いや、こんな人は啄木の時代でも理想であり、フィクションでしょう。
ふがひなき
わが日(ひ)の本(もと)の女等(おんなら)を
秋雨の夜(よ)にののしりしかな
……こっちが本当です。やはり女の人は、啄木の思い通りに動いてはくれないのです。それで、ダダをこねてる啄木君でした。かわいらしいなあ。
文庫本の注では、ロシア革命のように、女の人たちも立ち上がれと言いたかった、という解釈です。これから8年後に富山で米騒動が起きて、女性たちは立ち上がるのですから、時期はすでに来ていて、啄木はそれを予見していたというところかな。これも恋の歌ではないですね。ザンネンでした。
先んじて恋のあまさと
かなしさを知りし我なり
先んじて老ゆ
……まるで2年後の自らの死を予感しているような、それを書かずにはおられない、ものすごく焦って生きている啄木が、ふともらしたため息のような歌です。人に先んずることが大好きだった彼は、人生そのものもあっという間に終わらせてしまいます。
それを思うと、ザンネンで仕方ないけれど、彼には彼の充実感はあったと思うし、後の私が悔やんでもどうにもならないことです。結核はみんながなる可能性があって、みんな短い人生を終えていくのが当たり前でした。
だから、啄木自身にそれほどの悔いはなかったでしょう。そういうものだと思っていたし、人生は短く、その中でどれだけやれるかがすべてでした。今はあまりに長い老後があるという恐怖があって、自分がいつおかしくなったり、寝たきりになったり、介護されたり、楽しい老後がイメージできないのです。
どっちがいいかな。短いからせいぜい頑張る人生と、だらだら盛り上がりのない、最後が不安だらけの人生。私はバカモノだから、どんなにみじめでもいいから、ダラダラ生きて行けたらいいなと思っていますけど……。
★ 今日は、奥さんがいなくて、さびしい夜をすごしています。だれとも会話をせず、パソコンに向かっているだけなので、それこそダラダラです。いい加減に諦めて、明日の朝、何か書こうと思います。失礼しました。