京都。東本願寺と西本願寺に、現行NHK大河ドラマの織田信長の真意を知りたくて、行ってきました。
大好きな、歴史現地取材です。
さてまずは・・・
現在の両寺の基本勉強です。
浄土真宗東本願寺派 『東本願寺』 御影堂

創建年:1602年 宗祖:親鸞聖人。 ご本尊:阿弥陀如来。
寺院数 :8607院 信者数: 5,333,146人
二つの本願寺の『宗祖』。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)
1173年:京都の日野の里で誕生。9歳:比叡山で学び初め。29歳:師・法然聖人と出遇い、本願念仏の道に入る。
90年の生涯:「煩悩に満ちた私たちは、阿弥陀如来のみ教えを仰ぐことこそ、苦しみの世を生き抜く道である」と教える。
浄土真宗本願寺派 『西本願寺』 総門

創建年:1591年 宗祖:親鸞聖人。 ご本尊:阿弥陀如来。
寺院数:10275院 信者数: 6,940,967人
二つの本願寺の『ご本尊』。
阿弥陀如来(あみだにょらい)
極楽浄土にあって、大悲の本願をもって生きとし生けるもの、すべてを平等に救済してくださる仏様。
『お念仏』は、私たち全てを救いとってくださる阿弥陀如来への『報恩感謝のしるし』。 ・・・だそうです。
次にいよいよ・・・
本願寺派:西本願寺 と 織田信長の
『石山合戦』 信長の本心・真意 の検証。 迫ります。
信長以前にも。
1532年: 細川晴元は、京都山科を本拠としていた『大谷本願寺:西本願寺』を、その勢力を恐れて、焼き討ち。
大谷本願寺を失くした西本願寺。
西本願寺・10世法王・証如: 交通の便の良い大坂御坊:『石山本願寺』を建立。 本願寺の本拠とする。
(現大阪城。あたりだそうです)
その後。
本願寺の勢力は、年々増大して、中央集権との結びつきが強くなった。
信長の時代になって。
1568年: 織田信長が上洛に成功。すぐに畿内をほぼ制圧する。
1570年9月12日:本願寺法王・顕如は、「信長が本願寺を破却すると言ってきた」として、突如、織田軍を攻撃。 激突する。
1571年: 信長は、長島願証寺で起こった、『一向一揆』の壊滅を図る。 失敗。
1572年: 本願寺法王・顕如は、武田信玄や毛利輝元などと密かに同盟を結んで、信長を東西から挟撃しよう、と画策する。
信長の危機。
『西本願寺』と『一向一揆』、『畿内勢力』から攻められる。
西本願寺: 長島・越前・石山の3拠点で、信長と戦う。
一向一揆勢: 長島・屋長島・中江の3箇所に篭るが、信長の兵糧攻めに耐え切れず、降伏開城する。
結果は・・・一揆勢を焼き殺した。 指導者の願証寺の顕忍は自害。
『西本願寺』は将軍と組む。
1576年: 本願寺法王・顕如は、毛利輝元に庇護されていた将軍足利義照と与して、三度の挙兵。
戦いは続いて。
1578年: 信長は、朝廷を動かして、本願寺法王・顕如と、和解を試みる。
本願寺・顕如は、毛利氏の賛同がないと応じられないと、和解を拒否。
1579年: 本願寺・顕如は、将来の弾薬や食料の欠乏を恐れて、密かに朝廷に、信長との和解話のやり直しを頼む。
そしてついに・・・
1580年3月1日: 本願寺は和議を推し進めることで合意。 信長も本願寺側との妥協点を探った。
3月7日: 本願寺は信長に『誓紙の筆本』を提出。 信長と本願寺は3度目の講話を果たす。
1570年~1580年。 10年間の、信長と西本願寺の『石山合戦』、に終止符が打たれる。
よそ者であり、『天下統一』『天下布武』、を実現する信長の道程は、簡単ではありません。
『本願寺野本拠地』…京都山科で細川氏の焼き討ち→大坂石山で信長に降伏→次はどこへ?→現京都に移る。
この続きの、信長と本願寺の検証は次回に。 お楽しみに。
ここで・・・
今回の二つの本願寺訪問での 驚きの発見と報告です。
静かな厳粛な 『東本願寺』 静けさこそが日本の寺の良さと感動でした。

『参拝接待所』
沢山の一般人が、静かに座っていました。
『剃刀の儀』(かみそり儀)を待っている方々です。
『剃刀の儀』。
『帰敬式』(ききょう式)が正式名。
仏・法・僧の三宝に帰依し、
南無阿弥陀仏の教えを拠りどころとして人生を歩むと、『新たに誓う』、真宗門徒の『出発式』。 だそうです。
『その時』を静かに待つ人たち。
敬意を称して、皆様に敬礼して 、静かに立ち去った私です。
、静かに立ち去った私です。
静かな東本願寺から歩いて・・・
次に到着。
にぎやか。大勢の人人。キラキラ。派手。東本願寺と対照的。 『西本願寺』

今日は親鸞の誕生日。大イベント中でした。 『宗祖・親鸞聖人:降誕会』
寺の外。沢山ののぼりがたなびきます。
寺の内。
沢山の僧侶と一般人。 『親鸞聖人降誕祝賀会』

沢山の雅師による奉納。 『雅歌』 沢山の僧侶 と 信徒 と 参拝者。


式典は厳かに施行されていました。
その隣は
『龍虎殿』。
休憩所でした。
こちらでも・・・東本願寺同様に、『剃刀の儀』 の方々が御待ちでした。
若いお坊さんがアナウンス。「剃刀の儀にご参加の方はお名前をお呼びします。 申込書をお出し下さい。」 と。
名前を呼ばれる方の多いのには、私は心底驚きました。
驚いた私。
お名前を呼ぶお坊さんの所へ行って、尋ねました。
「沢山の方が帰依なさるのはすばらしいことですね。 立派ですね。
皆様は、1年間とか2年間とか仏教をお勉強なさって、今日の日をお迎えになったのですか?」 と。
お坊さんの答。
「いいえ。 あなた様もいかがですか? 剃刀の儀に今からでも参加できますよ。
キリスト教をご存知でしょうか? キリスト教の洗礼の時には『クリスチャンネーム』を頂きます。
キリスト教同様に、剃刀の儀を終えた人は、『法名』を頂きます。
剃刀の儀とは、仏教徒になるという『宣誓式』です。
勉強はそれからです。 今日から私も釈迦様の弟子になるとの表明の儀です。」 と。優しく教えてくれました。
えぇ~!!
今日! 希望者は、何の知識もなくとも、仏教徒になる儀式に参加できるのです!!
坊さまの説明は、キリスト教からの説明でした。 えぇ~!!
更に驚いた私。 調べてみました。
『剃刀の儀』
西本願寺でも東本願寺でも、毎日原則年中無休で朝昼の2回、執り行われています。
『お礼金』は『一人1万円』。
『法名』と『略肩衣』(仏と対面時に威儀を正す、門徒の正装)を頂きます。
『戒名』と『法名』の違い。
「戒名」とは、戒律を守って生活する人、つまり 受戒を受けた人に与えられる名前。
「法名」とは、仏法に帰依した人に与えられる名前で、戒律のない浄土真宗では「戒名」とはいわず、「法名」を用います。
長くなりましたので…今日はここまでで。 御粗末様でございました
5月21日。復活節第五水曜日。
『今日の御言葉』
『イエスは弟子たちに言われた。
「わたしはぶどうの木。あなた方はその枝である。
人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。」』
ヨハネ福音書 15章5節
『ぶどうの実』は 『愛の実』ですよね。
人はいろいろの行動をします。 でもそこに『愛』がなければ、『ぶどうの実』ではない。てことですよね。
イエスの生活は、すべてが、『愛』ある生活でした。
私たちも、神から力を頂いて、イエスの生活に倣って、『ぶどうの実』を結びましょう!
きっと・・・
仏教徒も皆様も、御釈迦さんに倣って、『ぶどうの実』を結んでいらっしゃるのでしょうね!
皆様!
御訪問に感謝申し上げます。 お元気ですか?
織田信長真意検証の旅からも学ぶことがいっぱいです。 人は一生学び。 そして 一生青春ですね!
大好きな、歴史現地取材です。
さてまずは・・・
現在の両寺の基本勉強です。
浄土真宗東本願寺派 『東本願寺』 御影堂

創建年:1602年 宗祖:親鸞聖人。 ご本尊:阿弥陀如来。
寺院数 :8607院 信者数: 5,333,146人
二つの本願寺の『宗祖』。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)
1173年:京都の日野の里で誕生。9歳:比叡山で学び初め。29歳:師・法然聖人と出遇い、本願念仏の道に入る。
90年の生涯:「煩悩に満ちた私たちは、阿弥陀如来のみ教えを仰ぐことこそ、苦しみの世を生き抜く道である」と教える。
浄土真宗本願寺派 『西本願寺』 総門

創建年:1591年 宗祖:親鸞聖人。 ご本尊:阿弥陀如来。
寺院数:10275院 信者数: 6,940,967人
二つの本願寺の『ご本尊』。
阿弥陀如来(あみだにょらい)
極楽浄土にあって、大悲の本願をもって生きとし生けるもの、すべてを平等に救済してくださる仏様。
『お念仏』は、私たち全てを救いとってくださる阿弥陀如来への『報恩感謝のしるし』。 ・・・だそうです。
次にいよいよ・・・
本願寺派:西本願寺 と 織田信長の
『石山合戦』 信長の本心・真意 の検証。 迫ります。
信長以前にも。
1532年: 細川晴元は、京都山科を本拠としていた『大谷本願寺:西本願寺』を、その勢力を恐れて、焼き討ち。
大谷本願寺を失くした西本願寺。
西本願寺・10世法王・証如: 交通の便の良い大坂御坊:『石山本願寺』を建立。 本願寺の本拠とする。
(現大阪城。あたりだそうです)
その後。
本願寺の勢力は、年々増大して、中央集権との結びつきが強くなった。
信長の時代になって。
1568年: 織田信長が上洛に成功。すぐに畿内をほぼ制圧する。
1570年9月12日:本願寺法王・顕如は、「信長が本願寺を破却すると言ってきた」として、突如、織田軍を攻撃。 激突する。
1571年: 信長は、長島願証寺で起こった、『一向一揆』の壊滅を図る。 失敗。
1572年: 本願寺法王・顕如は、武田信玄や毛利輝元などと密かに同盟を結んで、信長を東西から挟撃しよう、と画策する。
信長の危機。
『西本願寺』と『一向一揆』、『畿内勢力』から攻められる。
西本願寺: 長島・越前・石山の3拠点で、信長と戦う。
一向一揆勢: 長島・屋長島・中江の3箇所に篭るが、信長の兵糧攻めに耐え切れず、降伏開城する。
結果は・・・一揆勢を焼き殺した。 指導者の願証寺の顕忍は自害。
『西本願寺』は将軍と組む。
1576年: 本願寺法王・顕如は、毛利輝元に庇護されていた将軍足利義照と与して、三度の挙兵。
戦いは続いて。
1578年: 信長は、朝廷を動かして、本願寺法王・顕如と、和解を試みる。
本願寺・顕如は、毛利氏の賛同がないと応じられないと、和解を拒否。
1579年: 本願寺・顕如は、将来の弾薬や食料の欠乏を恐れて、密かに朝廷に、信長との和解話のやり直しを頼む。
そしてついに・・・
1580年3月1日: 本願寺は和議を推し進めることで合意。 信長も本願寺側との妥協点を探った。
3月7日: 本願寺は信長に『誓紙の筆本』を提出。 信長と本願寺は3度目の講話を果たす。
1570年~1580年。 10年間の、信長と西本願寺の『石山合戦』、に終止符が打たれる。
よそ者であり、『天下統一』『天下布武』、を実現する信長の道程は、簡単ではありません。
『本願寺野本拠地』…京都山科で細川氏の焼き討ち→大坂石山で信長に降伏→次はどこへ?→現京都に移る。
この続きの、信長と本願寺の検証は次回に。 お楽しみに。
ここで・・・
今回の二つの本願寺訪問での 驚きの発見と報告です。
静かな厳粛な 『東本願寺』 静けさこそが日本の寺の良さと感動でした。

『参拝接待所』
沢山の一般人が、静かに座っていました。
『剃刀の儀』(かみそり儀)を待っている方々です。
『剃刀の儀』。
『帰敬式』(ききょう式)が正式名。
仏・法・僧の三宝に帰依し、
南無阿弥陀仏の教えを拠りどころとして人生を歩むと、『新たに誓う』、真宗門徒の『出発式』。 だそうです。
『その時』を静かに待つ人たち。
敬意を称して、皆様に敬礼して
 、静かに立ち去った私です。
、静かに立ち去った私です。静かな東本願寺から歩いて・・・
次に到着。
にぎやか。大勢の人人。キラキラ。派手。東本願寺と対照的。 『西本願寺』

今日は親鸞の誕生日。大イベント中でした。 『宗祖・親鸞聖人:降誕会』
寺の外。沢山ののぼりがたなびきます。
寺の内。
沢山の僧侶と一般人。 『親鸞聖人降誕祝賀会』

沢山の雅師による奉納。 『雅歌』 沢山の僧侶 と 信徒 と 参拝者。


式典は厳かに施行されていました。
その隣は
『龍虎殿』。
休憩所でした。
こちらでも・・・東本願寺同様に、『剃刀の儀』 の方々が御待ちでした。
若いお坊さんがアナウンス。「剃刀の儀にご参加の方はお名前をお呼びします。 申込書をお出し下さい。」 と。
名前を呼ばれる方の多いのには、私は心底驚きました。
驚いた私。
お名前を呼ぶお坊さんの所へ行って、尋ねました。
「沢山の方が帰依なさるのはすばらしいことですね。 立派ですね。
皆様は、1年間とか2年間とか仏教をお勉強なさって、今日の日をお迎えになったのですか?」 と。
お坊さんの答。
「いいえ。 あなた様もいかがですか? 剃刀の儀に今からでも参加できますよ。
キリスト教をご存知でしょうか? キリスト教の洗礼の時には『クリスチャンネーム』を頂きます。
キリスト教同様に、剃刀の儀を終えた人は、『法名』を頂きます。
剃刀の儀とは、仏教徒になるという『宣誓式』です。
勉強はそれからです。 今日から私も釈迦様の弟子になるとの表明の儀です。」 と。優しく教えてくれました。
えぇ~!!
今日! 希望者は、何の知識もなくとも、仏教徒になる儀式に参加できるのです!!
坊さまの説明は、キリスト教からの説明でした。 えぇ~!!
更に驚いた私。 調べてみました。
『剃刀の儀』
西本願寺でも東本願寺でも、毎日原則年中無休で朝昼の2回、執り行われています。
『お礼金』は『一人1万円』。
『法名』と『略肩衣』(仏と対面時に威儀を正す、門徒の正装)を頂きます。
『戒名』と『法名』の違い。
「戒名」とは、戒律を守って生活する人、つまり 受戒を受けた人に与えられる名前。
「法名」とは、仏法に帰依した人に与えられる名前で、戒律のない浄土真宗では「戒名」とはいわず、「法名」を用います。
長くなりましたので…今日はここまでで。 御粗末様でございました

5月21日。復活節第五水曜日。
『今日の御言葉』
『イエスは弟子たちに言われた。
「わたしはぶどうの木。あなた方はその枝である。
人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。」』
ヨハネ福音書 15章5節
『ぶどうの実』は 『愛の実』ですよね。
人はいろいろの行動をします。 でもそこに『愛』がなければ、『ぶどうの実』ではない。てことですよね。
イエスの生活は、すべてが、『愛』ある生活でした。
私たちも、神から力を頂いて、イエスの生活に倣って、『ぶどうの実』を結びましょう!
きっと・・・
仏教徒も皆様も、御釈迦さんに倣って、『ぶどうの実』を結んでいらっしゃるのでしょうね!
皆様!
御訪問に感謝申し上げます。 お元気ですか?
織田信長真意検証の旅からも学ぶことがいっぱいです。 人は一生学び。 そして 一生青春ですね!

















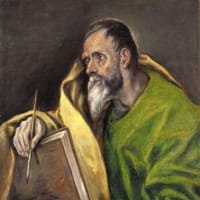

西本願寺の境内には国宝がいくつかありますが、
機会あれば『飛雲閣』を観られることをお勧めします。
金閣や銀閣は京都の観光スポットとして誰でも知って
ますが、意外と飛雲閣は国宝にもかからわず知られて
ません。(個人的には京都三閣のうち飛雲閣一番ええと)
公開すれば観光客が京都駅からも徒歩で行け、
ドッと増えるのを避ける措置もあるかも。問い合わせを
されれば観られますよ~(ダダやと思います)
確かに法名懇志は1万円なんですが、ランダムですから
どんな法名になるかは分かりまへん。ちなみに『内願』と
言って所属寺の承認さえあれば、こちらの申請した字の
法名を授かる事が出来ます。それはちなみに2万円
他の宗派寺院の一部にはボッタクリの所もあるけど、それに比べりゃリーズナブルでっしゃろ??
西ですか! お西さんは、水曜日は親鸞様の誕生日でしたので(知らずに行きました)、日本の北から南からと津々浦々から、沢山お観光バスでお出でで、沢山の人でした。大勢の方とご一緒も又日頃とは違っていて楽しかったです。
京都は良いですね。年に5回程訪れます。大好きです。
やはり飛雲閣を観るべきでしたかね!! いつもは非公開が多いようですが、親鸞さんの誕生日もあってか水曜日は公開していました。 入館をと思ったのですが・・・長蛇の列と最低5000円の寄付金(なんと呼んでいたかしら?覚えていません)でしたので、大枚を払うならもう少しゆっくりと観れる時にと、今回は諦めました。次回の国宝拝観のチャンスを楽しみにします。
法名はその方の永遠の名前になるのですか? とすれば、自分で決めた法名が良いですよね。2万円は確かにリーズナブルかもしれませんね。
ちなみに、カトリックの洗礼の際のクリスチャンネーム(霊名)は、永遠に消えることのない自分の名前となり、自己申告です。