いまだかつてない最大級のエルニーニョのために考えられない暖冬が続いています。そのため善光寺平でも冬型にならないため晴天の日がほとんどありません。冬型になると善光寺平北部の山間部は雪ですが、盆地は晴れることが多いのです。そんな週末は久しぶりの晴天に恵まれました。撮影に行かない理由はありません。まずは妻女山展望台へ。

展望台から北アルプスの絶景パノラマ。2枚の望遠カットをフォトショップで繋げました。左から爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、ちょこんと見える不帰ノ嶮、天狗ノ頭を経て白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳。北には戸隠連峰と飯縄山。東へ目を向けていくと高社山から志賀高原、笠ヶ岳、横手山、東には根子岳と四阿山。善光寺平でもこれだけの山並みを一同に見られる場所は、この妻女山展望台しかないのです。ここは川中島八景のひとつ。妻女山秋月に挙げられています。あと七つは、茶臼山暮雪、猫ケ瀬落雁、千曲川帰帆、八幡原夕照、勘助塚夜雨、典厩寺晩鐘、海津城晴嵐。またここは、信州サンセットポイント百選に選ばれており、美しい夕焼けが見られます。

展望台から南へ辿り、駐車場を抜けて右の林道を登ること10分。斎場山(旧妻女山)へ(左)。ご覧のように円墳(斎場山古墳)で、二段の墳丘裾があります、山頂は円形で平ら(中)。冬枯れで落葉したため、北方の川中島の景色がよく見えます。樹間から望遠で飯綱山を撮影(右)。

長坂峠へ戻って堂平大塚古墳へ。爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳の仁科三山。中央の鹿島槍右側の影は、日本で5番目、長野県で初の氷河かという、平家の落人が隠れ住んだというかくね里の大きな谷。青く蛇行する千曲川には、お馴染みの鴨の姿がまだ見られません。暖冬のせいでしょうか。

堂平大塚古墳(左)。斎場山とここには、毎年のことですが、この辺りの標識を作った倉科のMさんが注連縄を飾ってくれています。狂い咲きしたヤマツツジの残花(中)。同様に咲いた2013年の冬。明けて14年2月にはあの記録的な上雪の豪雪。戻って陣馬平へ。信濃柿がそのまま干し柿になっています(右)。本来は渋柿ですが、こうなると甘くて美味。鳥やタヌキなどの冬の貴重な餌になります。

陣馬平の北東の角にある菱形基線測点(左)。後方は松代城跡のある東方向。NO.16 基本 菱形基線測点のプレート(中)。長坂峠に戻って斎場山(右)。陣馬平でオフロードバイクで来た二人組と遭遇。ひとりは堂平大塚古墳の持ち主の故Kさんと旧知でした。本の紹介をすると、歴史好きだそうで早速買い求めてくださるそうです。

妻女山松代招魂社に戻りました(左)。左後方に茶臼山と白馬三山が。再び展望台へ。北東には中野の高社山(中)。拙書でも紹介していますが、登りがいのある面白い山です。右へ首をふると堀切山の向こうに根子岳と四阿山(右)。年末というのに驚くほど雪が少ない。菅平でスキーコーチをしている友人も、年内は仕事がないとぼやいています。この両山も詳しく紹介しています。

妻女山展望台へ(左)。ここの案内看板の英語が間違っています。訪れたら探してください。ヒントは鞭声粛粛。麓の薬師山トンネルの脇にある会津比売神社へ(中)。古代科野国の産土神。古くは山上にあったが上杉謙信が庇護していたため武田の兵火に遭い、その後現在の山陰にひっそりと再建されたとあります。境内から見下ろす参道(右)。左に謙信鞍掛の松と槍先の泉。これは後世の作り話。昭和30年代の祭りでは、この参道の両側に出店が並び、子供達の歓声が聞こえたものです。

所用で千曲市に行った帰りに、雨宮の唐崎城跡に登ってみました。雨宮のご神事が行われる斎場橋たもとの招魂社から登ります(左)。お宮の左手の小径を登ると登山道。約15分ほどで唐崎城跡(中)。そこから尾根を辿って高圧線鉄塔の見晴らし台まで行ってみました(右)。
唐崎城は、現地の看板によると、「この城は朝日城、唐崎城、藤崎城とも呼ばれる。唐崎山頂にあり、雨宮、土口、生萱にまたがる。この城は生仁館の本城で、雨宮摂津守、または生身大和守の居城であったとも云われ、一説には宇藤摂津守安時がここに居たとも云うことで麓を宇藤坂(現在は謡坂)ともいう。(中略)この地の土豪、雨宮氏の築いしところと伝えられている。時代は南北朝末応永時代約600年前と推定される。」ということです。だいたい埴科郡誌の記述と同じですね。ここから天城山(てしろやま)を経て鞍骨城跡へ至るコースは、拙書でも詳しく紹介しています。

高圧線の向こうに北アルプス。午後になってコントラストが弱くなりました。長野自動車道が龍の様に曲線を描いています。中央が更埴ジャンクション。この辺りは千曲川の自然堤防上で龍王といい、その昔、土豪の居館、または城跡があった場所ということです。古代科野国があった場所でもあります。手前の川は、コンクリートで固められてしまった味気ない沢山川(生仁川)。私が高校生の頃は、タンポポや野草が咲き乱れ鮒が泳ぐ綺麗な小川で、毎日自転車でこの土手を通いました。右下の橋は宇佐美橋といって、川中島合戦の際に宇佐美氏が作ったという伝説があります。転化してうさぎ橋(笑)。できればビオトープの手法で、単なる用水路から、子供たちも遊べる自然豊かな小川に戻して欲しいものです。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。陣馬平への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
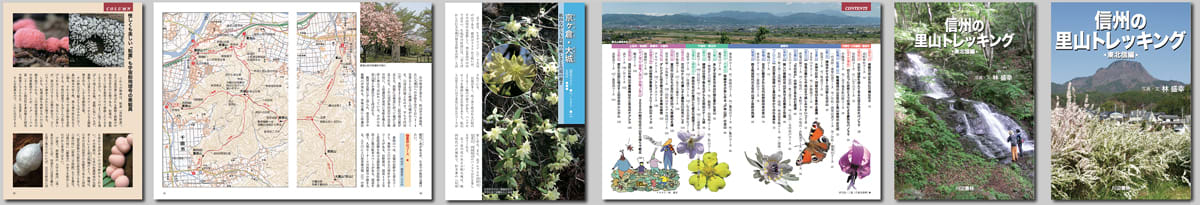
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。







展望台から北アルプスの絶景パノラマ。2枚の望遠カットをフォトショップで繋げました。左から爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、ちょこんと見える不帰ノ嶮、天狗ノ頭を経て白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳。北には戸隠連峰と飯縄山。東へ目を向けていくと高社山から志賀高原、笠ヶ岳、横手山、東には根子岳と四阿山。善光寺平でもこれだけの山並みを一同に見られる場所は、この妻女山展望台しかないのです。ここは川中島八景のひとつ。妻女山秋月に挙げられています。あと七つは、茶臼山暮雪、猫ケ瀬落雁、千曲川帰帆、八幡原夕照、勘助塚夜雨、典厩寺晩鐘、海津城晴嵐。またここは、信州サンセットポイント百選に選ばれており、美しい夕焼けが見られます。

展望台から南へ辿り、駐車場を抜けて右の林道を登ること10分。斎場山(旧妻女山)へ(左)。ご覧のように円墳(斎場山古墳)で、二段の墳丘裾があります、山頂は円形で平ら(中)。冬枯れで落葉したため、北方の川中島の景色がよく見えます。樹間から望遠で飯綱山を撮影(右)。

長坂峠へ戻って堂平大塚古墳へ。爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳の仁科三山。中央の鹿島槍右側の影は、日本で5番目、長野県で初の氷河かという、平家の落人が隠れ住んだというかくね里の大きな谷。青く蛇行する千曲川には、お馴染みの鴨の姿がまだ見られません。暖冬のせいでしょうか。

堂平大塚古墳(左)。斎場山とここには、毎年のことですが、この辺りの標識を作った倉科のMさんが注連縄を飾ってくれています。狂い咲きしたヤマツツジの残花(中)。同様に咲いた2013年の冬。明けて14年2月にはあの記録的な上雪の豪雪。戻って陣馬平へ。信濃柿がそのまま干し柿になっています(右)。本来は渋柿ですが、こうなると甘くて美味。鳥やタヌキなどの冬の貴重な餌になります。

陣馬平の北東の角にある菱形基線測点(左)。後方は松代城跡のある東方向。NO.16 基本 菱形基線測点のプレート(中)。長坂峠に戻って斎場山(右)。陣馬平でオフロードバイクで来た二人組と遭遇。ひとりは堂平大塚古墳の持ち主の故Kさんと旧知でした。本の紹介をすると、歴史好きだそうで早速買い求めてくださるそうです。

妻女山松代招魂社に戻りました(左)。左後方に茶臼山と白馬三山が。再び展望台へ。北東には中野の高社山(中)。拙書でも紹介していますが、登りがいのある面白い山です。右へ首をふると堀切山の向こうに根子岳と四阿山(右)。年末というのに驚くほど雪が少ない。菅平でスキーコーチをしている友人も、年内は仕事がないとぼやいています。この両山も詳しく紹介しています。

妻女山展望台へ(左)。ここの案内看板の英語が間違っています。訪れたら探してください。ヒントは鞭声粛粛。麓の薬師山トンネルの脇にある会津比売神社へ(中)。古代科野国の産土神。古くは山上にあったが上杉謙信が庇護していたため武田の兵火に遭い、その後現在の山陰にひっそりと再建されたとあります。境内から見下ろす参道(右)。左に謙信鞍掛の松と槍先の泉。これは後世の作り話。昭和30年代の祭りでは、この参道の両側に出店が並び、子供達の歓声が聞こえたものです。

所用で千曲市に行った帰りに、雨宮の唐崎城跡に登ってみました。雨宮のご神事が行われる斎場橋たもとの招魂社から登ります(左)。お宮の左手の小径を登ると登山道。約15分ほどで唐崎城跡(中)。そこから尾根を辿って高圧線鉄塔の見晴らし台まで行ってみました(右)。
唐崎城は、現地の看板によると、「この城は朝日城、唐崎城、藤崎城とも呼ばれる。唐崎山頂にあり、雨宮、土口、生萱にまたがる。この城は生仁館の本城で、雨宮摂津守、または生身大和守の居城であったとも云われ、一説には宇藤摂津守安時がここに居たとも云うことで麓を宇藤坂(現在は謡坂)ともいう。(中略)この地の土豪、雨宮氏の築いしところと伝えられている。時代は南北朝末応永時代約600年前と推定される。」ということです。だいたい埴科郡誌の記述と同じですね。ここから天城山(てしろやま)を経て鞍骨城跡へ至るコースは、拙書でも詳しく紹介しています。

高圧線の向こうに北アルプス。午後になってコントラストが弱くなりました。長野自動車道が龍の様に曲線を描いています。中央が更埴ジャンクション。この辺りは千曲川の自然堤防上で龍王といい、その昔、土豪の居館、または城跡があった場所ということです。古代科野国があった場所でもあります。手前の川は、コンクリートで固められてしまった味気ない沢山川(生仁川)。私が高校生の頃は、タンポポや野草が咲き乱れ鮒が泳ぐ綺麗な小川で、毎日自転車でこの土手を通いました。右下の橋は宇佐美橋といって、川中島合戦の際に宇佐美氏が作ったという伝説があります。転化してうさぎ橋(笑)。できればビオトープの手法で、単なる用水路から、子供たちも遊べる自然豊かな小川に戻して欲しいものです。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。陣馬平への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
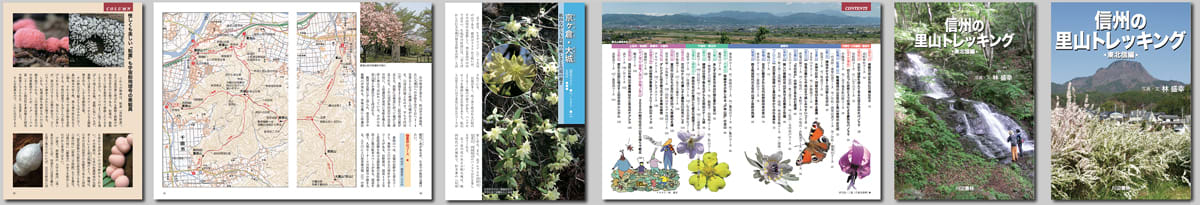
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
















