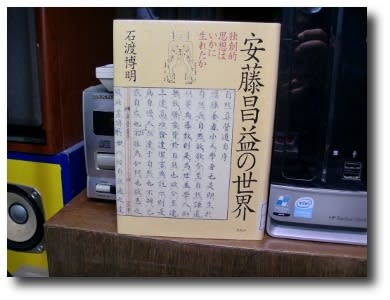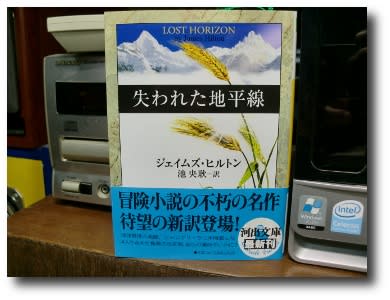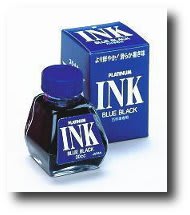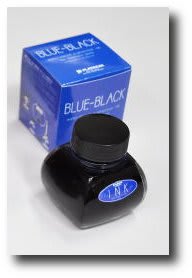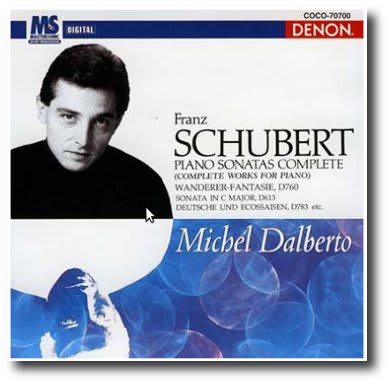まだ若い頃、たぶん学生時代に、岩波新書の目録の中に、ハーバート・ノーマンの『忘れられた思想家~安藤昌益のこと』という二巻本があることから、青森県八戸市に住んでいたという江戸時代の思想家・安藤昌益に興味を持ったことがありました。残念ながら、ノーマンの岩波新書は入手できず、岩波文庫の安藤昌益著『統道真伝』二巻をパラパラと読み、なかば驚き、なかば呆れたものです。
驚いたというのは、古代の聖人たちへの批判、とくに釈迦への批判の痛烈さでした。妻子を捨てて自分の修行に没入し、独身主義で女性を修行の妨げとし、両親の性愛の結果として生まれてくる自然の営みを罪悪視する教えは虚妄で有害だと喝破する痛烈さにびっくりしました。ましてや、お布施や喜捨を称揚し成仏を約束する僧侶たちの、社会への寄生性を合理化する仏教の教説を糾弾する論調の激越さに、正直言っていささかビビりました(^o^)/
また、独特の用語法や、屁理屈にしか思えない様々な議論の内容などは、若い青年(私)の理解を超えており、「当時としては画期的かもしれないが現代には縁の薄い古典」として、書棚に納めるだけに終わっていました。
ただし、安藤昌益という人物がどういう人なのか、なんでまた八戸にそんな思想家がポコッと存在したのか、という興味は底流としてあったようです。たまたま図書館で、2007年に草思社から刊行された単行本、石渡博明著『安藤昌益の世界~独創的思想はいかに生まれたか』を見つけた時に、謎の人物に対する興味を覚え、読んでみようと手に取った次第です。
本書の構成は、次のようになっています。
第1章 安藤昌益の生涯
誕生の地・大館/修行の場・京都/展開の場・八戸/終焉の地・大館
第2章 安藤昌益、復活の歴史
狩野亨吉による紹介/奥州街道の初宿・千住/書物の運命/戦前・戦中の研究/戦後の資料発掘/「安藤昌益全集」の刊行/海外での研究
第3章 安藤昌益と自然真営道
万有存在の法則を求めて/安藤昌益の基本用語/易批判と互性の論理/思考の深化/自然をどう見るか/直立・直耕する人間
第4章 安藤昌益の医学と医論
医学界への批判/伝統的医学論への批判/真営道医学の世界
第5章 安藤昌益の社会思想
社会の基本とは/「自然の世」と「法の世」/版図拡大をどう考えるか/安藤昌益の世直し論
それによれば、安藤昌益は今の秋田県大館市二位田の豪農の次男として生まれたらしいです。京都に出て禅林で仏教修行に励み、やがて無我の境地に至り、悟りを得るという体験を得て師から印可を受けるのですが、やがて自らの解脱体験を一種の錯覚であるとして否定するようになります。著者はその理由を、青年期の性の問題を越えられず、むしろ男性だけの仏門の倒錯性や仏教の教えにある虚妄性が、仏門からの離脱を促したのでは、と見ているようです。
仏門を去った安藤昌益は、新たな方向性を医学の道に求め、当時の名医・味岡三伯に師事します。医学の豊富な経験を積んだ昌益は、壮年期にさしかかった頃に、奥州南部・八戸藩の城下に移住します。ここでも、町医者でありながらその医術の実績と人柄から尊敬を集めるようになり、かなりの弟子たちが集まるようになります。その後、大館の実家の兄が逝去したので故郷に戻り、実家には養子を取らせて後継とし、八戸には同じく良医だったらしい息子を残し、自分は大館に住んで医者を続け、そこで没しているようです。
では、彼の過激なまでの思想は、どのように形成され、発表され、後世に遺されたのか。実は、弟子たちは師の医術の根本にある思想の危険性を充分に自覚していたようです。だからこそ、おそらく京都にある妻の実家の版元から問題部分を削除して出版した『自然真営道』三巻本以外の大著の原稿を、それぞれ書き写し、手許に秘蔵して後世に伝えたのでしょう。著者のこの推測は、説得力があります。
そして、安藤昌益の過激な思想の形成には、実は当時の医療の現状に対する批判があった、とする著者の見解もまた、説得力があります。当時、吉益東洞に代表される古方派医学の台頭により、攻撃的な薬物療法が専らとなり、薬剤による副作用には目をつぶり、結果責任に対しても「生死は医のあずからざるところ」などと言ってはばからないような、医療の荒廃があったようで、安藤昌益はこれを痛烈に批判していたようなのです。そして、伝統的医学の体系の中に、こうした医療の荒廃を生み出す素地があるとして、封建的な壮年男子中心の医学体系(*1)を、生命の本源である婦人科を冒頭に置き、小児科、壮年科、老人科という順序に病を考察し治療を施すべきだというように、人の成長に沿って作り変えようとした、と指摘しています。また、精神疾患・精神障害も病という観点から細分化された多くの症例をあげ、薬物療法と対話療法で臨む、とした点を評価(p.201~3)しています。
本書「まえがき」にある、
安藤昌益は、一言でいえば、食と性愛を基軸にして宇宙の全存在を一大生命とと見なし、そこから平和で平等な社会を希求した江戸時代中期の「いのちの思想家」である。
という要約が、なるほどと納得できました。農山漁村文化協会版『安藤昌益全集』を執筆・編集した著者ならではの好著であると感じるとともに、学生時代からの「謎の人物」の姿が、かなり解明されたように思い、嬉しく感じました。
(*1):「本道」と呼ばれた当時の内科医学では、医学の対象は皇帝や家長としての成人男性であり、大部分がこの内容で、婦人科や小児科は「巻末に申し訳程度に置かれる構成になっていた」(p.193)とのことです。