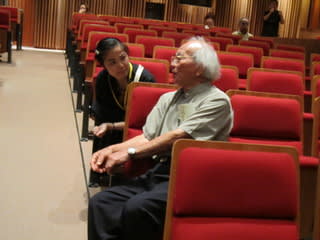
ゲネと本番の公演をとても楽しんだ。具志幸広さんがタクトを振る姿も見ながら、舞台も見た。歌舞劇の面白さが繰り広げられた。物語の筋は単純である。すでに『嵐花』などの朝薫の自伝や琉球の歴史を土台にした沖縄芝居を私たちは見ている。18世紀初頭の琉球の文化の高揚感のある時期に、玉城朝薫と平敷屋朝敏という希有な天才芸術家が存在した。彼らの人生と作品の物語を大城立裕は小説に書き、さらに芝居にし、さらに詩劇にした。しかし玉城朝薫は何度か大城作品に登場するが、朝敏についての新作組踊はついに書かれなかった。なぜだろう?「手水の縁」を超える恋愛は書かれないのだろうか?「苔の下」にしても断食して自害した遊女よしやの後を追うように按司もまた死出の旅に出ることが暗示されている。朝敏の生み出した恋愛の陶酔感を超えるものを大城立裕は書けなかったのだろうか?朝敏は男女の恋愛の至福、魂(融合の美)を描いている。
「愛」をテーマとする新作組踊の中身をこれから検証していくが、例えばこの「首里城物語」について言うならば、物語は決して複雑ではない。朝薫が尚敬王から踊奉行に任命され、彼は下男二人を引き連れてヤンバル行脚をする。村々の芸能を見聞し創作に取り組む。王府の内原の神女たちのウスデークもある。そして朝薫が江戸上りや薩摩で見聞し、習得したお能の技芸もあった。それらを統合しながら新しい踊「組踊」の形式を生み出していく、その朝薫の創作に至る経緯を、神女思戸金と村娘ジラーの恋人ナビーとの愛のトライアングルに悲しみと歓びを織り込んで結末へと導いていく。
首里に招かれたジラーと神女思戸金の許されぬ身分違いの恋、それを目撃しながら創作へと登りつめる朝薫。下男の狂言回しが実にいい。仁王(呉屋かなめ)とカミジャー(小嶺和佳子)の女のマルムンの役柄が生きている。彼ら二人が物語の本筋に絡んでいく。それをパロディー化し、庶民の感性をまた代表する。二人のやり取りの中に許田の手水の縁の伝承がパロディー化される。かろうじて朝敏の匂いが浮き上がる。しかし、ヤンバル出身の美しい若者ジラーと神女の恋の行方がどうも「執心鐘入」の女の愛の執心(欲情)の土壌になったという筋書きである。
二人の女たちの執心の闇に引きずられるジラーの姿があり、その関係の闇を解くために作者はジラーを引き離すか、殺さざるを得なかった。枷から自由になる天地を目指して遁走せんとするジラーと思戸金を引き離す朝薫がいる。ジラーは清に向かう船に乗り、清の芸能を学んでこいと朝薫、そして愛を引き裂かれた女が踊るのが、古典女踊「諸屯」になる。
「枕並べたる 夢のつれなさよ 別て面影ぬ 立たばーー、慣れし匂い袖に 移ちあもの」
つじつまはあう。恋する男に会えない、引き裂かれた女の情感が思いを内に押し込んだ踊りになる。抑制された動きの中に一図に思いを内へ内へと押し込む女の情念の炎が、その抑制された身体の動きの中で燃え上がる。天女の舞を思戸金に見る朝薫。
そしてひたすらジラーを待ち焦がれるナビーと、船が難破しジラーを失い朝薫を恨み自らの罪に震える神女を見据える男朝薫、そこに【執心鐘入】が誕生するという物語の流れになる。
朝薫「人の悲しみと喜びの間や暁の闇と明け雲のこころ 潮の満ち引きの 代わりごころーーーー、国の悲しみと人の悲しみと 国の喜びと いちゃしがな一道 誠びけい」
朝薫は3人の男女の愛の成り行きを目撃し、引き裂き、その悲しみ・喜びを国の悲しみ・喜びに重ね、創作の糧としたという物語の結末は華美壮麗な四つ竹踊りに執心鐘入を同時に演じさせるという舞台のフィナーレになる。めでたしめでたし。
作家の超越した姿勢が朝薫と大城立裕に重なって見えなくもなかった。人の悲しみと喜び、国の悲しみと喜びを描きだす作者の位置があり、その観察者の前でたゆたう人間の情念があり創作に高められる。それはそれで納得はできる。天女の舞いのような思戸金が踊る古典女踊りがある。それを実際に踊った男の古典女踊りとして舞台で見せても良かった。思戸金の踊りから男の女踊りを見せてもいいのでは?女の情念を男たちが躍ったのである。男たちが躍った女の情念の炎がどう身体化されたのか、それが見たかった。最も実際朝薫が古典女踊を創作したかどうかは曖昧なままだ。また「野遊びの場面」が集団演技もなかなかによろしく演じられたが、当時三線がヤンバルで演奏されたのか、その辺はまだ曖昧である。いつ頃三線はヤンバルの野遊びに取り入れられたのか、もっと吟味してみたい。ウシデークやシヌグなど女たちの手拍子や小さな太鼓は当時の雰囲気を今に伝えているが、1719年の時点で三線が村々に伝わったかどうか?よく分からない。(これから専門家に聴いてみるつもり)ひょっとしたら19世紀に入ってから?
おそらく御内原の神女たちの恋はあったであろうし、ウミナイビたちの恋もまたあったであろう。すべて親たちによって決められた婚姻が規範であったとしても、人を恋する思いはどの社会の規範の中にもあったとみていいのかもしれない。ただ1672年に辻村に遊里ができ、士族層がそこで疑似的な恋愛空間を楽しんだという史実(琉歌の数々は抒情歌が多い)、中には妾の女性をそこで囲ったという王府時代の習慣を思うに、辻や仲島の性の解放空間からおよそ40余年後に創作された朝薫の組踊の世界である。「ジュリの登場があってもおかしくはないね」と共に観劇した沖縄芝居女優は言った。
「嵐花」の芝居には朝敏と辻のジュリの恋愛が物語に組まれる。しかし、この【首里城物語】は辻のジュリを登場させていない。首里城の物語ゆえでもあろうか?御内原の神女を登場させた。神女の恋である!その恋に悲劇的結末をもたらしたのが朝薫であり、朝敏は恋を成就させた(手水の縁)。「道成寺」と比較される「執心鐘入」だが、女はパッションの塊になり鬼になりやがて救われるというのが昨今の解釈である。実際どうなのだろう?好きな男が死んでしまうこの物語においては女たちには悲しみが残されるだけで、その悲しみと共に生きることを余儀なくされる。生きることの悲しみと喜びが糸と糸の綾のように編まれる。生きることが耐えることでもある人生の無常(無情)が迫ってもくる。
その中で朝薫は国の宿命と人の情けを創作に織りあげたという物語!おそらく作家大城立裕もまた琉球・沖縄の歴史を具現化するかのように物語を編んできた作家であろうか!
演出の嘉数道彦は、今回歌舞劇の可憐な舞台を創出してきたかつての『乙姫劇団』現【うない】の若い団員を抜擢した。佐和田香織と花岡尚子である。二人が重要な役柄を演じている。まさに「うない」の味わいも感じさせる舞台だった。華麗なる舞台のイメージがあった。さらにその壮麗な舞の振付をしたのが佐辺良和であり、あらたな琉球音楽を意図した「交響曲」を作曲し全編を音楽構成の中に取り組んだ具志幸広がいた。丁寧に仕上げられた舞台である。それゆえに興趣が深くなった。さらに演出は細かい集団演技を見せた。動きに卒がなく、踊りを楽しみ、ソロの歌唱も聞かせてくれた。ゆえにTBSのデイフォルメされた琉球の踊よりはるかに良かったのである。音楽もまた、はるかに繊細な情感が楽譜に踊っていたのだ!沖縄のこの若者たちの舞台創作の感性の豊さ、完成度の高さは東京の舞台を超えている。沖縄ならではの沖縄の総合芸術の花が咲きほころぶ時が到来したのである。
******************************************************************
国立劇場おきなわ
2011年7月23日(土)午後6時半開演
24日(日)午後2時開演
歌舞劇「首里城物語」
作 大城立裕 演出・補綴 嘉数道彦
音楽 具志幸大 舞踊振付 佐辺良和
演出助手 川満香多
出演は、
玉城朝薫 宇座仁一
国王 東江裕吉
王妃 佐和田香織
思戸金 花岡尚子
ジラー 宮城茂雄
ナビー 古謝渚
仁王 呉屋かなめ
カミジャー 小嶺和佳子
ジラーの母 大湾三瑠
踊り手 阿嘉修 岸本隼人 国場涼太 仲宗根弘将
金城真次 玉城匠 友寄隆乃進 比嘉大志
松田香織 伊志嶺忍 平田瞳 金城麻美
新里春加 平安山裕子 伊良波さゆき 又吉まどか
地謡
歌三線・笛 新垣俊道 入嵩西諭 澤井毎里子
歌三線・胡弓 瀬良垣幸男 大濱麻未 米増健太
Ⅰ箏 日高貞子 知念真子
Ⅱ箏 池間北斗 外間環
十七弦 田中はるか 新垣初子
打楽器 與儀朋恵 横目大通
************************************************************************
<写真は「国立劇場おきなわ」芸術監督・幸喜良秀氏!氏が育てた若者たちが舞台創造(想像)をしっかり継承している!写真の削除はいつでもOKです。もし問題がありましたらコメント欄からご連絡ください!>



















