前回の記事でアマチュア研究者・アマチュア精神の果たす役割に関する対話を紹介しました。かくいう私も、もともとは熱帯林保全が専門なのですが、この間、新古典派経済学の「自由貿易神話」や河川工学者の「ダム神話」に対し、「アマチュア精神」で挑んできました。
2012年に出版した拙著『自由貿易神話解体新書 ―「関税」こそが雇用と食と環境を守る』(花伝社)では、「方法論的アマチュア主義」と題して以下のように書いています。紹介いたします。
***拙著『自由貿易神話解体新書』pp.26-27より引用****
方法論的アマチュア主義
本書の立場は、「方法論的アマチュア主義」である。専門家が業界のインサイダーと化したとき、業界益を守るため一般の人々を騙すような虚言を弄すようになる。アマチュア主義に立つということは、「インサイダーではない」という表明である。
自由貿易に関しては、日米の一般世論に見られるような懐疑的な考えに正当性がある。自由貿易を肯定する新古典派経済学のモデルの方が間違っているからである。
幅広い教養を持ち、科学的リテラシーを持っていれば、専門家の虚言を見破ることは可能である。既得権益のしがらみに属さず、幅広い教養があって、事の是非を判断できる教養人が社会には必要なのである。しかし、日本の大学では教養教育が軽視されるようになり、いわゆる「専門バカ」が増えてしまった。専門家のモラルも低下し、それをチェックできる教養人も減っているように思える。
自由貿易を批判する代表的な論客として活躍している中野剛志は、教養学部の卒業である。教養学部では、タコツボのような狭い専門分野に特化していないので、幅広い視点から大局的にモノゴトの是非を判断できる教養人が育ち得るのかも知れない。
私の場合、自らがインサイダーである自分の専門分野に関しては業界に配慮して判断が曇る可能性があるかも知れない。私はそうでないつもりである。しかし専門家は、業界内部のしがらみによって判断が歪む可能性があることを、絶えず肝に命じておいた方がよい。
経済学に関して、私は何のしがらみもない。経済学の専門家に対しては、私は非専門家であり、一般人である。経済学のムラ社会に所属していないので、初めから「ムラ八分」になる心配もない。専門家を名乗るインサイダーたちよりも、立場的には中立的であろう。
「専門分野の事は専門家に任せよ」という言説は明確に誤りである。専門家同士も相互にチェックし合い、インサイダーだけの閉鎖的ムラ社会の暴走を許さないような制度設計が必要であろう。経済学の場合、インサイダーの専門家に任せておくと世界中の人々を困窮に陥れるような甚大な被害を招く。利害関係のしがらみのないアウトサイダーたちが、インサイダーたちを積極的に監視すべきと思われる。
***引用おわり******
2012年に出版した拙著『自由貿易神話解体新書 ―「関税」こそが雇用と食と環境を守る』(花伝社)では、「方法論的アマチュア主義」と題して以下のように書いています。紹介いたします。
***拙著『自由貿易神話解体新書』pp.26-27より引用****
方法論的アマチュア主義
本書の立場は、「方法論的アマチュア主義」である。専門家が業界のインサイダーと化したとき、業界益を守るため一般の人々を騙すような虚言を弄すようになる。アマチュア主義に立つということは、「インサイダーではない」という表明である。
自由貿易に関しては、日米の一般世論に見られるような懐疑的な考えに正当性がある。自由貿易を肯定する新古典派経済学のモデルの方が間違っているからである。
幅広い教養を持ち、科学的リテラシーを持っていれば、専門家の虚言を見破ることは可能である。既得権益のしがらみに属さず、幅広い教養があって、事の是非を判断できる教養人が社会には必要なのである。しかし、日本の大学では教養教育が軽視されるようになり、いわゆる「専門バカ」が増えてしまった。専門家のモラルも低下し、それをチェックできる教養人も減っているように思える。
自由貿易を批判する代表的な論客として活躍している中野剛志は、教養学部の卒業である。教養学部では、タコツボのような狭い専門分野に特化していないので、幅広い視点から大局的にモノゴトの是非を判断できる教養人が育ち得るのかも知れない。
私の場合、自らがインサイダーである自分の専門分野に関しては業界に配慮して判断が曇る可能性があるかも知れない。私はそうでないつもりである。しかし専門家は、業界内部のしがらみによって判断が歪む可能性があることを、絶えず肝に命じておいた方がよい。
経済学に関して、私は何のしがらみもない。経済学の専門家に対しては、私は非専門家であり、一般人である。経済学のムラ社会に所属していないので、初めから「ムラ八分」になる心配もない。専門家を名乗るインサイダーたちよりも、立場的には中立的であろう。
「専門分野の事は専門家に任せよ」という言説は明確に誤りである。専門家同士も相互にチェックし合い、インサイダーだけの閉鎖的ムラ社会の暴走を許さないような制度設計が必要であろう。経済学の場合、インサイダーの専門家に任せておくと世界中の人々を困窮に陥れるような甚大な被害を招く。利害関係のしがらみのないアウトサイダーたちが、インサイダーたちを積極的に監視すべきと思われる。
***引用おわり******














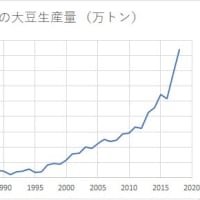

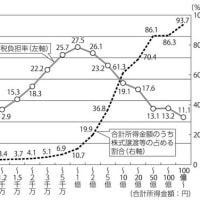



いちばん分かりやすい例は、福島第一原発が事故を起こす前までの原子力工学関係者です。政府の政策や電力会社の方針にすっかり巻き込まれていたと思います。もちろん、そういう中でも、きちんと異論を出していた研究者はいます。万年助手(助教)の小出裕章さんや今田哲二さん、元原発設計者の後藤政志さんや田中三彦さんのような方々です。
わたしが個人的に記憶しているのは、日本国際経済学会の第70回全国大会(2011年10月22日・23日、慶応大学三田キャンパス)の第一日目にあった大会シンポジウムです。TPP問題に火がついたばかりで、シンポジウムの主題もTPPでした。じつはわたしはこのシンポは最後の部分しか聞いていなのですが、農業経済が専門という研究者が国際経済の専門家はほとんどがTPPに賛成なのはなぜですかと、悲嘆に近い声をあげられていたことを思い出します。全体の流れは知りませんが、国際経済学の専門家はTPP推進で当然という人が圧倒的多数だったのでしょう。
この場合、原子工学やバルサルタンの臨床研究のように、研究資金が流れたというのではないでしょう。しかし、国際経済学のいちぶである(これまでの)貿易理論は、その成立のときから、自由貿易という政策が組になっていて、理論と政策の区分が不分明です。
お金で買収されていなくても、経済学のような学問では、どうしても自分の専門分野の政策を主張したくなることが多いと思います。貿易論は、こうした構図が、ある意味、明確な分野ですが、他の学問領域でもおなじようなことがあるでしょう。そういう意味で、「専門家はインサイダー」という留保はつねに必要です。
>農業経済が専門という研究者が国際経済の専門家はほとんどがTPPに賛成なのはなぜですかと、悲嘆に近い声をあげられていた
>研究資金が流れたというのではないでしょう
私の知り合いの国際経済学会の会員にはTPPに批判的な方もおります。しかし、表立ってそういうセッションを立ち上げたり、あからさまにそう主張するのは難しいような場の雰囲気があるのでしょうか。
場の雰囲気に馴染まないと仲間に入れないというか、国際経済学のインナーサークルの一員になるためには「自由貿易を支持しなければならない」というテーゼを受け入れないとならないという無言の圧力があるのではないでしょうか。
農業経済学会の方も、同様にインサイダーになるための掟やしきたり、不毛な学閥の支配と対立で満ちているようなので、お互いに救われないという感じもいたします。
私の専門の林学の場合、ムラ社会への無言・有言の同調圧力で満ち満ちています。
私が大学生のころには「拡大造林を支持しなければならない」とか「熱帯林破壊の原因は木材伐採という林業行為によるものではなく地元住民の焼畑である」とか、いずれも「林業ムラ」「林野ムラ」のあからなさまな利権から発生しているテーゼを受け入れなければならないという同調圧力で満ちていました。
私が選んだ専門分野がよほどおかしいのだと思って、学生のころは「とんでもない分野を専攻してしまった」と後悔しきりでした。しかし次第に他の分野も同じようなもんだということが分かってきました。
ムラ社会の同調圧力に屈しないためには、誰ともつるまない、一匹オオカミを貫くという対策をとるしかなく、それを実践してきました。しかしそういう態度をとっていると学会で発表しても聴衆が一ケタということになりました。
病根は深いと思います。どう解決したらよいのでしょうか。
アマチュア研究者が増え、各学問分野に存在するナンセンスな不文律を洗い出してくれることに期待します。利権のない教養ある方々が、各学会に存在するナンセンスな不文律を洗い出すような作業をしてくれればすばらしいと思います。一般の人々がその不文律を信じなくなればよいのですから。
この間、私が主に取り組んできたのは河川工学分野の不文律の追求でした。彼らがダムを造りたいのは、職業病とでも言うべきものです。彼らの場合、薬学研究と同様に、あからさまな研究資金の流れもあります。彼らがダムを支持するのは勝手です。
しかしながら許せないのは、ダムを造りたいがために、「森林が成長しても流域の保水機能の増進は確認できない」というウソを主張するまでに至ったことです。科学的事実を捻じ曲げ、虚偽を主張することだけは断じて許してはなりません。
これ以外にも、他にもウソだらけで、唖然とすることばかりです。彼らは方程式の左右の次元が合わないモデルも平然と使って、それを正しいと主張するのです・・・・。
いちど日本の学会すべて解体して最初からやり直した方がよいのではないかとすら思います。
これがある経済学の学派の成立要件だとすると、経済学のある学派の理論を学ぶうちに、知らず知らずのあいだに、その学派がもつビジョンと政策とを学び取ってしまっている可能性があります。
国際経済論の場合、国際マクロあるいは国際金融論が出てくるまでは、国際経済学といえば貿易理論でした。この貿易理論には、リカード理論、ヘクシャー・オリーン・サミュエルソンの理論(HOS理論)の二つの大きな基礎理論がありますが、歴史的経緯から、どちらの理論も、政策としての自由貿易とセットになっていました。
その影響で、いまでもリカード貿易理論=自由貿易推進政策という公式が学校でも大学でも教えられています。しかし、理論と政策とがそのように直結することは本当はありません。結論を導く前提や、理論モデルの一部の仮定を置き換えれば、別の結論が導かれうるからです。
わたしが『リカード貿易問題の最終解決』で目指したのは、政策と切り離して、どういう状況のもとに貿易の利益が得られるのか、どういう状況では逆に不利益が生ずるのか、きちんと議論・分析する枠組みを作り上げることでした。
たとえば、完全雇用が成立するなら、貿易は貿易をしない場合より、ひとびと(この場合、労働者)に利益があるが、ただ自由化するだけで総需要が増えないと失業が生まれることが証明できます。こうしたことは、リカード貿易理論の枠組みの中できちんと言えることです。
貿易の利益・不利益も、誰にとっての利益・不利益なのかという分析も必要です。従来のリカード理論では、国を単位として議論してきた結果、この「だれに」の視点がしばしば抜けていました。この点も、あたらしい貿易理論では、産業あるいは企業単位で分析できるようになっています。たとえば、自由化の結果、ある産業は競争的でなくなる可能性があります。このとき、この産業の企業は廃業・倒産の危険にさらされます。資本家/経営者は、そのことにより損失をこうむる可能性があります。その産業で働く労働者は、失業の憂き目に会うかもしれません。
HOS理論は、その前提が一般均衡にありますから、一方で倒産や失業が生まれても、他方で投資機会と雇用が増えるので、要素価格や製品価格の変動といった問題以外に経済的不利益は生じないという「前提」になっています。
ここがリカード理論とHOS理論の大きな違いです。リカード理論は、うまく構成すれば、ケインズの構想と整合的なものになるとわたしは考えています。しかし、これはまだ『リカード貿易問題の最終解決』では示せていません。ごく簡単な構想が述べられただけです。そういう意味では、リカード理論はまだまだ発展させなければならないし、発展の可能性をもっていると信じています。
こういう状況はあるのですが、まだまだそういう新しい理解は浸透していません。これまで、貿易理論は、リカードを含めて貿易推進論者によって開発・発展されてきました。そのため、後の時代になって貿易理論を学ぶようになった人たちは、理論の根本をきちんと検討することなく、常識的に貿易自由化政策を主張するようになりました。日本の国際経済学会の状態も、こうした大きな状況の一部なのでしょう。
政策を固めには、そういう常識論として知っていることではなく、もっと深い分析と広い視野が必要です。
政策は総合的なものですから、経済学的な損得だけで結論をだすことはできません。たとえば、森林や水、景観あるいは文化や伝統といった、ふつうは経済学的想像力の視野にないことも考えなければなりません。
演劇はよく総合芸術といわれます。しかし、演劇を一人の専門家だけでやることはほとんど不可能です(さいきん、一人芝居というスタイルもあることはありますが)。
政策を考えるにも、おなじように人間生活のさまざまな場面(この中には自然環境も含まれます)を対象とする異なる専門学問のあいだの討論が必要でしょう。このような討論には、各専門家は、自分専門以外の学問についてはアマチュアとして興味と理解しようという意志を持たなければならないはずです。
やはりアマチュア精神が必要です。
経済学者が自由貿易による総需要の収縮効果について語らないので、フランスの人類学者のエマニュエル・トッドがしきりにそれを問題にしていました。
この点に関しても、こんどの塩沢先生の『リカード貿易問題の最終解決』が出版された意義はあまりにも大きいと思います。私も啓発につとめたいと存じます。
自由貿易は、生態系や文化や地域コミュニティの持続性といった非経済学的な観点から肯定できないのはもちろんなのですが、自由貿易による総需要収縮効果を認めるだけで経済学的にも認められなくなると思います。私の本でもそれはずいぶんと書きました。
最近はスティグリッツなども、自由貿易による失業と賃金低下のスパイラルの発生を言い始めています。
わたしが上でいったことは、「総需要が増えないと失業が生まれる」ということで、世界全体の総需要(世界最終消費)が一定でも、かならずある国に失業が生まれます。総需要が減るから失業が生まれるのではないのです。
もちろん、こうしたことが起これば、失業者が100%所得補填されないかぎり、総需要は減少するでしょう。産業再編で、今後成長が期待される産業には新規投資が増えるの可能性がありますが、撤退が必要となる産業では投資はとうぜん減少します。貿易自由化は、働き続ける人にとっては、実質賃金離の上昇を意味しますので、その効果による総需要の追加があるかもしれません。これらすべでが現実にどう出るかは、状況によると思われます。
ほっておいても高度成長期の日本のように総需要が自然に増大する状況では、これはそれほど問題視しなくてもよいかもしれませんが、需要飽和(消費飽和)の状況ではそれなりの対策とセットに考える必要があります。
需要飽和(消費飽和)ということ自体、いろいろなところで話題に上っていても、経済学的な理論化も分析もまだ少ないのが現状です。このあたりだけをみても、経済学のブレークスルは必要です。
関先生が言及されているスティグリッツについては、分析はさらに難しいと思われます。アメリカ合衆国では、単純労働者と高度職業者とのあいだの格差が近年の貿易深化=グローバル化で開いているのではないかという議論があります。しかし、これが本当に貿易のためなのか、国内の経済構造の変化なのかは意見の分かれることころです。
もしこういうことが起こるならば、貿易自由化から利益をうる産業あるいは階層から不利をうける階層に所得移転を行なうことも考えるべきかもしれません。もちろん、新自由主義の人たちがそう考えるとは思われませんが。
「総需要が増えない」以前に、総需要って、そもそも、不足しているのではないでしょうか?
下記のエントリに書いたように、店頭に商品があるということは、「売れ残り」があるということで、需要を供給能力が上回っているということです。少なくとも、ミクロ的にみると、ほぼ全ての市場が供給能力過剰(需要不足)ということになります。
http://d.hatena.ne.jp/suikyojin/20110216/p1
なお、供給能力過剰であるため、比較生産費説が成り立たないということを以下のエントリに書きました。
http://d.hatena.ne.jp/suikyojin/20140701/p1
わたしの7月2日のコメント「貿易自由化と総需要」は、理論内部の論理構造に関するコメントです。現実に総需要が不足しているかどうかとは、無関係です。より正確にいえば、独立です。
現実に総需要が不足して失業が存在してい場合に、そのまま貿易を自由化すれば、その総需要が増えないかぎり、失業は存在し続けます。失業者数は増えます。現実に総需要が足りていて、失業がない状態で貿易を自由化しても、世界全体で総需要が増えないかぎり、かならずどこかの国に失業が生まれます。
リカードの貿易に関する数値例は、しばしば「比較生産費説」とか「比較優位説」とか言われていますが、この名前はJ.S.ミル以降のものです。これは貿易特化のパタンに関する命題と貿易利益に関する命題との複合です。
(この両者はほんとうは区別する必要があります。)
水鏡仁さまは、後者の貿易の利益(gains from trade)について考えられているのでしょうが、「利益」ということになると、だれにとってという視点が必要です。これまで貿易する両国にとってと曖昧に考えられてきたことはたしかです。しかし、もっと詳しく分析することも可能です。
失業や廃業に追い込まれる人にとっては「不利益」(損失)ですが、そのような場合でも、就業し続けて従来どおりの賃金をもらいつつげる人にとっては、実質賃金の上昇という「利益」があります。このようなことは、すべてわたしの『リカード貿易問題の最終解決』には考えられています。
ただ、重要なことは、貿易の不利益があることが言えても、それでも貿易理論としてのリカード理論、あるいはより現代的な形でのリカード・スッファ貿易理論は成立します。これが理論と政策とをきちんと分けて考える必要のひとつです。
理論と政策とを直結することはできないということは、6月28日のコメント「理論と政策」にも書いています。
新しい記事で、エマニュエル・トッドの説についても加筆して紹介しておきました。スティグリッツも慎重な書き方で煮え切らないのですが、TPPなどの自由貿易協定と失業と低賃金化を関連づけて論じていますので、あわせて紹介しておきました。
「理論内部の論理構造」についてではなく、現実についてリカードの理論が適用できないと指摘したつもりでした。舌足らずでした。
リカードのモデルや均衡モデル等、経済学(特にミクロ経済学)のモデルは、現実の経済とかけはなれており、経済学のモデルの多くが、現実の経済には適用できない、という認識なので、リカードのモデルと現実の経済とは違うことを強調して、あのような記述にしてしまいました。
まあ、経済学のモデルと称するものが、あまりにも現実離れをした前提を置いた上で結論を出し、政策含意まで述べる論文が多いので、水鏡仁さんのようにやや「性急に」議論される気持ちも分からぬではないのですが、学問を育てる上でも、ただしい政策思想をもつうえでも、もうすこし丁寧な見方が必要ではないでしょうか。
たとえば、水鏡仁さんは、モデルと理論とを同一視されているかのような書き方をされていますが(そしてこれも多くの経済学者によく見受けられることなのですが)、理論とモデルとは違います。さらにいえば「リカードのモデル」といっても、いろいろな多様性があり、その背後にある考え方や理論も異なります。
ここでは、話しをリカードの貿易理論に限定しますが、リカード自身が考えた説明はきわめて簡単なもので、それは現在ふつうにリカード貿易理論と読んでいるものとおなじではありません。普通の教科書に書かれている「リカード・モデル」は、きわめて新古典派的に解釈され、定式化されたものです。しかし、それだけがリカードの貿易理論ではありません。つまりいくつもの「リカード貿易論」があります。
たとえば水鏡仁さんは、「比較生産費説の基本的な欠点とは、比較生産費説が供給不足を前提としているに対して、現実の経済ではほとんどの商品(サービスを含む)は需要不足となっているということです。」(酔狂人の異説2014.7.1)と書かれています。「現実の経済ではほとんどの商品が需要不足となっている」ということは正しいのですが、比較生産費説がすべて「供給不足を前提としている」というのは、ある種のリカード理論に当てはまりますが、すべてのリカード理論がそうだというわけではありません。
たとえば、わたしの『リカード貿易問題の最終解決』の第3章系21あるいは『経済学を再建する』第5章定理3.8を見てくだされば分かるように、需要不足が失業を必然とすることも扱われています。
いくつかの教科書を見て、それで経済学一般だと理解されるのは、すくなくとも経済学につては誤りです。経済学には、たくさんの学派があります。価格や価値と中核部分についてはいえば、古典派価値論と新古典派価値論の二つの大きな対立があります。この両者は、ほとんど対極にあるといってもよいものです。
現在の主流の経済学は新古典派です。ふつうミクロ経済学といわれているものがこれにあたります。これは需要供給の一致により価格が決まるという価格理論(価値論)をもっています。この考えを形式化し一般化したものが一般均衡理論です。こういう枠組みでは、需要と供給とはつねに一致するので、需要不足ばかりでなく、供給不足もありえません。
(厳密にいえば、供給>需要という場合がありますが、そのとき価格は0になるというのが均衡の定義です。価格が正で供給=需要か、価格が0で供給>需要という状況を超過需要が0といいます。)
これに対して、古典派価値論は、生産費価値論に立っています。この代表がリカードです。生産費価値論はフルコストの生産費が価格を決めるという考えです。ここでは、供給過剰も需要不足も起こりえます。
リカードというと労働価値説と反射のようにいう人もいますが、リカードの考えはだんだん変わってきており、整理すると(これ自身はJ.S.ミルのことばですが)生産費価値説というほうがよいのです。
ここでコメントをとめてもよいのですが、またまた誤解する人が出てくるでしょうから、リカードに関するケインズの理解について付言しておきます。
ご承知のように、ケインズは、失業の存在を理論的に定式化しようとした始めての人です。しかし、かれの主著とされる『雇用・利子および貨幣の一般理論』には、現在の眼から見て(すくなくとも私の眼からみて)、あまり適切でない批評や経済学の分類が色々混ざっています。その最大のものが、自分以前の経済学を古典派も新古典派も一括りにして「古典派」と呼んでいることです。このような乱暴な分類によって、ケインズは自分の首を自分で締めてしまったとわたしはおもっています。
ケインズよりはるか後になりますが、1970年代後半以降、ケインズ経済学に対するある種の反革命がおこります。それが現在の主流中の主流というべき、新しい古典派(New Classical School)です。ニューケインジアンと呼ばれているもうひとつのアメリカで優勢なグループは、いわば新しい古典派の変種です(そういうと、この派の人たちは怒るでしょうが)。
このような結果になった遠因は、ケインズにあります。1960年代後半から70年代前半に掛けて「マクロ経済学のミクロ的基礎付け」という運動が起こりました。そのとき、ミクロ的基礎付けの基礎に用いられたのが新古典派経済学だったからです。最初の試みとて新古典派経済学が試されるのは当然でしょうが、それでうまくいかなかったら、もうひとつの価値論を試してみるとい可能性をケインズの乱暴な分類は奪ってしまったと思います。
もうひとつのケインズのまちがいは、リカードその他の古典派経済学者を「セイ法則を認めるかどうか」を判定基準にして、セイとリカードをセイ法則派、マルサスや重商主義者をセイ法則否定派に分類して、リカードを非難し、マルサスを持ち上げたことです。セイとマルサスは、価値論でいえば、新古典派とおなじ需要供給理論にたっています。これに対して、リカードは、生産費価値説を唱えたのです。残念ながらこの伝統は、1870年代の限界革命により、ほとんど消滅し、新古典派の時代になりました。ケインズは、その経済学に反発したはずですが、自分の理論が古典派価値論を基礎にすればうまく展開できるという可能性に気づきませんでした。
結論的にいえば、
(1)経済学にはいろいな考え方(理論上の対立)があること、
(2)ひとつふたつの教科書をみて、それが経済学のすべてと思わないこと、
(3)多くの経済学の中には、水鏡仁さんなどの考えを理論的にバックアップしてくれるものもあるのですから、きちんとそういう理論を探す努力をすること、
これらの注意が必要と思われます。
こういう努力を続けないと、いくら現在のおかしな経済学を批判されても、良い経済学は育ってきません。