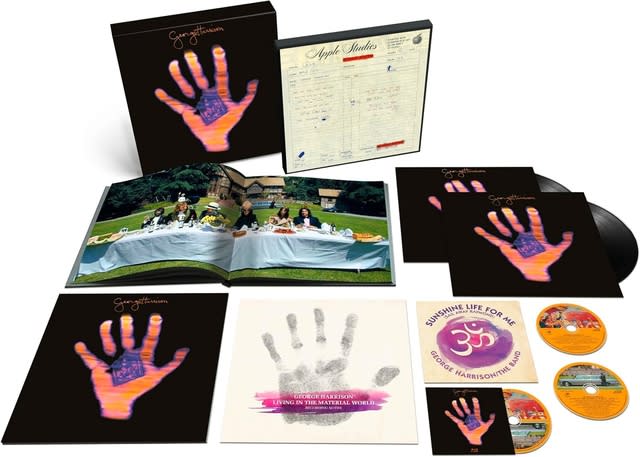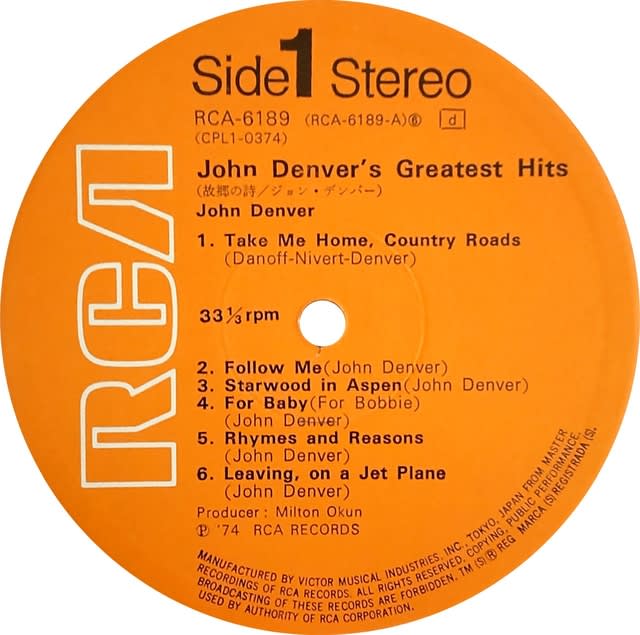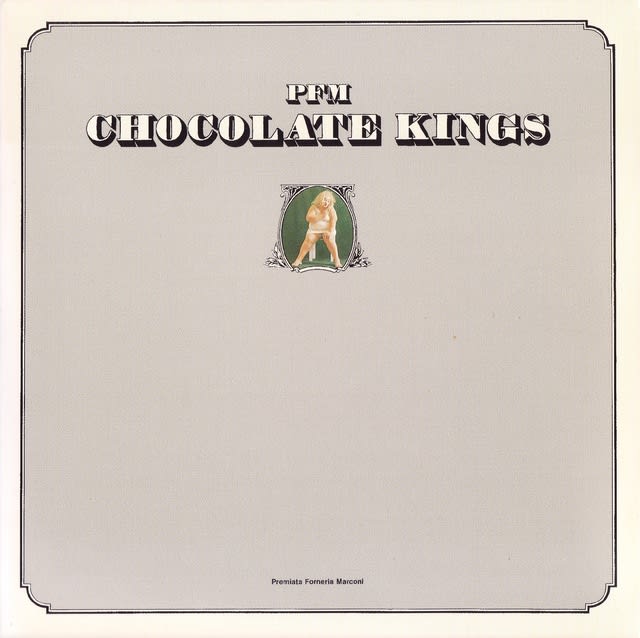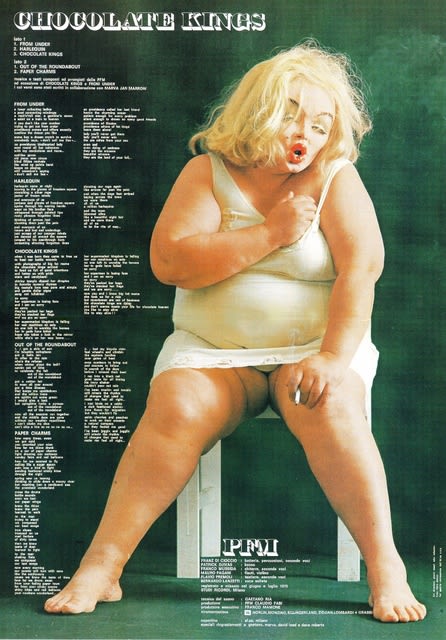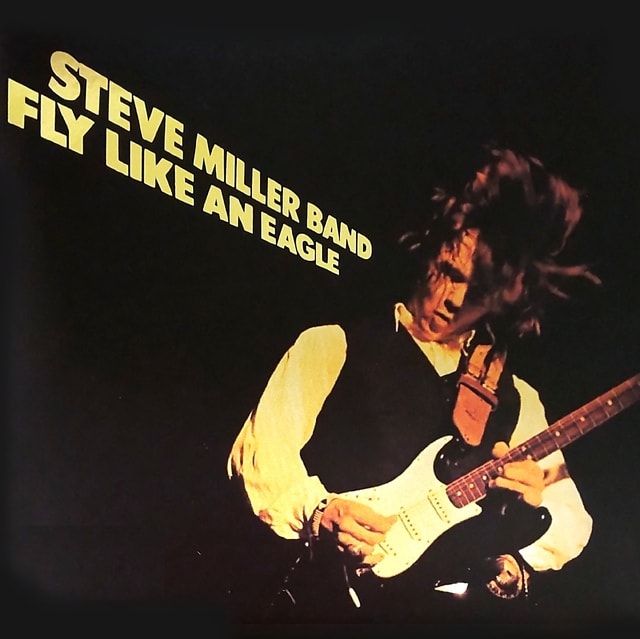70年代と言えばカントリー・ロック結構流行っていた気がするけれど、今じゃバーズやイーグルスなんかは懐メロ的存在で、ラスティー・ヤングやポール・コットンらが相次いで死去してしまったポコなんかもオイラのような年配のファンを除けば話題に上らないね。
80年代になって時代は変わり、アンクル・テュペロ、初期のウィルコ、カーボーイ・ジャンキーにジェイ・ホークスなどオルタナ・カントリー・ロック・バンドなんかが相次いで登場し話題を振りまいたんだけれど、そんな彼らもいつの間にか忘却の彼方。
これも時代の流れ、仕方がないのかな。
本日は1982年のポコのアルバム、Cowboys & Englishmenでも聴いて昔を思い出すことに。


アルバム・タイトル通り、メンバー構成がアメリカ人のラスティー、ポールとキーボード担当のキム・バラッドとイギリス出身のスティーブ・チャップマンとチャーリー・ハリソンからなる正統派カントリー・ロックが楽しめる。
当時ポコの売り出しに消極的だったMCAレーベルでの契約上の最終作で全10曲のうち7曲がカバーとポコとしては異例の作品ではある。
エバリー・ブラザーズ、ゴードン・ライトフット、ティム・ハーディンにJ.J. ケールらの渋めの曲をカバー。特にJ.Jの曲、Cajun Moonなんかはその後ライブで結構披露しているのでかなり彼らにとって思い入れのある作品かと感じる。
カバー曲が多いとは言え、しっかりコーラス・ワークやキレのいい演奏はいつも通りで決してMCAレーベル最終作のやっつけ仕事では無いと今更ながら思う。
まあ地味ではあるんけれど…