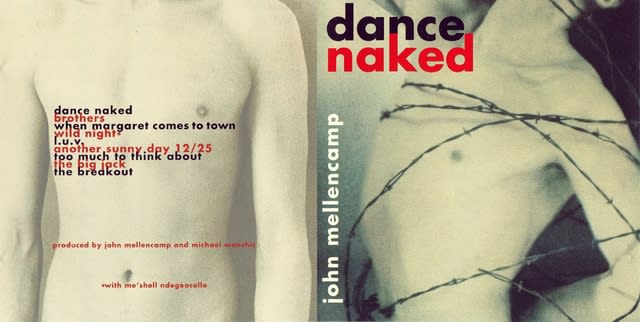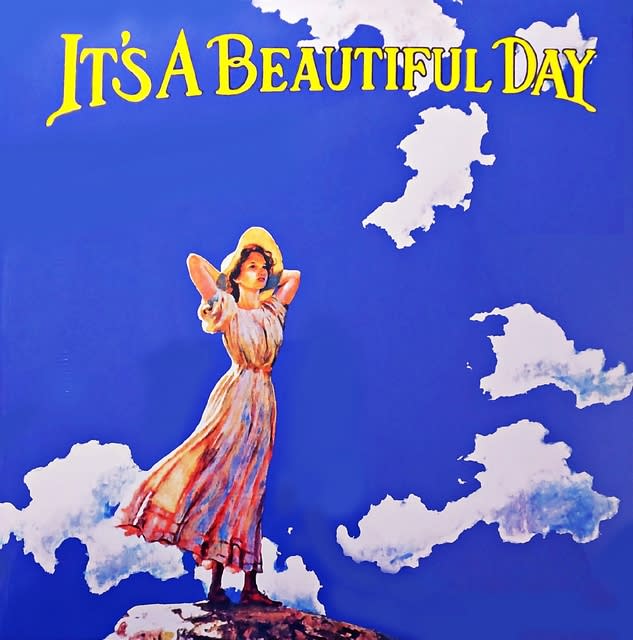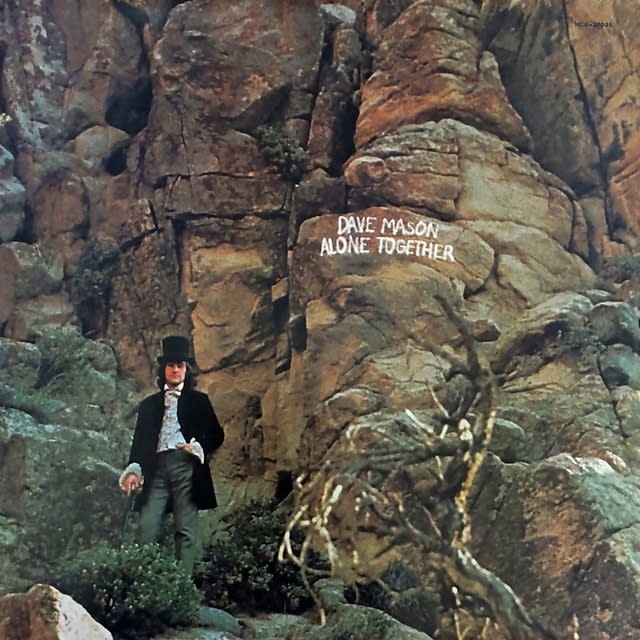先日、レコード・メーカーがピクチャー・レコードは黒の通常盤とその音質を比較するべきではないと自白していた事を語ったが、じゃカラー・レコードはどうよ?
これは以前にここでアップした通り、レコードの原料はポリ塩化ビニールが主剤となる合成樹脂で色は透明。塩ビの素材は柔らかいので通常材質の強度を増すために透明な樹脂にカーボンを加える事によって黒盤となる。一般的にカーボンの添加によって強度が増したレコード盤は、低域がタイトに聴こえるそうな。一方カラー・レコードは透明な塩ビ樹脂に適切な顔料を混ぜて合わせる事によって製造され、材質の強度の関係から黒盤と比べて音質がマイルドに聴こえるらしい。
つまり一概にカラー・レコードの音質が悪いというわけではなく、聴く人によって好みが別れるのでないかって意見を述べた。
じゃあこのカラー・レコードはどうなの?と取り出したのがボストンの1978年のセカンド・アルバム、Don’t Look Back。

ファースト・アルバムの大成功で途切れないツアーの合間にレコーディングされ完璧主義者のトム・シュルツにとってはやっつけ仕事感があったかもしれないがこのアルバムも結構売れたね。
今回の盤は2020年に再発専門レーベルのフライデー・ミュージックから発売されたもので、トランズルーセント、ブルー・アンド・ブラック・スワールって記載されていて、半透明なベースに青と黒の顔料が部分的に吹き付けられ飛び跳ねている感じでプレスされている。

(この色のアレンジには全く美意識が感じられないように思うのだが...)
半透明な箇所と青もしくは黒の顔料が混ざってプレスされている箇所は厳密に言えば若干ではあるが材質が異なり、再生に影響があるのでは?
まあ実際のところは音質の差異なんて無視できる仕様なんだろうけれど...
限定盤ということで通常盤よりお値段が少々高いので、オイラとしてはやっぱり視覚による鑑賞一択。
時折思い立ったように盤を取り出し、ターン・テーブルに一旦セットし暫しじっくりと眺めるも再生はせずにまた元のジャケに逆戻りと何とも奇妙な光景で、盤のミント・コンディションを維持しながら将来のアンティーク的な価値が爆上げするのを待つって感じかな?
ただ将来今のレコード・ブームも去り、かってCDがレコードをマーケットから駆逐し始めたCD黄金時代の頃と同様にまたまた中古レコードが2束3文で取り扱われる可能性の方が大かもね。