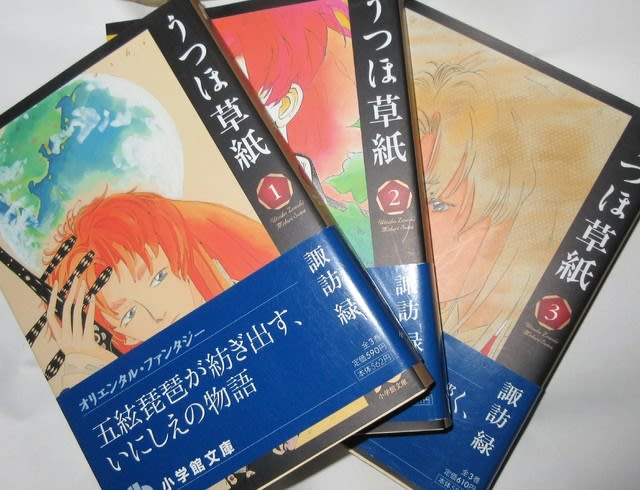ひめちゃんと獅子丸は、東の牧場に行こうとしました。
あちゃあ、小学生の集団登校です

急遽道を除けて、今朝はサマンサ坂を下りて、ヤギさんに逢いに行きます

いるかな?


「えさをあげえないで!」の掲示が、空しい
もう逢えないかな?
下野薬師寺からの帰り道、道鏡塚のある、龍興寺に寄ります。


仁王さま、ボケボケの写真になってしまいました。
又今度お会いしたときに、アップします。
さて、山門をくぐってみたものの、道鏡塚は何処だろう
手水舎があります。

向こうに、「史跡道鏡塚」とあって、説明板もあります


道鏡は、宝亀元年(770)八月、下野薬師寺の別当にされて、都からやって来たのです。
日本史の授業で、何となく覚えていた出来事でした。
まさか、道鏡が左遷された下野薬師寺を訪れるとは思ってもみませんでした。
「道鏡を守る会」、ご活躍を祈ります
「既にあった円墳を墓標として手厚く葬りました」ということは、後ろのこんもりした所が古墳で道鏡塚だということでしょうか?
すぐ近くに登り口かな?

まあ、やめておきましょう。
とりあえず、合掌
さて、ついでだから境内を散策です。

色々ありそうです。
「とちぎの名木百選、龍興寺のしらかし」です。

かわいい御三方がいます
何だろう?
不思議な光景になってきました。



天庭ですか
難しい。
聖観音です。
迫力有ります



大いなる慈悲の心と慈愛の眼差しをもって観守り、一切の苦しみを取り除いて心の安寧を与えて下さる母性具有の観音様です。
合掌
何だろう?


難しそうです。
境内の裏の方を廻ります。


本坊とあります。
鐘楼堂も落ち着いた雰囲気です。

本坊の前にある建物が本堂です。


弘法大師の像があります
真言宗のお寺ですね。
御朱印を頂きたいけど、時節柄、次の機会を待ちましょう
東の飛鳥・下野薬師寺付近、かなり地理不案内で、見落とした所があります。
日光開山・勝道上人父の藤麿墳を始として、未訪問がいくつもあります。
またの機会に