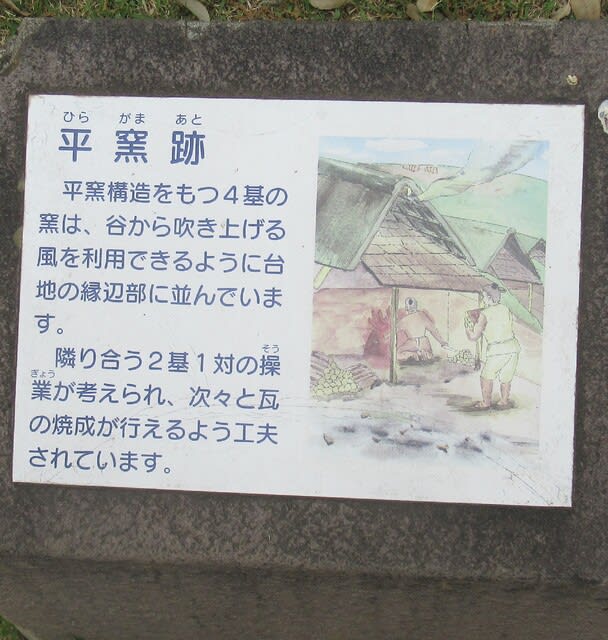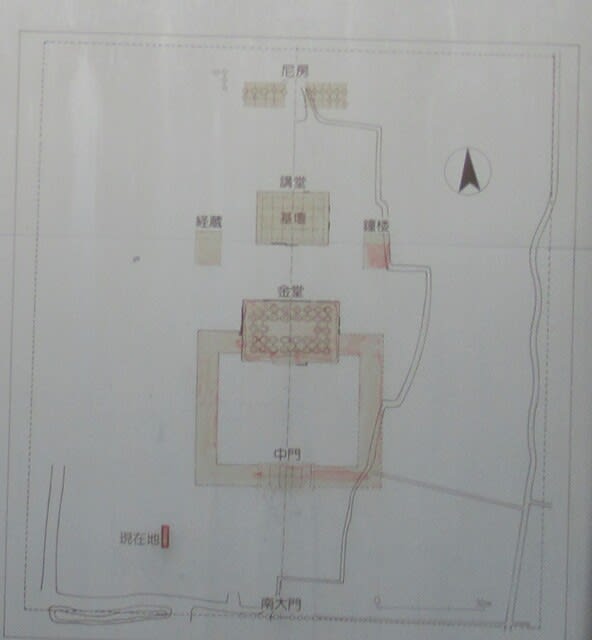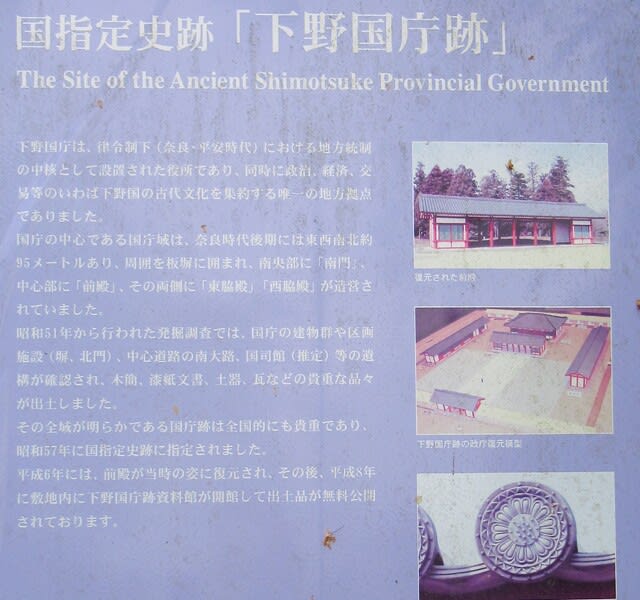ひめちゃんと獅子丸は、天神田(字天神の田んぼ)を廻って南の方から帰ります。
何気なく道ばたに、小さな祠です

ルピナスが成長しています
種を持ち始めた株もあります。

毎年こぼれ種が活躍してるのかな?
庚申塚古墳を通ります。


スッキリ晴れないね
早く帰って、朝ご飯にしましょう
思川の乙女河岸(おとめがし)に寄って帰ります
実は、来るときにも通っています。
でも、広くはない駐車場はなんと満杯でした
密でした
帰りに寄ろうと諦めてきました。
さて、どうかな?
よかった、誰もいません

説明板と船の模型があります。


乙女河岸の起源は戦国時代にまで遡るとされますが、注目されるようになるのは慶長5年(1600)7月25日の小山評定からです。この時、徳川家康は会津の上杉景勝を討つべく小山に進軍しましたが、その際武器や兵糧を乙女河岸から陸揚げしたとされています。
帰路は大雨によって渡良瀬川筋の栗橋の舟橋が押し流されていたため、8月4日乙女河岸から乗船し、武蔵国西火災に下船したことが「徳川実紀」に記されています。
そうなんですか
高瀬舟です。
こういう舟だったんですか
船底が平らなのですね



博物館でいただいた「乙女河岸跡」のパンフレットによれば、
中講積替河岸としての乙女河岸
江戸時代の舟運は年貢米が中心であったが、水深や水勢・川幅などにより利用できる船が制限された。水深の浅い上流では小型の船しか航行できないが、下流では大きな帆船で多量の仏師を運搬することが可能となる。思川は乙女や網戸付近を境に川の様相が変わり、ここから上流へは大型船の航行が出来なかった。
そのため、高瀬舟などの大型船はお止め河岸で荷を一旦下し、小型の都賀船などへと積み替える必要があったのである。乙女河岸は荷の積み替え拠点・中請積替河岸=中次河岸として繁栄した。
そうだったのですか
この高瀬舟は、大型船なのですね
付近の案内板があります。
遠くの山々も描かれています


赤城山は、中央の向こうに遙かに見える山です。
乙女河岸からも見えるんだ
不思議なものがあります


黒田長政が日光東照宮に寄進した鳥居の一部で、高瀬舟で運ばれたものが落下したといわれてきました。
高瀬舟はこんな大きな重いものも、運んだのですね
思川の方に降りてみます
上流の流れです。
かつては、豊かな水量を誇っていたのですね。
向こう岸に渡るにも舟が必要だったのでしょうね。

下流の流れです。

下流の方が、水量が多いかな?
川岸を少し散策して、公園に戻ります。
レトロな建物は、トイレです。
向こうに、日光に運ばれる予定だった石柱が見えます。
黄色い掲示板には、「イノシシ出没注意」です

一番左に見えるのは浅間山、その隣が赤城山ですね。

もう一ヶ所寄り道をして、赤城山の麓の村に帰ります