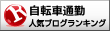橘氏と関係があると言われる内越氏ですが、まずは橘氏を知っておく必要があるので調べてみました。
橘氏は藤原氏に排斥され続けた影響もあり、歴史の影に隠れてしまいスポットライトがあたってこなかった氏ですが、実は長い歴史を持ち、興味深いエピソードも数多く残されている「隠れた名族」といえます。本記事では、そんな橘氏の歴史・子孫についてまとめます。

橘氏は、源氏や平氏、藤原氏ほど大きな子孫を残さなかったものの、その賜姓のエピソードは美しいものがあります。橘氏は、女帝から女官に賜姓されたという点が特徴的です。このエピソードは、橘氏が公卿や武士としてではなく、女官としての地位を重んじたことを示しています。女性が支配的であった時代において、そのような賜姓を受けることは異例であり、橘氏の家系における女性の権力や影響力を示しています。また、橘氏の賜姓は、高貴なる出自や功績を称えられる一方で、その家系がどのような人々に支えられてきたかを物語っています。
日本の歴史の中で重要な役割を果たした橘氏の由来には、元明天皇の宴での一言が基となっています。元明天皇は、橘が果実の王であり、枝は霜雪を恐れずに繁茂し、葉は寒暑をしのぎ、美しい様相を持つことから、「橘を氏とせよ」と述べました。これにより、三千代に橘宿禰の氏姓を与え、橘氏は誕生しました。橘は日本書紀の神話に登場し、「非時香菓」と呼ばれる柑橘系の木として、永遠性や永続性の象徴とされてきました。橘氏はその象徴から、日本の歴史において名家として栄え、重要な地位を築いてきました。
橘の由来は、神話上では垂仁天皇の命により遠い常世国から採取された木の実が橘となり、その橘にちなんで氏を賜ったと言われています。また、女帝元明天皇は美しく聡明な橘三千代を「いつも黄金に輝く橘の実」とたとえ、賞賛していた逸話もあります。彼女はその美しさと才知で多くの人々に愛され、橘の名を冠した橘三千代として親しまれました。今でも京都御所の紫宸殿には、橘と桜が並ぶ「右近の橘」があり、その歴史や由来が人々に伝えられています。橘の木は天皇家にゆかりが深く、橘三千代の逸話は美と知恵を象徴する物語として多くの人々に愛されています。
橘三千代は橘氏の歴史において重要な人物であり、橘氏の始祖である橘諸兄に次ぐ存在として知られています。生まれながらに朝廷の倉庫を管理・警護する家に生まれながら、その才能や学問を活かして朝廷内で勢力を築いた人物でした。彼女は敏達天皇の玄孫、美努王と結婚し、葛城王や佐為王、そして牟漏女王をもうけました。これらの子孫はそれぞれ後の日本の歴史に大きな影響を与えています。彼女が橘氏の名前を賜ったことをきっかけに、橘氏はますます勢力を拡大し、日本の歴史に名を刻む存在となりました。その後、橘氏は大和朝廷の中枢に位置し、藤原氏や菅原氏とともに古代日本の政治や文化において重要な役割を果たすことになりました。その功績は今なお称賛されるべきものであり、橘三千代の存在は古代日本の歴史において欠かせないものとなっています。
古代日本において藤原氏や橘氏の繁栄を支えた橘三千代。彼女は、藤原不比等に嫁ぎ、息子や娘の出世や後宮への立后に尽力し、自らも歌人として活躍しました。その功績が称えられ、「賢女」と称されました。また、彼女が賜った「橘氏」の姓は、実は一代限りのものであり、その名前を受け継ぐのは息子たちだった。橘三千代の果たした役割は、日本の歴史において軽んじられがちな女性たちの貢献を示す一例であり、彼女の存在は日本古代史の一角を照らしています。

平安末になると、橘は武家となります。橘遠保は、伊予橘氏の中心的存在であり、平将門の乱や藤原純友の乱での武勇で名を馳せました。遠保は藤原純友を捕らえるという快挙を成し遂げ、その活躍が評価され遠江国の国司に任命されました。さらに、伊予国宇和郡の所領も得ることとなりました。彼の子孫は多くの武将として活躍し、楠木正成を祖とする文献も存在します。伊予橘氏の重要な一員でありながらも、歴史の中で源氏や平氏に隠れる存在となった遠保は、武家橘氏の歴史を語る上で不可欠な人物と言えます。