
古代の伝説の女王「神功皇后」の物語
江戸時代末に作られた古今雛の中に神功皇后の人形がありました。
歴史の教科書や本で、「神功皇后(じんぐうこうごう)」という名前を聞いたことはありますか?今回は、この古代に活躍した女王の話を、分かりやすくまとめました。

**神功皇后ってどんな人?**
神功皇后の本名は「気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)」といいます。彼女は第14代仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の奥さんで、『日本書紀』や『古事記』という歴史書に登場します。
彼女のお父さんは「息長宿禰王(おきながのすくねのおう)」、お母さんは「葛城高額比売(かつらぎたかぬかひめ)」という人でした。歴史書では突然、仲哀天皇と結婚した話から登場し、その後の物語で重要な役割を果たします。
**仲哀天皇との出来事**
西暦193年、仲哀天皇が福井県の敦賀(つるが)にある神功皇后のもとを訪れた後、熊襲(くまそ)という九州南部にいた豪族を討つために山口県の豊浦(とゆうら)へ向かいました。
このとき、神功皇后は同行せず、天皇だけが出発しました。ところが、その後、天皇は神様の声(神託)を信じず、急に亡くなってしまいます。歴史書では、熊襲との戦いで矢に当たったとも書かれています。
**神功皇后の活躍**
仲哀天皇が亡くなったあと、神功皇后は神様から「西の国(新羅)を攻めるべきだ」というお告げを受けました。皇后はその指示に従い、軍を率いて朝鮮半島の新羅(しらぎ)へ向かいます。
新羅の王は、皇后の力に恐れをなして降伏しました。その後、神功皇后は九州へ帰る途中で赤ちゃんを産みそうになりますが、石を腰に巻いて出産を遅らせたという伝説があります。そして九州に戻ってから、息子の「譽田別命(ほむだわけのみこと)」(後の応神天皇)を産みました。
**国を守り続けた女王**
神功皇后はその後、息子を皇太子にして自らは摂政(せっしょう:天皇の代わりに政治を行う役職)として69年間も国を治めました。彼女の治世の間、たくさんの戦いを乗り越え、国を守り続けたのです。
**なぜ天皇にならなかったの?**
こんなに長い間、国のトップとして活躍した神功皇后ですが、今の天皇の歴史には含まれていません。それでも、江戸時代にはとても人気があり、明治時代には彼女の肖像画が高額紙幣(10円札)に使われたこともあります。
ただし、昭和時代になると「天皇ではない」という決定がされ、現在の教科書では天皇としては扱われていません。
**神功皇后は本当にいたの?**
神功皇后の存在については、学者の間でも意見が分かれています。一部では「実在しない」「歴史書を作るときに追加された人物だ」とも言われています。それでも、彼女の物語が日本の歴史書に多く書かれていることから、とても重要な人物だったことは間違いありません。
**まとめ**
神功皇后は、古代の日本で国を守り、新しい国とも向き合った伝説の女王でした。彼女が実在したかどうかは分かりませんが、その活躍は歴史に深く刻まれています。日本の歴史をもっと知りたいなら、ぜひ彼女の物語を読んでみてくださいね!










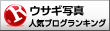
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます