馬頭観音
旧集落の道筋を歩いていると、自然石に刻まれた石仏に出会うことがよくあります。如来、観音菩薩、金剛像などさまざまな種類がありますが、特に目につくのが「馬頭観音」です。この石仏が多く見られるのには、深い理由があります。
石仏と信仰の特徴
一般的に、石仏や石塔は民間信仰の表れであり、地域の人々の信仰心を示すものです。しかし、西目地域ではこれらの石仏が他の地域に比べて少ないと感じられます。その背景には、西目独特の「御柱信仰」の影響があるのではないかと考えられます。御柱信仰は、木を神の依代として祀る風習であり、石仏や石塔の建立とは異なる信仰形態を持っているためです。
やっと見つけた馬頭観音の石仏
そんな西目地域でも、わずかに馬頭観音の石仏が残されています。今回、中沢地区で2つを見つけることができました。この石仏には「馬頭観世音」と刻まれており、かつては道沿いに祀られていたものと思われます。現在は台座が失われ、本体だけが残されていましたが、かつての信仰の名残を感じさせます。 2柱ありますが、一つは江戸時代のもので嘉永5年と書かれています。もうひとつは牛頭天王で昭和25年のものと並んでいます。


現在は使われていない馬道にあるので簡単に見つける事はできません。かしわ温泉から由利原に登れる道ですが、通行止めの看板があります。
よそではなぜ馬頭観音が多いのか?
馬頭観音(ばとうかんのん)は、六観音の一つで、正式には「馬頭観世音(ばとうかんぜおん)」と呼ばれます。特徴的なのは、頭上に馬の頭をいただいていることです。この姿は、六道の一つ「畜生道」に苦しむ者を救済する存在であることを示しています。そのため、昔から馬の守護神として広く信仰されてきました。
馬頭観音は、観世音菩薩の三十三の化身の中で唯一、忿怒(ふんぬ)の相を持っています。普通は三つの顔(三面)を持ち、腕は二本または八本(二臂・八臂)あるとされます。その怒りの表情は、人々を救う力の強さを表しており、「怒りが強ければ強いほど、救済の力も大きい」と考えられています。また、馬は大食であるため、人々の悩みや苦しみを食べ尽くしてくれる存在ともされています。
昔の人々にとって馬は、農耕や運搬に欠かせない大切な存在でした。そのため、農家では農耕馬の無病息災を願い、馬の産地では仔馬の健やかな成長を祈り、馬を生業とする人々は道中の安全を願いました。また、亡くなった馬の冥福を祈るためにも馬頭観音が祀られました。こうした信仰が広まり、各地に多くの馬頭観音の石仏が建立されたのです。 由利の立居地にも馬頭観音がきちんと祀られています。
馬頭観音の石仏を探してみよう
西目地域では、他の地域と比べると石仏の数が少ないものの、馬頭観音は今も静かにたたずみ、かつての人々の思いを伝えています。井岡地区の宮比神社と海士剥の月山神社にもありますにもあって道端や寺院の片隅にひっそりと残されていることもあります。もし散策する機会があれば、ぜひ馬頭観音を探してみてください。そこには、馬とともに生きた人々の祈りが刻まれていることでしょう。










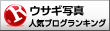
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます