メルクの修道院の老僧アソドが見習修道士の若き日に遭遇した7日間の奇怪な物語を回想し、書き残した手記。
中世、イタリア。フランチェスコ会修道士、バスカヴィルのウィリアムとメルクのアソドは、ある山の上の修道院を訪ねる。折りしも、修道士が死体で発見され、その調査を頼まれる。
異形の建物には貴重な古文書が置かれた迷宮の文書館があった。
ウィリアムが調査を始めるのを待っていたかの様に、次々と殺人が起こる。
文書館の迷宮に秘密があると、ウィリアムとアソドは中に入り込んで行く。
ミステリーと思って読み始めたが、その要素もあるが、異端審判の話や、各宗派の教えの違いや対立、宗派にからんだ権力争いなどの話もあり、読んでいても結構難しく、何処まで理解できたのか。
中世の古城のような、僧院。その場所や描写も細かいので、想像するが、映像でもみたくなる。
映画になっていて、1度観たのだが結構忘れている。しかし、僧院の雰囲気はきっと映画の映像が頭にあって、重々しい空気感を感じながら読んだ。
異形の建物の迷宮は、中村青司の館を思い出してしまう。
図が出ているのだが、ウィリアムがその迷宮を解いて行く時、図を見ながら理解していくのは楽しかった。
アソドが初めて触れた女性に抱く恋心も、この物語の重要な話になっている。
ミステリーだけでなく、色々な読み方が出来る物語だと思う。
「笑い」も話題のひとつになっている。笑いは、教義を広めるのに必要かということ。
キリストは笑わなかったと。しかしそれは、弟子が書いていることなので、真実かどうかはわからないが。
三原順さんの「はみだしっこ」で、アンジーが「オレは笑わない奴は信じない」というのがあった。
「はみだしっこ」は自分のバイブルだから、自分もそう思っていた。笑いは色々な意味で必要だと思うけれど。
自分が1番感じたのは、宗教なんて、生きている人間の欲や権力の前ではただの利用する物になってしまうと言う事。
宗教の名の元に、どれだけ血が流された事か。
それは、中世のこの物語の時代も、今も変わっていないのだと。
国境がなくなると同時に宗教の壁がなくならないと、人類が平和になる事はないのかも知れない。
中世、イタリア。フランチェスコ会修道士、バスカヴィルのウィリアムとメルクのアソドは、ある山の上の修道院を訪ねる。折りしも、修道士が死体で発見され、その調査を頼まれる。
異形の建物には貴重な古文書が置かれた迷宮の文書館があった。
ウィリアムが調査を始めるのを待っていたかの様に、次々と殺人が起こる。
文書館の迷宮に秘密があると、ウィリアムとアソドは中に入り込んで行く。
ミステリーと思って読み始めたが、その要素もあるが、異端審判の話や、各宗派の教えの違いや対立、宗派にからんだ権力争いなどの話もあり、読んでいても結構難しく、何処まで理解できたのか。
中世の古城のような、僧院。その場所や描写も細かいので、想像するが、映像でもみたくなる。
映画になっていて、1度観たのだが結構忘れている。しかし、僧院の雰囲気はきっと映画の映像が頭にあって、重々しい空気感を感じながら読んだ。
異形の建物の迷宮は、中村青司の館を思い出してしまう。
図が出ているのだが、ウィリアムがその迷宮を解いて行く時、図を見ながら理解していくのは楽しかった。
アソドが初めて触れた女性に抱く恋心も、この物語の重要な話になっている。
ミステリーだけでなく、色々な読み方が出来る物語だと思う。
「笑い」も話題のひとつになっている。笑いは、教義を広めるのに必要かということ。
キリストは笑わなかったと。しかしそれは、弟子が書いていることなので、真実かどうかはわからないが。
三原順さんの「はみだしっこ」で、アンジーが「オレは笑わない奴は信じない」というのがあった。
「はみだしっこ」は自分のバイブルだから、自分もそう思っていた。笑いは色々な意味で必要だと思うけれど。
自分が1番感じたのは、宗教なんて、生きている人間の欲や権力の前ではただの利用する物になってしまうと言う事。
宗教の名の元に、どれだけ血が流された事か。
それは、中世のこの物語の時代も、今も変わっていないのだと。
国境がなくなると同時に宗教の壁がなくならないと、人類が平和になる事はないのかも知れない。
















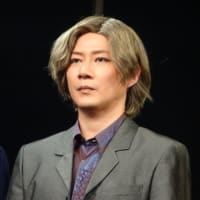
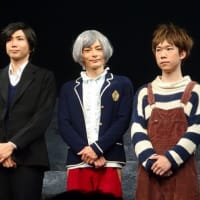








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます