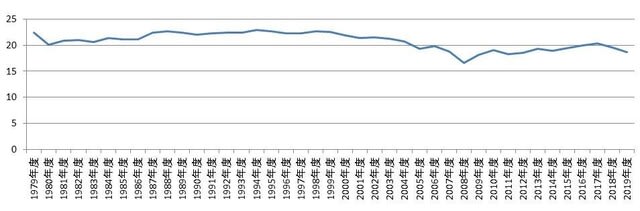多くの国で、国民の油断を突いたのでしょうか、コロナがまた猛威を振るい始めているようです。
それに重なるように、原油価格の高騰の問題が起きてきました。
産油国は多くを語らないようですが、産油国の身になってみれば、世界中が「化石燃料から再生可能エネルギーへ」と努力を始めているのですから、原油の埋蔵量が豊富だなどと言って楽観していられる状態ではないという事ではないでしょうか。
当然、今の内に少しでも原油価格を上げたいと考えるのは人情というものでしょう。
そうなれば、原油は投機対象商品ですから、当然値動きは荒くなって来るでしょう。
またこれにタイミングがあっているわけですが、多くの国がコロナ禍からの経済の回復に舵を切っています。当然多様な資源や半導体など材料、部品への需要が多くなり、資源価格を始めそうしたものの一般的な値上がり傾向が出るときです。
更に経済回復を目指す国では、政府の梃子入れで物価は上昇基調です。
そこでかつての石油危機ほどではないにしても原油価格の値上がりを産油国が期待するというのもある意味では当然かもしれません。
再エネ、再エネと言っても、現状、石油は圧倒的に主要なエネルギー源です。多くの国で原油価格の高騰は物価上昇の動きを強くし、典型的にはアメリカの様な物価上昇が、ヨーロッパでもアジアでも見られそうな気配です。
2%インフレターゲットなど疾うに超えているアメリカでは、FRBはインフレ懸念から金融の引き締めを示唆し、まずは量的、更に金利の引き上げも視野という事のようです。
その結果、国際投機資本の動きはドル買いとなり、ドル高、日本にとっては円安の動きが出ます。
しかし、アメリカにとってドル高は大きな痛手になるでしょう。インフレは避けたい、しかしドル高にはしたくない。FRBは難しい選択を迫られているようです。
石油消費国は、原油価格の高騰を何とか止めてほしいと思っています。
そこでアメリカは、アメリカも原油の生産を増やすし輸出もするが、日本などの消費国でも備蓄を一部放出して原油相場を冷やそうという手に出ました。
慌てたマーケットは「一瞬だけ」原油価格の下落をみましたが、よく考えれば、例えば日本の場合の備蓄は140日余だそうですが、そのうち何日分が放出可能かと考えても、供給増加は知れていると気づいたのでしょう。
結果は理論通り原油の先物の価格上昇という形になってきました。
マーケットは、備蓄の放出など高が知れていると読んだのでしょう。そしておそらく、日本のやりくりの様子を新聞記事で見ても、とても対抗手段にはならないが、要請された通り真面目にやりましたという程度と見えてしまいます。
という事で問題は今後です。
この先さらに原油価格が上昇し、世界中がインフレムードになってくるようなことが起こり得るのでしょうか。
基本的には産油国次第でしょうが、これまでの経験から見ても、原油価格が高騰した後はまた下がることの繰り返しです。
ただ、下手な対応をすると、かつての石油危機の後遺症で先進国が一様にスタグフレーションに陥ったようなことが起こりかねません。
さてどんな問題が待ち受けているのでしょか。この辺の検討を次回してみたいと思います。