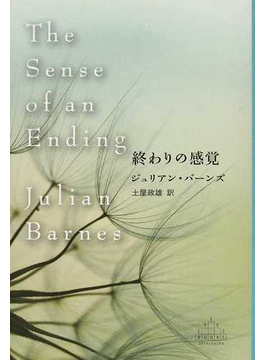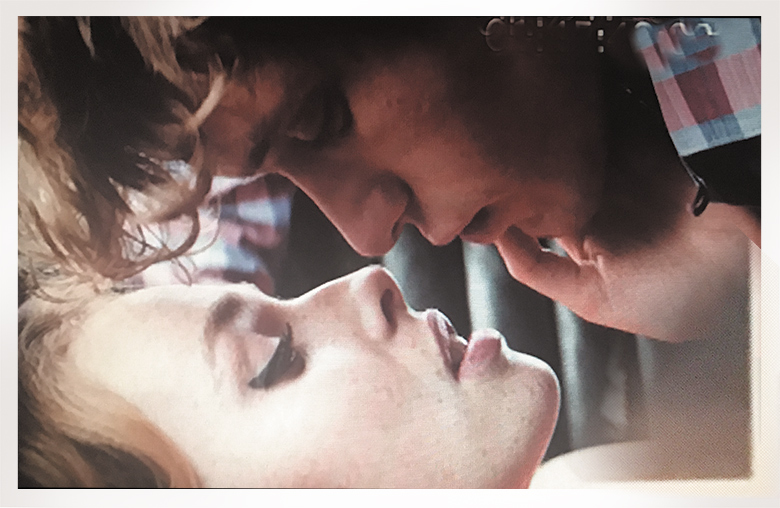OB訪問サイトとの関連は?
2019/3/27 酒井一樹 | 株式会社エイリスト 就活SWOT代表
またしても、OB訪問絡みで許されない事件が起きてしまった。
先月、大林組に所属する社会人が「OB訪問」にかこつけて就活生に猥褻行為をしようとしたと報道されたのは記憶に新しいが、今度は住友商事に所属していた社会人による性的暴行事件が報じられた。
【容疑者はすでに懲戒解雇】
事件が起きたのは就活解禁直後の3月1日〜2日にかけてであり、3月6日に住友商事が容疑者を解雇したという。
そして逮捕日である3月26日に住友商事からリリースが出されている。
2019/03/26 住友商事 当社元社員の逮捕について
当社の元社員が、就職活動中の学生に対して猥褻な行為をしたとして、本日逮捕されました。
当社はこの事態をたいへん重く受け止めており、被害にあわれた方に心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。
また、就職活動中の学生の皆様、関係者の方々にたいへんなご不安、ご迷惑をおかけすることとなり、重ねて深くお詫び申し上げます。
当社はこのような事態が二度と起こらないよう繰り返し社内徹底してまいります。
出典:https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2019/group/11660/
逮捕された三好琢也容疑者は24歳であり、住友商事には入社一年目だったようだ。ネット上では同容疑者のものと思われるTwitterのログや予備校時代〜大学時代のプロフィールも見つかっており、それが本人のものであれば慶應義塾大学の体育会所属であったことなどが判明している。
【住友商事は、OB訪問を積極的に推進】
なお住友商事は昨年OB訪問マッチングサイト「ビズリーチキャンパス」と提携し、OB訪問を積極的に実施していた。
今回の事件との関連は不明だが、本事件が同サービスでのOB登録にどのような影響が出るのかも注目が集まっている。
OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」住友商事の社員 約350名が登録
学生が社会人に会う機会を増やし、主体的なキャリア選択を支援
株式会社ビズリーチ(所在地:東京都渋谷区/代表取締役社長:南 壮一郎)は、当社が運営するOB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」が、住友商事株式会社(本社:東京都中央区/代表取締役 社長執行役員CEO:中村邦晴、以下「住友商事」)に2018年2月1日より導入されることをお知らせします。
入社1年目の若手社員から中堅社員を対象に、幅広い職種の社員約350名が「ビズリーチ・キャンパス」に登録し、大学生・大学院生からの希望に応じてOB/OG訪問に対応します。
出典:https://www.bizreach.co.jp/pressroom/pressrelease/2018/0201.html
同サイトは、OBの出身大学に在籍する学生がOB訪問できる仕組みを提供しているという。
今回被害にあった学生が「地方から上京していた」という情報と、容疑者が慶應義塾大学出身だったという情報が確かであれば、OB訪問が成立した経緯はこのサービスとは無関係かもしれない。
しかし住友商事が「正式に企業としてOB訪問アプリを使用していた」という事実は波紋を呼ぶことになるだろう。
【今回の事件は準強制性交等罪で起訴】
住友商事の対応は早く、報道された時点ですでに同社員は解雇された後だった。このため「元社員」として報道されているが、猥褻行為を行った時点では社員であり、その地位を利用してOB訪問を受け付けていた事になる。
ホテルの鍵を盗み部屋に侵入したという事なので擁護する余地もない。
この手の事件が報道されるのは氷山の一角だと常々言われているが、ここまで明確に犯罪行為に走った例は珍しいのではないだろうか。
実際、今回の事件は「準強制性交等罪」とされている。
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴力・脅迫によらずこれらの状態にして、性交等をする罪。刑法第178条第2項が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
出典:デジタル大辞泉
これは「非親告罪」であり、被害者による告訴がなくとも起訴ができる罪だ。
「OB訪問でセクハラを受けた」というような話とは一線を画している。
居酒屋に誘われた時点で断ることはできたかもしれないが、志望企業の社員相手に飲酒を断りづらい状況だったことも想像に難くない。
仮に「男社会なんだからお酒くらい付き合えないとやっていけない」などと志望企業の社会人に言われれば、言いくるめられてしまう学生は多いだろう。
「OBではなく女性のOGから話を聞けば良いのではないか」と思う方もいるかもしれないが、商社のように総合職のほとんどが男性という企業でOG訪問をするというのはかなり難しい。
いずれにしても、居酒屋や相手宅でのOB訪問は避けるべきだろう。
OB訪問で居酒屋を指定された時点で警戒しなければならないというのが悲しい事に現実だ。
今回は「地方からの上京」で就活をしているタイミングであり、泊まっているホテルを相手が知っていたという事も被害に遭う要因となってしまった。
【学生を守るため、企業が動くべき時が来ている】
就活解禁日の3月1日に上京し、このような被害に遭えばその後の就活に与える悪影響は計り知れない。
もちろん就活という要素を抜きにしても犯罪なのだが、到底許される行為ではなく倫理観が欠如している。
しかし学生が自衛するにも立場上限界があり、このような「危ない橋」を渡らなければならない状況を企業側が解消させるように動いていくべきだ。
その対策を怠った企業は、すでに報じられている住友商事や大林組のように不名誉な風評を得る可能性があると言えるだろう。
志望学生を守り、そのようなリスクを回避するために企業は何ができるか、その対応が今求められている。
酒井一樹
株式会社エイリスト 就活SWOT代表
慶應義塾大学在学中、世界初の就活SNS「Dachinco!」の代表に就任。国内最大の就活SNSへと成長させた後に大学を卒業し、エグゼクティブサーチを行う人材ベンチャーに入社。役員・事業責任者などの幹部人材の採用支援に携わる。2009年にエイリストを設立し「自分の頭で考え、行動する人材を増やす事」を命題として就職情報サイト「就活SWOT( https://swot.jp )」を開設。
2019年3月27日-大林組に所属する社会人によるOB訪問事件が報道されたのは記憶に新しいが、今度は住友商事に所属していた社会人 ... この手の事件が報道されるのは氷山の一角だと常々言われているが、ここまで明確に犯罪行為に走った例は珍しいの
住友商事「元社員」として報道されているが、猥褻行為を行った時点では社員でありその地位を利用してOB訪問を受け付けていた事になる。ホテルの鍵を盗み部屋に侵入したという事なので擁護する余地もない。
2019/03/28
“「OBではなく女性のOGから話を聞けば良いのではないか」と思う方もいるかもしれないが、商社のように総合職のほとんどが男性という企業でOG訪問をするというのはかなり難しい”