マドンナに大島麻衣( 30 歳)さんを迎えての第六弾の旅。再放送が待ちきれず、鎌倉淳さんの「タビリス」から、その旅を追体験した。「タビリス」の記事は原稿用紙に換算すると 30 枚という大作で、旅の全貌が分かるのです。
第一日(高速バスの利用を勧められる)
8 :16 に東大寺大仏殿を出発し、まず奈良駅に出て案内所で情報を集め、三重県に出て高山を目指します。
例によって県境では少し歩きますが、梅の名所月ヶ瀬を経て、三重県伊賀市「上野市駅」にお昼過ぎに到着します。この案内所で「名古屋行の高速バスはここから関バスセンターまでは、下道というか一般国道を走りますので、この区間は路線バスといっていいのではありませんか」というアドバイスを受ける。これを利用し、関バスセンター(鈴鹿市)に 15 : 06 に着いた。
そこから 7km 歩き亀山駅前に、さらに平田町駅に 19 : 27 に着き、ホテルキャッスルイン鈴鹿に宿泊した。
(芭蕉の生誕地伊賀市は、 558.17 ㎢もある広い都市で、奈良県、京都府、滋賀県と接していた。いつか行ってみたい)
第二日(名古屋市金山行を教えられる)
平田町駅 8 : 18 出発。四日市駅~桑名駅~たちばなの里~(徒歩で愛知県に入り)~近鉄蟹江駅前から、少し歩いて名古屋行のバス停を探しているところで、(バスのツウ)とでもいうべき男性に、名古屋金山行の市営バスの戸田停留所を教えられ、一気に名古屋に入る。金山着 16 : 57 。
「タビリス」鎌倉淳さんは、桑名に着く前の近鉄六把野駅から(あるいは桑名からでも)岐阜を目指していれば、名鉄岐阜に 17 : 39 に着くルートのあったことを検証しておられる。(確かに、こちらの方が楽だ)
実際には、名古屋を北上し小牧に進み、知り合った高校の校長という人の勧めで、尾張一宮まで行き、ホテル東横イン一宮駅前店に投宿することになるが、午後 11 ; 00 過ぎ。
第三日(美濃太田駅案内所にて活路を見出す)
尾張一之宮駅前 6 : 58 出発。遅い到着、早朝出発、連日の長距離の歩きで疲労困憊の筈。9 : 09 に着いた岐阜バスターミナルで、イラついたマドンナが「決め手がないと乗らないんですか?」「来たバスに乗っちゃうぐらいの勢いで勝負をかけていかないと進まないですよ」と、決断のつかない田中、羽田レギュラーを牽制する一幕もあったようだが、その後 15 : 45 に到着した美濃太田駅で、案内所係員の「八百津~下河原を経て福地峠を越えていくルート」が紹介され、行くべきルートが決定した。
「タビリス」鎌倉淳氏は、「丁寧に対応してくれた案内所係員のクリーンヒット」と称えている。
この日は「まつや旅館」(岐阜県加茂郡八百津町)に宿泊。
第四日(薄氷の勝利)
高山濃飛バスセンターに 17 : 31 到着できたのだからいいのだが、鎌倉淳氏が「薄氷の勝利」というのは、全体で 46,6 km も歩いたし、三重県から直接岐阜に入らず、尾張一宮経由にしたこと、特に最後の詰めの部分、高山線白川口駅から一区進んだバス停「三掛」から、飛騨川べりの国道 41 号線を 12.5 km 歩き、やっと着いた焼石駅前から下呂駅、あとは、一気に高山に入ったそのゴールの仕方が、もう少し楽なルートが数本検証できただけに物足りなく感じたのだろう。
飛騨川は、今年七月上旬の豪雨で氾濫し、下呂市が水害に見舞われたことは記憶に新しいが、昭和 44 年(1969 )8 月 18 日には、未曽有の惨事を引き起こした。それは、白川口駅近くの国道 41 号線路上で集中豪雨を避けて避難していた観光バス 2 台を、近くの山から流れ落ちた土石流が、濁流渦巻く飛騨川に押し流し、乗客乗員 104 名の命を奪った事故だ。それは、日本バス事故最大のものであった。
ところで、到着地の高山市の面積は、2, 179.35 ㎢ で、これは東京都の面積に近い。それでいて人口は 10 万人に満たない。日本は大都市に人が集まり過ぎ、過疎地は益々過疎になっていく。















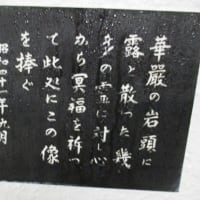




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます