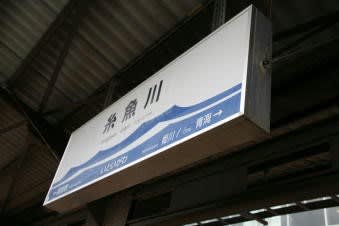信濃大町駅は、立山黒部アルペンルートの起点でもあります。

多くの人はここで下車。南小谷行の乗り変えたのは、キャンプに行く小学生。
大糸線下り 普通 南小谷行。
 信濃大町 10:28発
北大町 10:31着 10:32発
信濃大町 10:28発
北大町 10:31着 10:32発
次々と雲がわき出てきます。
 信濃木崎 10:35着 10:36発
信濃木崎 10:35着 10:36発
仁科三湖の一つ、木崎湖が左手に見えてきます。

 稲尾 10:39着 10:39発
稲尾 10:39着 10:39発
 海ノ口 10:42着 10:42発
海ノ口 10:42着 10:42発
農具川が流れこむ「湖の口」に位置するとから付いた名前。隣の稲尾駅と同じようにホーム正面から木崎湖が見えます。木崎湖は近世には「海之口池」と呼ばれていたそうです。
電車は上っていきます。次の簗場駅は標高827.2m。大糸線で一番高いところに位置します。
 簗場 10:46着 10:47発
簗場 10:46着 10:47発
青木湖でキャンプをする小学生が降りていきました。

小学生が降りた後の車内はがら~んとしています。
 ヤナバスキー場前 レ
南神城 10:56着 10:56発
ヤナバスキー場前 レ
南神城 10:56着 10:56発
JR東日本最西端の駅です。
 神城 11:00着 11:00発
神城 11:00着 11:00発
スキー場をよく見ます。この辺り白馬村は、大量の降雪がある「特別豪雪地帯」。そのため、スキーを軸とした観光が盛んです。
 飯森 11:03着 11:03発
白馬 11:07着 11:08発
飯森 11:03着 11:03発
白馬 11:07着 11:08発
白馬村の中心駅です。白馬村は民宿発祥の地とも言われています。(諸説有り)

白馬岳や鑓ヶ岳、唐松岳などの山々に源とする松川を渡ります。
 信濃森上 11:10着 11:11発
信濃森上 11:10着 11:11発
だいぶ雨脚が強くなってきました。

右手に姫川第二ダムが見えます。
 白馬大池 11:16着 11:17発
白馬大池 11:16着 11:17発
駅名に「白馬」とありますが、駅は白馬村ではなく小谷村にあります。「大池」は駅西方にそびえる白馬乗鞍岳の山頂付近にある池、白馬大池に由来します。
左手に栂池高原スキー場が広がります。
 千国 11:21着 11:22発
千国 11:21着 11:22発

本当に残念でした。北アルプス。
 南小谷 11:26着
南小谷 11:26着

2010年(平成22年)8月に改装された駅舎の待合室には畳敷きのスペースがあり、冬には炬燵が置かれるそうです。

大糸線は、江戸時代に越後では松本街道そして信州では糸魚川街道と呼ばれた、松本と糸魚川を結ぶ千国街道に沿って走っています。
千石街道の名は、街道の宿場の一つである千国(現小谷村)が由来。
日本海からは塩や海産物が運ばれ山国信州からは農産物や山の幸が運ばれ、それらの荷物は、牛馬や人の背に担がれて運ばれたのです。
駅スタンプの絵柄はそれが題材となっています。

土砂降りです。
一駅一名物の「茅葺屋根付観光案内板」も霞んで見えます。

何とか駅前にあるお土産屋さんに行ってみました。

ここでなければ手にすることが出来ない物はと聞いたところ、「小谷漬」と「若笹寿し」
が地元の物と勧められ買い求めました。

南小谷駅は、JR東日本が管轄する電化区間と、JR西日本が管轄する非電化区間との境界駅です。
「特急あずさ」が下りは千葉駅始発、上りは新宿駅行各1本が定期運行されています。
JR西日本 大糸線下り 普通 糸魚川行は、JR西日本のローカル線用の小型気動車、キハ120形気動車1両です。

 南小谷 12:00発
南小谷 12:00発
南小谷駅から先、トンネル区間が多くなります。
立山トンネル385m
姫川を渡ります。
 中土 12:06着 12:06発
中土 12:06着 12:06発
池原トンネル178m
袖ノ山トンネル385m
滝ノ口トンネル380m
姫川を縫うように進みます。

外山トンネル1,563m
雨もさることながら、大小のトンネルが続くため、温度差によって窓ガラスが曇ります。
 北小谷 12:13着 12:14発
北小谷 12:13着 12:14発
下寺トンネル50m
李平トンネル380m
大糸線最長の真那板山トンネル3,125m
平岩 12:22着 12:22発
達磨山トンネル158m
鎌倉山トンネル1,647m
江尻トンネル476m
第2西山トンネル48m
小滝 12:36着 12:36発
ここの標高は134m。南小谷駅が513.1mですから、379.1m下ったことになります。
駅構内右手には給水塔の残骸が残っています。

姫川の流れも、だいぶ緩やかになってきました。

大前トンネル135m
唐沢トンネル307m
雨も止んできました。
 根知 12:42着 12:43発
根知 12:42着 12:43発
根小屋トンネル80m
中山トンネル400m
大野トンネル694m
頸城大野 12:48着 12:49発
 姫川 12:52着 12:52発
姫川 12:52着 12:52発
駅と国道を挟んで向かい側には姫川病院があったようですが、廃墟となっているようです。

水前トンネル463m
北陸新幹線をアンダーパスすると、糸魚川駅に到着です。

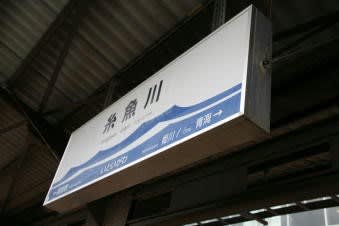 糸魚川 12:57着
糸魚川 12:57着
つづく