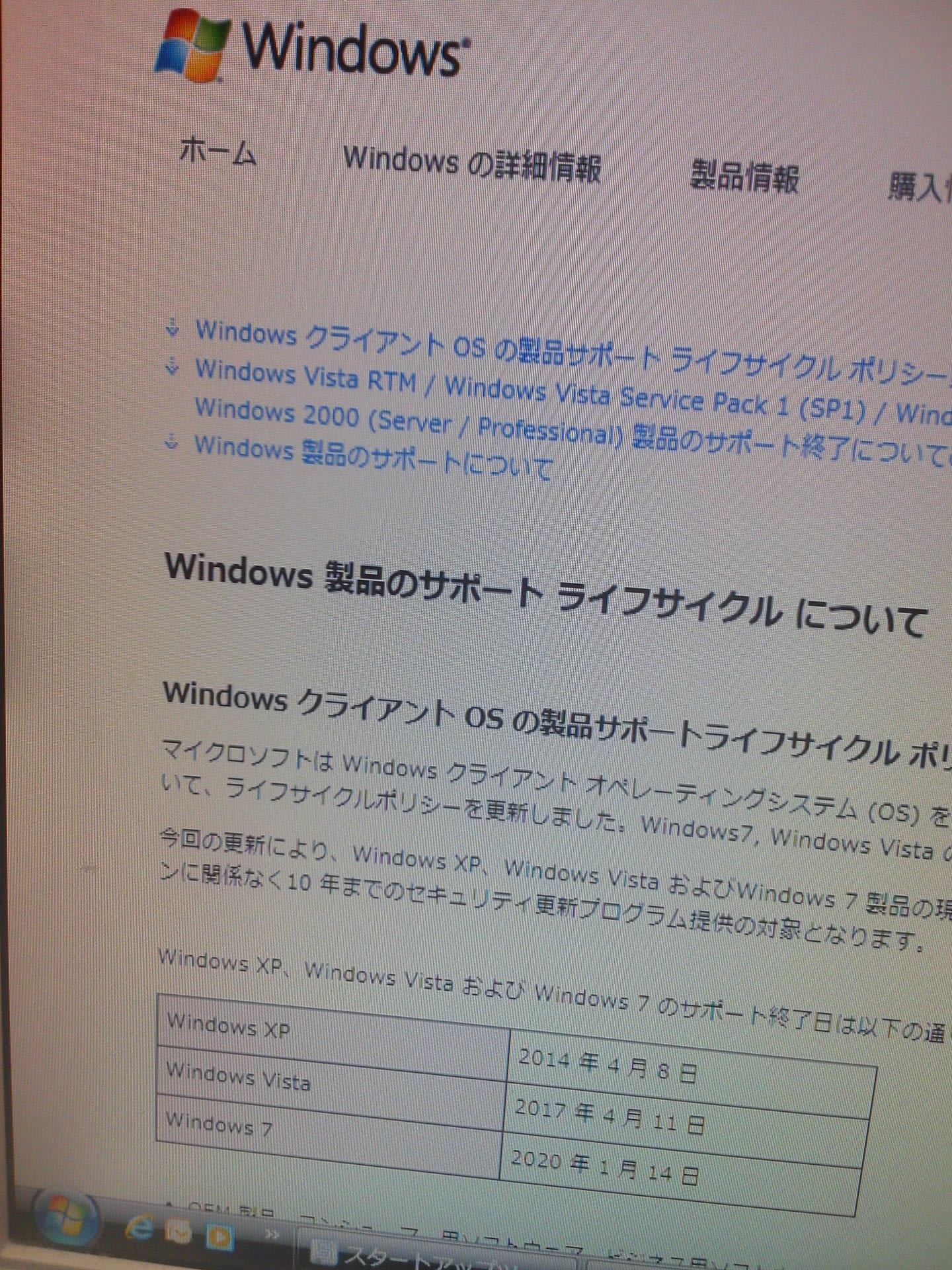野菜を始めとする山野草や動物や魚の名称を書く時
漢字もあればひらがなもカタカナもありますが、
むしろカタカナ書きが一般的になりつつあります
調べてみると
昭和21年内閣訓令32号「当用漢字表」に「使用上の注意事項」として
ホ、動植物の名称は、かな書きにする。
とあるが実際にはカタカナを用いることが多かったようです。
特に自然科学の学術論文ではひらがなよりカタカナの使用が多かったそうです
昭和56年に「常用漢字表」に改められたときに上記の注意事項は削除されています
カタカナ書きは慣習によって現在に引き継がれているのでしょう
昭和61年7月1日内閣告示第1号「現代仮名遣い」では
かな書き規定が無くなったのに加えて前書きで
三、 この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や
個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない
との文言が付け加えられています
キャベツ、トマト、コアラ、パンダ・・・と外来語が多い現代社会の中で
日本に昔からいる動植物もカタカナで統一して呼ぶようになったと思われます
文学・芸術的表現ではカタカナだと味気ないので漢字を使えばいいし
ひらがなが似合う時もあります
私は出来るだけわかりやすくするため、カタカナ表記に努めたいと思います
三つの表現ことば(字体)をもつ日本文化の奥ゆかしさを感じた
小ちゃな探訪でした
漢字もあればひらがなもカタカナもありますが、
むしろカタカナ書きが一般的になりつつあります
調べてみると
昭和21年内閣訓令32号「当用漢字表」に「使用上の注意事項」として
ホ、動植物の名称は、かな書きにする。
とあるが実際にはカタカナを用いることが多かったようです。
特に自然科学の学術論文ではひらがなよりカタカナの使用が多かったそうです
昭和56年に「常用漢字表」に改められたときに上記の注意事項は削除されています
カタカナ書きは慣習によって現在に引き継がれているのでしょう
昭和61年7月1日内閣告示第1号「現代仮名遣い」では
かな書き規定が無くなったのに加えて前書きで
三、 この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や
個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない
との文言が付け加えられています
キャベツ、トマト、コアラ、パンダ・・・と外来語が多い現代社会の中で
日本に昔からいる動植物もカタカナで統一して呼ぶようになったと思われます
文学・芸術的表現ではカタカナだと味気ないので漢字を使えばいいし
ひらがなが似合う時もあります
私は出来るだけわかりやすくするため、カタカナ表記に努めたいと思います
三つの表現ことば(字体)をもつ日本文化の奥ゆかしさを感じた
小ちゃな探訪でした