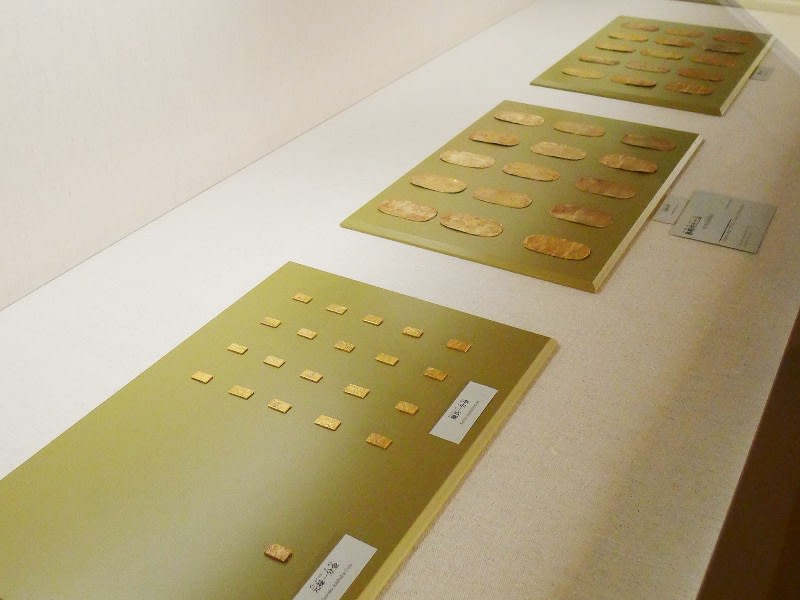一昨日の「トーハク」では軽薄だけど、やはり東博は凄い (その5) のつづきは、東京国立博物館(東博)本館2階の「日本美術の流れ」から、私の注目作品をご紹介します。

昨年9月の記事「超々久しぶりの千秋公園(その4、まだ寄り道)」で、
私は一生の間に何点拝見することができるのでしょうかねぇ。っつうか、私はまだ1点も「佐竹本三十六歌仙絵巻」を生で観たことがないのが悲しい…
 と書いた佐竹本三十六歌仙絵巻を、ついに生で観ることができました
と書いた佐竹本三十六歌仙絵巻を、ついに生で観ることができました
東博が原操さんという方から寄贈された という「佐竹本三十六歌仙絵巻断簡(忠峯)」です(右の画像をクリックするとアップ画像をご覧いただけます)。
という「佐竹本三十六歌仙絵巻断簡(忠峯)」です(右の画像をクリックするとアップ画像をご覧いただけます)。
説明プレートを引用しましょう。
壬生忠峯(みぶのただみね)は9世紀から10世紀にかけて活躍し、『古今和歌集』の撰者もつとめた。黒装束に、緌(おいかけ)を着けた冠を被り、武官らしいきりりとした面構えで、彼方を見やっている。目鼻や眉、鬚等を精細に描き込んで個性的な表情を創り出すのは、まさに似絵(にせえ)の本領。
イメージしていたものより、大ぶりだった(36.6cm × 59.6cm)のが意外でした。
ちなみに説明にある「緌(おいかけ)」というのは、武官が冠の両脇につける「馬の毛をブラシのように束ねて扇形に開いた用途不明の飾り(Wikipediaの記述より)」のことです。
ところで、ここに書かれている忠峯の歌は、拾遺和歌集に収められている、
はるたつと いふばかりにや みよしのの
やまもかすみて けさはみゆらむ
らしい(言われてみればそう読めないこともない)。あと半月で立春です。

次は、「その1」でちらりと触れた伊藤若冲の「松梅群鶏図屏風」。

 上の写真ではものの見事に人影に遮られてしまっていますが、この作品の見どころの一つは点描法で描かれた石灯籠(右の写真)でしょう。
上の写真ではものの見事に人影に遮られてしまっていますが、この作品の見どころの一つは点描法で描かれた石灯籠(右の写真)でしょう。
わたし的には、作品全体の中で石灯籠だけが浮いている感じで、ちぃと…なんですが…
一方で、さすがに若冲、様々なポーズを決めるニワトリたちが見事です。
こちら なんか、まさしく「正面から向かい合っている」というか…
なんか、まさしく「正面から向かい合っている」というか…

ニワトリの顔を真っ正面から見ると、こんな風になるのでしょうか。
なんともお間抜けに見えますナ。

最後は、わたしにとって総合文化展 最大のお楽しみ、「武士の装い―平安~江戸」。
今回も魅せてくれました
なんといっても、こちらの兜

左は明珍吉久作で「天和3年(1683年)」の銘のある紺糸素懸威栄螺形兜(こんいとすがけおどし さざえなりのかぶと)、そして右は岩井善兵衛作の茶糸威野郎頭形兜(ちゃいとおどし やろうがしらなりのかぶと)
方やサザエに、方や綾小路きみまろ頭(正しくは野郎頭:やろうがしら。こちらの記事にも別の作品が登場しました)のねじりはちまき添えデス
こちらの具足も意表を突きます。

越前福井藩主、松平齊善(なりさわ)公(11代将軍 家斉の二十二男 )所用の茶糸威四枚胴具足というものだそうで、兜にそびえ立つ飾り(頭立:ずたつ というものらしい)が強烈です
)所用の茶糸威四枚胴具足というものだそうで、兜にそびえ立つ飾り(頭立:ずたつ というものらしい)が強烈です
[左の写真をクリックすると背面からの写真をご覧いただけます]
この頭立に電飾 を施したらルミナリエみたいに見えるかもしれません
を施したらルミナリエみたいに見えるかもしれません
一気に時代を400年ほどさかのぼって、室町時代(15世紀)のこの鎧は美しかったぁ~
 「色々糸威腹巻」というのがこの鎧の名前ですが、腹巻といっても寝冷えを防ぐためのものではなく
「色々糸威腹巻」というのがこの鎧の名前ですが、腹巻といっても寝冷えを防ぐためのものではなく 、鎧の形式の一つです。
、鎧の形式の一つです。
シルエット が実に美しい…
が実に美しい…
っつうか、相当にスリムじゃないと着られない のではないでしょうか?
のではないでしょうか?
メタボ系の人がむりやり着ると、背中がガバぁ~っと開いて、かなりみっともないことになりそうです
 そんな時には、陣羽織で隠すしかないでしょう。
そんな時には、陣羽織で隠すしかないでしょう。
左の陣羽織「黒毛『五』文字模様」は江戸時代、それも19世紀のものですから、ほとんど実用性は考慮されていないものと思われます。
説明書きによると、この「毛」はヤクの毛を黒く染めたもの(黒毛和牛ならぬ黒毛唐牛か?)だそうで、別の情報によりますと、戊辰戦争で江戸城開城後に新政府軍のお偉いさんが被っているフサフサは、徳川幕府が清から輸入してため込んでいたヤクの毛を接収して流用したのだそうです。
そういえば、武田信玄には白い毛の生えた兜を被っているイメージがありますな。
調べてみると、諏訪大社に伝来した「諏訪法性兜(すわほっしょうのかぶと)」で使われているのもヤクの毛のようです。

ということで、1月10日に始めた「『トーハク』では軽薄だけど、やはり東博は凄い」シリーズ、全巻の完結であります
東博では明日から文化財保護法制定60周年記念 特別展「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」が始まります。また、「本館リニューアル記念 特別公開」は終わってしまいましたが、「新春企画 博物館に初もうで」は今月いっぱい(30日まで)開催されています。
次はいつ行きましょうかねぇ…


 させることにしました。
させることにしました。

 激しく残念です
激しく残念です

 )、使い続けそうな気がしています。
)、使い続けそうな気がしています。

して、このブログを行き当たりばったりに続けて行きます。











 もかけて
もかけて (どちらもおばさま。同一人物かも…)と、ちぃと
(どちらもおばさま。同一人物かも…)と、ちぃと
 つづき:2011/01/27
つづき:2011/01/27  の
の
 を観てきました。
を観てきました。
 には理解不能な方々がほとんど
には理解不能な方々がほとんど に、
に、 に、揚げ足取りや「重箱の隅つつき」が大好きな
に、揚げ足取りや「重箱の隅つつき」が大好きな …。
…。 がわんさかでてきます。
がわんさかでてきます。 (字幕読みネ
(字幕読みネ せざるを得ない中、一服の清涼剤というか
せざるを得ない中、一服の清涼剤というか のが、
のが、
 、「
、「 を送ったり、
を送ったり、 なのが笑えます。(学長=元財務長官の
なのが笑えます。(学長=元財務長官の
 )は、
)は、
 を買ったとしても、
を買ったとしても、
 。日本ではあり得ないと思いますし、ましてや
。日本ではあり得ないと思いますし、ましてや 当然、法的な準備は万全なのでしょうけど…。
当然、法的な準備は万全なのでしょうけど…。
 、「
、「





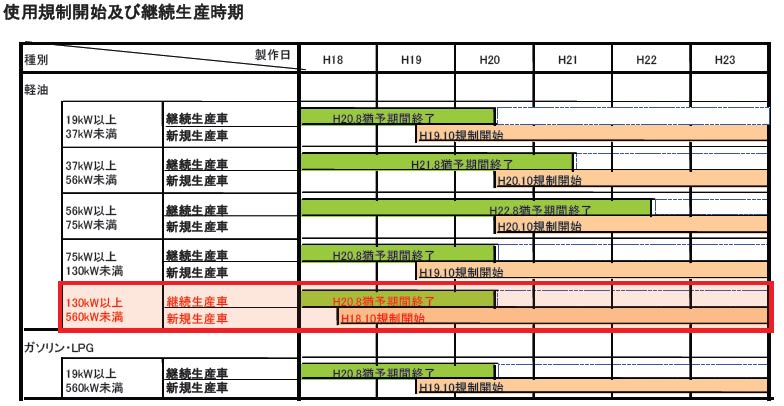

 に行くと、「
に行くと、「 「
「 が出てきました。
が出てきました。 。
。 を載せておきます
を載せておきます



 という「
という「


 なんか、まさしく「
なんか、まさしく「


 を施したら
を施したら
 が実に
が実に



 なのですが、
なのですが、
 が広がっています。
が広がっています。
 (一番シンプルかも)。
(一番シンプルかも)。

 」です
」です