 食堂にさえ・かん(冠)された、「百姓」という文字・・。
食堂にさえ・かん(冠)された、「百姓」という文字・・。
さいきん見かけない
この文字が、
 ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる
ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる
今回の旅で、
 クリンは、そのことを 知りました。
クリンは、そのことを 知りました。
 それは、このあたりが、日本有数の米どころ
それは、このあたりが、日本有数の米どころ だから、
だから、
というばかりでは
ありません。
 このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」
このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」
だったことに
かんけい(関係)しています
(今日は、長文です)
 クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と
クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と
よばれていました。
 ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます
ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます
れんにょ(かんじ:蓮如)っていう・お坊さんです 。
。
 れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の
れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の
リーダーで、
武士やきぞく(貴族)でなく、
 庶民を すくうべく、この地に やってきました
庶民を すくうべく、この地に やってきました
れんにょ(蓮如)は、
村のお百姓さんたちに
むかって
言いました。
 「
「 心から『南無阿弥陀仏』と唱えれば、必ず極楽に行けるよ。」
心から『南無阿弥陀仏』と唱えれば、必ず極楽に行けるよ。」

 戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた
戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた
人々にとって、
これは、まさに
「救いの言葉」・・
 しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく
しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく 、あたまがよく
、あたまがよく

気さくで
しんせつ(親切)な

とおとい・高そう(僧)


 百姓たちは、われさきに その手に すがりました
百姓たちは、われさきに その手に すがりました


 (←本当は このような方です。)
(←本当は このような方です。)
れんにょ(蓮如)の 布教方法は、
 おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で
おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で
書いた、きょうてん(教典)を
くばり、
 みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、
みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、
というもの。
かが(加賀)、のと(能登)、えっちゅう(越中)
と、
 れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、
れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、
こう(講)ができ、
信者のわ(輪)が
広がりました
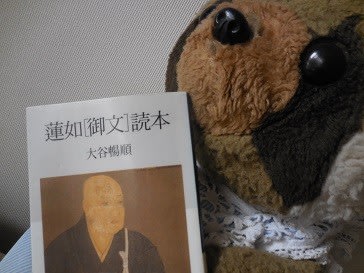 おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば
おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば
こんなことです。
 「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」
「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」
<意味>
 「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、
「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、
しっかり生きな 」
」  みたいなやつです。
みたいなやつです。
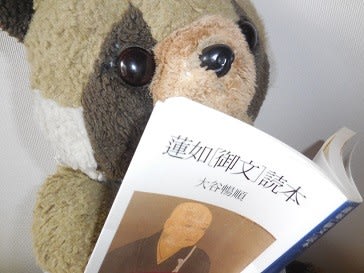 そぼく(素朴)
そぼく(素朴) にして、じゅんすい(純粋)
にして、じゅんすい(純粋) な 教えは、
な 教えは、
きびしくて
汚い世界で
生きるしかなかった
百姓の心を、
がっちり・とらえました
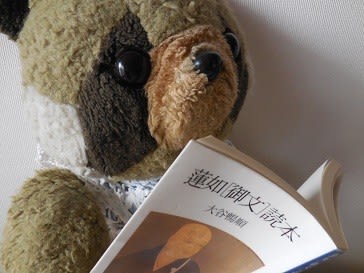 一大・ブームとなった
一大・ブームとなった 「一向宗」は、やがて
「一向宗」は、やがて
大きく
まとまりはじめ、
れんにょ(蓮如)の予想以上の
巨大せい(勢)力となって、
しだいに、けん(権)力者に ていこう(抵抗)


 信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための
信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための
いっき(一揆)を
おこしはじめます

 とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし
とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし 国をのっとる
国をのっとる
「加賀の一向一揆」
が
おこりましたが、
そのあとが、すごくて、
百姓たちは、
「ここは、一向宗の国だ
 ここには、大名なんかいらねえ
ここには、大名なんかいらねえ
 俺たちゃ、平和に暮らすぜ
俺たちゃ、平和に暮らすぜ
 」
」
と
宣言し、
 100年間の間、自分たちだけの国
100年間の間、自分たちだけの国 を、守りぬいたのです
を、守りぬいたのです


(こんなような状態→)  (赤が加賀国)
(赤が加賀国)
 戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、
戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、
おそれましたが、
 さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は つぶされて
さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は つぶされて
しまったのでした。。
が
それでも
 「
「 信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」
信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」
と
れきし(歴史)にくわしい、
うちのチットは
言ってます。
 「
「 あの、うるわしの文化都市・金沢の前身が、百姓の
あの、うるわしの文化都市・金沢の前身が、百姓の
宗教王国だなんて
めちゃ・すごすぎる 」
」
と、
チットは、かんしん(感心)しきり・・
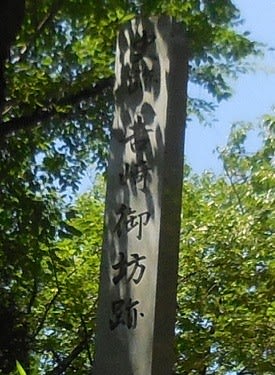 ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった
ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった
ここ
よしざき(吉崎)には、
 げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています
げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています
 「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、
「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、
 おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、
おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、
「蓮如上人・お腰掛の石」っていうのがあったり、
 その山自体が、吉崎の地形が見わたせる
その山自体が、吉崎の地形が見わたせる 「展望台」に
「展望台」に
なってますし、
 ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、
ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、
だれでも入れて、カフェもあり ・・
・・
 その向かいには、お庭あり
その向かいには、お庭あり 、
、
はくぶつかん(蓮如館)あり 、
、
 あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり
あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり 、
、
と
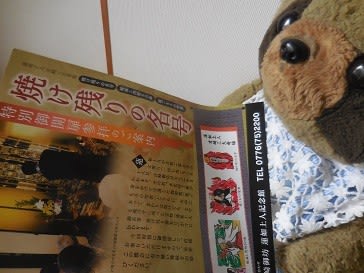 見るとこ・いっぱい
見るとこ・いっぱい

 てんじ(展示)室とかもていねいに見る人は、
てんじ(展示)室とかもていねいに見る人は、
全部あわせて
2~3時間
かくご(覚悟)したほうが いいと思います
クリンたちの
旅行初日は、
 この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、
この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、
くれていったくらいですから。
(その6、「火消しの蟹の話」につづく)














