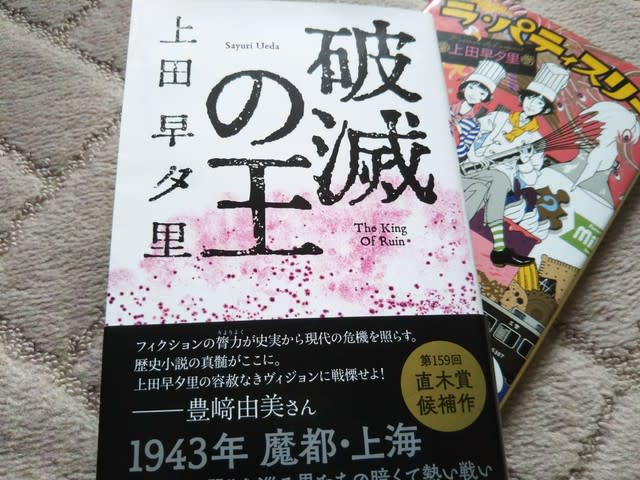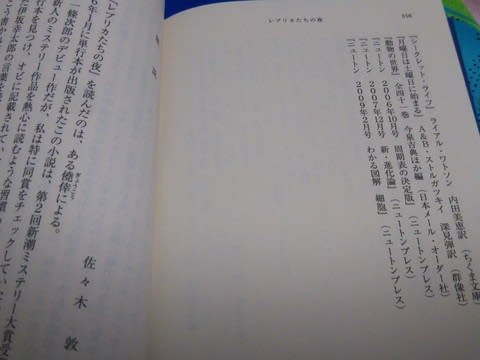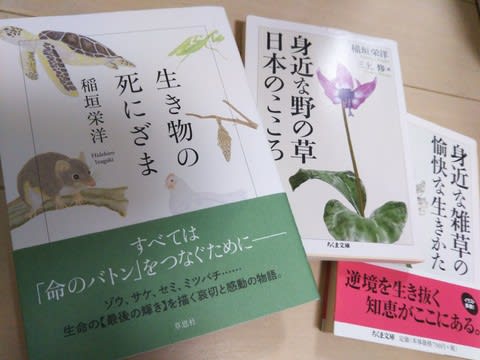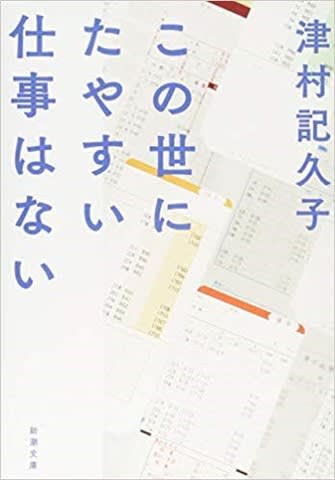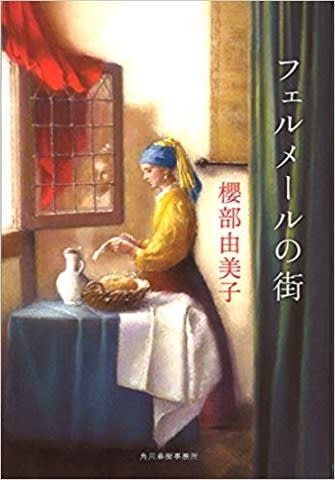梨木香歩さんの「不思議な羅針盤」を読み返していたら、椋鳩十という名がでてきて、だいぶ前に友人に教わった名前だったのを思い出した。さっそく図書館で借りてみた「鷲の唄」。
「山窩調」「鷲の唄」「夏の日抄」の3部からなり、1983年に発刊されたものだが、「山窩調」は昭和8年の作品。
山窩とは山を転々としながら暮らす無籍者。彼らの暮らしをショートストーリーで詞調につづる。

法律も何もない山の中で「生き物」として「素」で生きるのは、非情だったり残酷だったりするが、考えてみれば、今の他人との関係だったり国と国との取引も、これと大差がない。結局人間らしさなんてうわべのことで、人も生き物だということだろう。
これを読むと、今の、言葉を飾り理屈をこねた様々な本が、なんだが味気ないものにさえ思えてくるほど、後を引いた。

本を開いたら、30年前のしおりが褪せることなく折り目もなく挟まれていた。
今はカードでピッとやるだけ。返還日が書かれたレシートみたいなものを挟んでくれる。