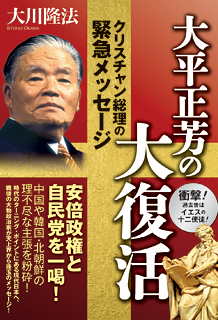花咲くも 二分咲く風の 寒さかな
梅士 Baishi
土曜日の今朝は気温6℃、晴れ、ガスストーブに火
を入れる。
昨日は朝のジョギングにもかかわらず、ストレスが
ピークに達して二時過ぎに家を出た。
料理の食材もなく、空腹だったからかもしれない。
駅を降りたが、適当な食事処もなかったので、十年、
二十年ぶりに「ほか弁」を買った。
ずいぶんと値段が上がっている。
定番のから揚げ弁当を注文して10分、揚げたての
弁当をリュックに入れて遍路に出た。
梅は終わっているはずなのに、梅のような花が泡
立つように咲いている。
桃なのか、やっぱり桜なのだろうか・・・。
久しぶりのルートは遍路道ではなく、林道である。
まだ咲きかけの桜の下で、ほか弁を開いた。
二分咲きの風が冷たい。

林道には椿が、奥山の紅一点の灯を点していた。
山の上から滝の観音に下った。
そこは、ばあさんが一人で堂守をしていると聞いて
いたが、人の気配はない。
死んだのだろうか。
細く険しい沢沿いの巡礼道には、椿が落ちて赤い
花を横たえている。
突然、バサッと鳥が飛び立った。
雉だろうか。
猪が吠えるような声が聞こえる。
猪が駆けてきたらどうしようかとあたりを見回しなが
ら沢を下って行った。
すると、チリンチリンと巡礼の鈴のような音がして、
すっと人影のようなものが横切ったように思えた。
婆さんの亡霊だろうかと、ぞっとした。
また、チリンチリンと音がする。
チリンと鳴った木の枝を見ると、風鈴がぶら下がっ
ていた。
まったくもって気味が悪いと思いながら、車道にで
たのだった。
そこの札所の桜もまだ二分咲きだった。

ファミレス文化を作った「すかいらーく」創業の理念
と苦労が語られる横川竟氏対談番組を見た。
三度、倒産の瀬戸際に立つ資金繰りのピンチがあ
ったという。
創業者の試練である。
そんな苦労を聞かない創業者もたまにはいるが、
語らないだけなのかもしれない。
サラリーマンでも資金繰りのピンチは少なくない。
だからサラ金地獄もあるのだろう。
試練を恐れていては、この世には生き甲斐がない。
不眠不休で熱中するのも、創業者に限ったことでは
ない。
何かを始めるということは、それほどに夢中になる
ということなのである。
成功していても、発展をやめたら転落が始まる。
一流の打者でも打率は三割だ。
そのとき、創業の原点が大事になる。
ささやかな安心、ささやかな発見、ささやかな希望
や称賛、そして、ささやかな交流の喜びと生き甲斐を
提供する努力が商品価値というべきか。
誉めるという要素が大切に思える。
「して見せて、言って聞かせて、させてみて、誉めて
やらねば」という、上杉鷹山や山本五十六の語録が、
消費者に対しても当てはまるのではないだろうか。
希少価値であると同時に、市場の8割を満足させる
価値を持つことがビジネス価値である。
希少価値とは、消費者の発見の喜びでもある。
それがなくなると、消費は下降線をたどる。
そうしたことが読み取れるインタヴューだった。
こうした方程式を何に当てはめるか、これが問題で
ある。
激動期の時代は、創業の時代でもあろう。
常勝思考で臨みたいものだ。
日本独立宣言・九州本部・神聖九州やまとの国
幸福実現党応援隊・中村梅士党