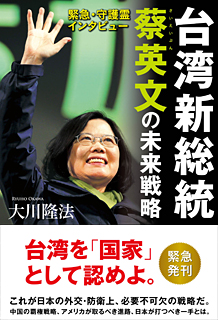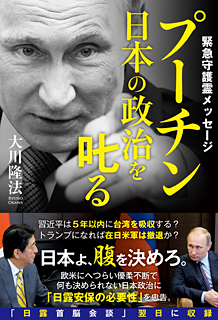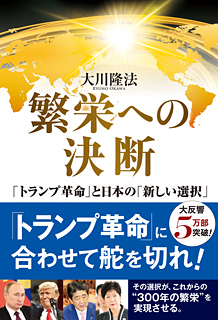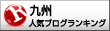花三分 人も三分か 三分雨
梅士 Baishi
今朝は11.5℃、小雨の金曜日、春三月の晦日である。
今年初めて、老母とランチに出かけた。
一度は入ってみたいと思っていた老舗の天ぷら割烹の
店までタクシーで乗り付けた。
ランチメニューは7種類に限られている。
選んだのは、天刺定食2000円だった。
さすがにネタが良くて、おいしかった。
そう、天麩羅は、ネタが新鮮で上等でなければならな
いのである。
夜の部は本領発揮だが、祝い事か接待でもなければ縁
がない。
包丁侍の仕立てという感じが良い。
櫛田神社では、桜は三分、色めき始めていた。
博多の歴史を紹介する「博多町家ふるさと館」には、
初めて観光客のように入館した。
いつも通る場所だが、入ったことはなかったのだ。

博多の歴史文化は古い。
度々戦火に焼かれている。
一番新しい戦火は、アメリカ軍のホロコースト、福岡
大空襲である。
古くは、卑弥呼の時代の出雲勢力との戦いが霊言でも
証言されている。
その時、卑弥呼の養女だった壱与が戦死している。
神功皇后の時代は、熊襲との戦で仲哀天皇が戦死した。
その後、身重の神功皇后が三韓征伐をして凱旋したが、
天智天皇の時代に出兵した百済救済軍が白村江の戦いに
敗れ、大陸からの侵略におびえた時代があった。
最も忘れがたいのは、二度にわたる元寇の役である。
その時の元の皇帝フビライハーンが、今、胡春華とし
て現代チャイナの中枢に潜んでいる。
元寇の役の決着は、まだついていない。
博多の街は、大陸貿易拠点として繁栄しながらも、度
度戦場と化して焼き討ちされ、戦国時代末期には森林と
化して人口を失っていたという。
兵どもが夢のあとである。
その後、太閤秀吉によって復興されたが、鎖国政策が
敷かれた江戸時代には貿易港としての活力は次第に衰退
に向かい、黒田の居城として地域政治・経済の拠点では
あったが、華やかさを失っていったのである。
尤も、炭鉱景気で賑わった時代があったが、原油と天
然ガスの時代になった現代では、九州の中心都市ではあ
れ、かつての精彩を失っている。
これから、新たな繁栄があるとすれば、新アジア共栄
圏の中心都市としての可能性であろう。

新アジア共栄圏の中心都市としての繁栄可能性につい
ての一考察。
まず、日本国の不況原因が払われる必要がある。
一つは、ナンチャイナやナンダコリア勢力との、技術
侵略を伴うコスト競争に負けたこととが大きい。
もう一つは、謝罪外交に代表される政治の堕落である。
三つ目は、新アジア共栄圏を創ると言う気概も使命感
もない沈滞ムードにある。
これを抜け出す民間努力としては、コストの安い優秀
な人材育成を九州拠点で行うことだ。
さらに、政治的に九州を減税特区とすることだ。
三つ目に、交通革命として、アジア地域への交通イン
フラ投資を強めることである。
活力あふれる日本にしたいものである。
そのためには、地方自治を廃止することだ。
公務員の数を激減させることである。
民間活力による立国こそが、民主主義である。
日本独立宣言・神聖九州やまとの国
New Asia Happiness Party