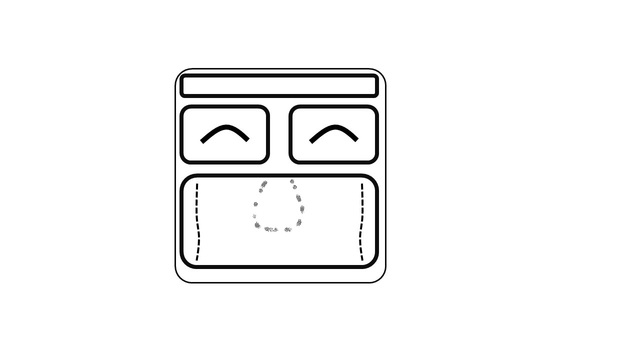生きていると、毎日何らかの決断をしている。
朝目が覚めて、布団からいつ出るか。
朝食に何を食べるか、食べないか。
車で出かけるか、自転車か、バスか。
ラーメンを頼むとき、餃子も頼むか、焼きめしはどうするか。
などなど、あまり普段決断と思っていなくても、やはり進む方向は一つ選んでいる。これくらいだとどうということないが、ぐっとつまって、「どうしよう。」と悩んで出さなければならない決断もある。決断から逃げ出すというのも一つの選択肢だが、あまり逃げ出していいことはないと感じる。ぐっと踏みとどまり、右か左か決め、決めたら進む。逃げてもいつかまたその問題がつきまとってくる。多くの場合さらに問題が複雑になって戻ってくる。
インフォームド・コンセントという言葉はほぼ市民権を得てきたような気がする。多くの場合治療方法を選択するときに、方法、危険性、他の選択肢など情報を得た上で、ある方法を納得の上で選択するという意味合いになる。つまりどの治療を受けるか、あるいはどの治療も受けないか、決断するということだ。
つらい場合もあるかもしれないが、決断から逃げ出しても問題が解決しないのは明らか。それに何らかの決断を下さないでいると、間違いなく後悔する。まがりなりにも決断すれば、多少の後悔が残ることはあっても、ある意味納得できる。
まさに、人生。
朝目が覚めて、布団からいつ出るか。
朝食に何を食べるか、食べないか。
車で出かけるか、自転車か、バスか。
ラーメンを頼むとき、餃子も頼むか、焼きめしはどうするか。
などなど、あまり普段決断と思っていなくても、やはり進む方向は一つ選んでいる。これくらいだとどうということないが、ぐっとつまって、「どうしよう。」と悩んで出さなければならない決断もある。決断から逃げ出すというのも一つの選択肢だが、あまり逃げ出していいことはないと感じる。ぐっと踏みとどまり、右か左か決め、決めたら進む。逃げてもいつかまたその問題がつきまとってくる。多くの場合さらに問題が複雑になって戻ってくる。
インフォームド・コンセントという言葉はほぼ市民権を得てきたような気がする。多くの場合治療方法を選択するときに、方法、危険性、他の選択肢など情報を得た上で、ある方法を納得の上で選択するという意味合いになる。つまりどの治療を受けるか、あるいはどの治療も受けないか、決断するということだ。
つらい場合もあるかもしれないが、決断から逃げ出しても問題が解決しないのは明らか。それに何らかの決断を下さないでいると、間違いなく後悔する。まがりなりにも決断すれば、多少の後悔が残ることはあっても、ある意味納得できる。
まさに、人生。