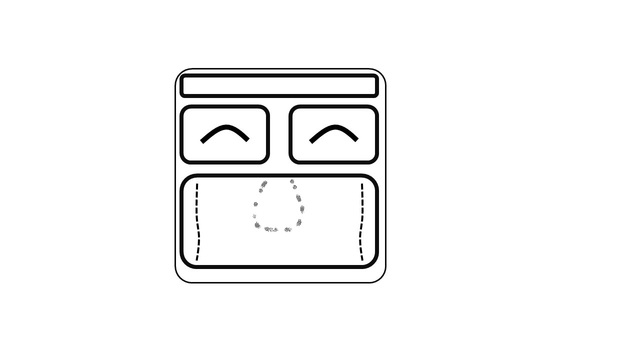米国スタンフォード大学の生物学教授が、先進国の寿命は2030年頃までに100歳になるとの予測を示したそうです。
悪性腫瘍に対する治療やアンチ・エージングに対する研究が現在のペースで進めば、そうなるとの予測です。
このような先進医療の恩恵を受けることができる国は、いわゆる先進国であり、命においても南北格差が出てくる可能性が高いようです。日本は、先進国に入るのでしょうが、福祉や医療に対するセーフティーネットがどんどん縮小している現在の政策では、国内においても命の格差は広がっていくような気がします。また、日本は先進国の中で唯一HIV感染が広がっている国といわれており、これも寿命に影響しそうです。
逆に、先進国での問題は肥満をはじめとする、生活習慣病です。この悪化により先進国での寿命が短縮するとの予測もあるようです。どちらにしても、人は皆死んでいくわけですが。
病気もさることながら、国民の寿命を大きくかえる因子として戦争があります。日本も戦争中は多くの若者が命を落とし、平均寿命は下がったはずです。米国の寿命が延びても、イラクの寿命は短くなっていると思いませんか。
多くのお金をつぎ込み、病気と闘い寿命を延ばす。
多くのお金をつぎ込み、相手を押さえ込み、相手の寿命を縮める。
皮肉なお金の使い方。
悪性腫瘍に対する治療やアンチ・エージングに対する研究が現在のペースで進めば、そうなるとの予測です。
このような先進医療の恩恵を受けることができる国は、いわゆる先進国であり、命においても南北格差が出てくる可能性が高いようです。日本は、先進国に入るのでしょうが、福祉や医療に対するセーフティーネットがどんどん縮小している現在の政策では、国内においても命の格差は広がっていくような気がします。また、日本は先進国の中で唯一HIV感染が広がっている国といわれており、これも寿命に影響しそうです。
逆に、先進国での問題は肥満をはじめとする、生活習慣病です。この悪化により先進国での寿命が短縮するとの予測もあるようです。どちらにしても、人は皆死んでいくわけですが。
病気もさることながら、国民の寿命を大きくかえる因子として戦争があります。日本も戦争中は多くの若者が命を落とし、平均寿命は下がったはずです。米国の寿命が延びても、イラクの寿命は短くなっていると思いませんか。
多くのお金をつぎ込み、病気と闘い寿命を延ばす。
多くのお金をつぎ込み、相手を押さえ込み、相手の寿命を縮める。
皮肉なお金の使い方。