岐阜の友人と久しぶりに会おう、ということになり、新幹線の東京-名古屋の中間点、静岡で会うことにしました。
駿府城は、静岡駅から歩いて15分ぐらいのところにあります。
周りを掘に囲まれ、広い庭園もあって、美しいスポットです。

なんでも、徳川家康公が隠居して住んでいた場所だとか。
隣接した「駿府公園」はとても広くて、静かな日本庭園が美しく、東京の新宿御苑に似た佇まいです。
中ほどに「お茶室」があって、見学できるように公開されています。
本式のお茶会ができる広間、そしてにじり口のついた「小間」もあります。
お茶室を出ると 小さな茶屋も作られていて、お茶とお菓子のセットをいただくことができます。
玉露セット、煎茶セット、抹茶セットがあったので、私たちは「抹茶セット」を頼みました。
水屋で立てられたお茶と 秋の風情を写した練り切りのお菓子が、しずしずと運ばれてきて、しっとりとした和の気分に浸ることができました。

駿府城は、静岡駅から歩いて15分ぐらいのところにあります。
周りを掘に囲まれ、広い庭園もあって、美しいスポットです。

なんでも、徳川家康公が隠居して住んでいた場所だとか。
隣接した「駿府公園」はとても広くて、静かな日本庭園が美しく、東京の新宿御苑に似た佇まいです。
中ほどに「お茶室」があって、見学できるように公開されています。
本式のお茶会ができる広間、そしてにじり口のついた「小間」もあります。
お茶室を出ると 小さな茶屋も作られていて、お茶とお菓子のセットをいただくことができます。
玉露セット、煎茶セット、抹茶セットがあったので、私たちは「抹茶セット」を頼みました。
水屋で立てられたお茶と 秋の風情を写した練り切りのお菓子が、しずしずと運ばれてきて、しっとりとした和の気分に浸ることができました。













 」
」






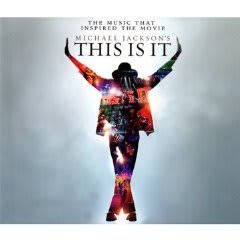







 )
) 」
」
 ・・・そういう風景での音楽よ。p(ピアノ)の部分は、小さかったモーツァルトやマリー・アントワネットの姿を想像したらどうかな。宮廷にだって、子どもはいただろうし。f(フォルテ)の部分は、堂々とした王様。少し高くなった音のところは、美しい妃・・・とかさ」
・・・そういう風景での音楽よ。p(ピアノ)の部分は、小さかったモーツァルトやマリー・アントワネットの姿を想像したらどうかな。宮廷にだって、子どもはいただろうし。f(フォルテ)の部分は、堂々とした王様。少し高くなった音のところは、美しい妃・・・とかさ」