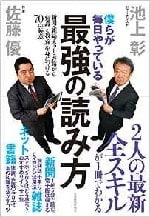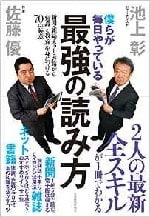「特別付録1 「「人から情報を得る」7つの極意」の以下、要旨、承前。
(4)人の話を聞くときは「緩やかな演繹法」でのぞむ
取材に行く前には、当然いろいろ下調べをして、「この場所でこの人と会うなら、こういう話を聞けるだろうな」というストーリーは事前にざっくりと描いてから行く。しかし、そこで大切なのは、「自分で事前につくったストーリーに縛られないこと」だ。実際に取材に行けば、予想外の新しい発見があるものなので。
そもそも、新しい情報を求めて取材に行くわけだから。
とはいえ、予想外の展開を活かせるかどうかは、その人次第という側面もある。なかには、いくら面白い意外な話が出てきても、最初のストーリーを崩したがらない人もいる。その一方で、最初のストーリーに固執せず、臨機応変に新しいストーリーを描いていける人もいる。
有能な人はそういう判断が早いのだろう。
これはビジネスパーソンにも同じことが言える。市場リサーチにしても聞き取り調査にしても、きっちり下調べをしたうえで、いかにそれを崩せるか。これを「緩やかな演繹法」と池上彰は呼ぶ。
あらかじめ考えた仮説にしたがって内容をまとめるのが「演繹法」だが、「緩やかな演繹法」とはいい表現だ。
調査した内容をもとにストーリーを組み立てる「帰納法」のように、現場主義的なやり方がいいわけではない。何かしらの問題意識があって行くわけなので、事前に仮説は立てなくてはならない。時間も無限ではないから。
しかし、無理に仮説に当てはめる本当の演繹法になったらつまらない。
仮説を立てる演繹法でスタートし、調査の結果によってそれを修正する帰納法で展開していくイメージだ。途中で話があらぬ方向に行ったとしても、焦らずに、むしろ「自分がこの現場に来たからこそ、聞き出せた話だ」と喜ぶくらいがちょうどいい。
(5)複数の「しゃべる人」の断片情報をつなぎ合わせる
人から情報を聞き出すうえで重要なのは、①「その人が情報をもっているかどうか」、そして②「話してくれる人かどうか」だ。「情報をもっていない人」にいくら当たっても意味がない。「話してくれない人」をいくら攻めても効果が乏しい。情報を得る側としては、まず①「情報をもっていて」かつ②「話してくれそうな人」を見つけることだ。
そして、その人が話しやすいタイミングを狙っていくのもポイントだ。そのとき、自分が知りたい内容を、少しずつ複数の相手から聞き出し、断片的な情報をつなぎ合わせる手法も覚えておくといい。ひとりからすべてを聞き出そうとすると、無理や偏りが出やすいし、誰だって自分に都合の悪いことは話してくれないから。そこで多方面から情報を一つひとつ聞き出し、その断片情報をつなぎ合わせていく。
情報が少なすぎると、情報が間違っている場合に気づきにくいという問題もある。複数の人から話を聞き出すときのコツは、人間は「自分の組織の話はしなくてもほかの組織の話はする」という鉄則を忘れないことだ。
警察署の交換手が、自分の管外の動きを「隣の管内の警察無線がうるさいわよ」と教えてくれるとか。警視庁捜査1課4係が担当する仕事を4係に取材しても教えてくれないが、5係の刑事に尋ねると、「そういえば、最近、係長がどこそこに呼ばれているらしいな」と噂話をしてくれるとか。その人は別にネタを漏らしている意識はないのだが、そこで「ははーん」と予測が立つわけだ。
ある記者いわく、「捜査1課、2課の情報は3課からとるんだ。1課は殺人などの凶悪犯罪、2課じゃ企業犯罪、3課は窃盗が担当。よく大きな事件を扱う1課、2課は普段から記者も接待モードだが、3課はそうじゃない。だが、応援で1課や2課には頻繁に行くので、情報はもっているのだ。
ビジネスに応用できる。社内でも取引先でも、自分のプロジェクトについては言わなくても、隣のプロジェクトについては、比較的気軽にしゃべってくれるものだ。
(6)セミナー、講演会、異業種交流会を上手に活用する
書籍ばかり読んでいる人には、勉強会や読書会、セミナーや会食に参加することをもっとすすめたい。その一方で、異業種交流会やセミナーの渡り鳥みたいになっている人には、もっと本を読んでほしい。このバランスがとれている人は、残念ながらあまりいない。
セミナーや講演会は、情報収集の効率としてはあまりよくない。90分の講演会を聞いても、情報量としては書籍1冊の何分の一だから。ただし、高い受講料を払って志を同じくする人があつまるので、意欲は高まる。実際に講師に会ってみることでわかることも、もちろんある。
いまひとつ面白くなかった場合でも、反面教師として参考になる。
当たり前のことだが、「書籍から得られる情報」と「人から得られる情報」のどちらも重要なので、一方に偏りすぎないことだ。最近は、新聞記者でも記者クラブにこもってネットだけで情報収集している人が増えている。新人時代は取材先の人脈を増やすことが何より大事だ。新鮮なネタは、自分の足を使わなければ手に入らない。
外交官の業界には「カクテルサーキット」という言葉がある。カクテルパーティに参加して、名刺を集めて、とにかく顔を売り込むことだ。そういう場所でいい情報が得られる可能性は実際にはほとんどないが、それでも人脈というのは、特に若いうちはあるに越したことはない。
人脈には、「種をまく時期」と「収穫期」の2段階がある。若いうちは、とにかく、いろんな場所に顔を出して「種」をまき、ある程度人脈が広がったら、今度はそんな効率が悪いことは続けずに、「収穫期」に入ります。〈例〉自動車のセールスマンで全国1位になるような人は、一定の年齢になると自分から積極的な新規開拓はしない。むろん、新人のころは必死にあちこちに飛び込み営業をして、まったく相手にされないことも多い。でも、買ってくれた人のアフターフォローをずっと続けて信頼を得ると、車検も任せてもらえて、別のお客さんも紹介してくれるようになる。
あらゆる業種に共通することだ。
目安としては、とにかく20代のうちはひたすら人脈を広げ、30代半ばからは収穫期に入れるようにしたい。
そこで収穫期に入れない人は、別のスタイルを見つけることだ。組織で上位に上がっていけるのは、せいぜい2割にすぎない。
(7)飲み会で仕入れた情報は、翌日「知らないふり」をする
新人時代は少し我慢をしてでも、時には上司や先輩と一緒に飲みに行くといい。自分は酒を飲まなくてもいいから。
やはり人間関係を円滑にするうえで最低限のコミュニケーションは必要だから。〈例〉歓送迎会や仕事の打ち上げなどの「大事な飲み会」にはきちんと参加して、それ以外の「普段の飲み会」には参加しないなどとスタイルを決めてしまうと楽だ。
どうしても付き合いが必要な場合は、一次会には参加しても二次会には付き合わないという方法もある。
時間は有限で、目的もなく誰かと話すより、本を1冊読んだほうがいいことも多いから。(6)のセミナーや講演会と同じで、いつも読書ばかりしている人にはもう少し飲み会に参加することをすすめたいし、連日飲み歩いているような人には読書する時間をしっかりつくってほしい。どちらか一方に偏るのはよくない。
職場の飲み会では、上司や先輩の武勇伝や過去の自慢話にうんざりすることもあるが、それを通してそのころの時代の動きもわかるし、ベテランならではの裏ワザや、何かが起きたときに社内外でどう対処すればいいかなど、学ぶことは実はたくさんある。
「時間が経ったいまだからこそ話せる」ということもあるし。
もし何度も同じ話を聞かされるようになれば、その人と飲みに行く回数を減らせばいい。ただし、そんなときでも「その話は何度も聞きました」なんてバカ正直に言ったりせず、あくまで可愛い部下として距離を置くことだ。
「初々しさ」がここでも大事になる。飲んだときの話が重要なのは、酒を飲むと誰でも口が軽くなるからだ。「自分にとって不都合な情報の99.9%は、じつは自分の口から出ている」。人間は秘密を暴露したい動物なのだ。別に話さなくてもいいはずなのに、それでも話してしまう。よくオフレコ情報で「ここだけの話だけど・・・・」などというのは、事実上は「私が話したことがわからなければ、使ってもいいよ」ということだ。
厳密なオフレコではないということだ。つまり、飲み会は「他人の貴重な情報」を聞き出す絶好の場であると同時に、「自分の不都合な情報」をつい漏らしてしまいかねない場でもある。諸刃の剣だ。
「酒の席で得た情報」で大切なのは、「飲み会の翌日、本人に確認してはダメ」ということだ。警戒心を抱かれてガードが固くなり、次の飲み会に呼ばれなくなる。素知らぬふりでいつもどおりに接しつつ、ほかの人から裏付けをとるのがコツだ。
「あいつは無粋なやつだ。用心しなくては」と思われると、入ってくる情報も入ってこなくなる。
あとは、仮に相手が酩酊して醜態をさらしても、決して非難しないことだ。もし相手に何か聞かれても、「いや、問題なかたよ。愉快な酒だった」と答えるのだ。
相手の脇の甘さや口の軽さを指摘すると、結局、情報を聞き出せなくなり、自分が損をする。
情報うんぬんを抜きにしても、食事を共にする行為は信頼関係を深める重要な時間だ。書籍やネットの情報ばかりに偏って人と会わないと、精神的なバランスがとれなくなってしまう。ほどほどの息抜きは必要だから。だからといって、食事をする相手は誰でもいいというわけではない。それに、つるみたがる人は、往々にして、先に行こうとする人の足を引っ張ることもある。
□池上 彰×佐藤優『僕らが毎日やっている最強の読み方―新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける77の極意』(東洋経済新聞社、2016)
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「
【佐藤優】「人から情報を得る」7つの極意(1) ~最強の読み方(7)~」
「
【佐藤優】ネット利用の3大原則 ~最強の読み方(6)~」
「
【佐藤優】ネットの使い方、情報の新しさを判断する目安 ~最強の読み方(5)~」
「
【佐藤優】雑誌の読み方、『失敗の本質』 ~最強の読み方(4)~」
「
【佐藤優】雑誌の読み方、「文藝春秋」は論壇カタログ ~最強の読み方(3)~」
「
【佐藤優】新聞の読み方 ~最強の読み方(2)~」
「
【佐藤優】新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける77の極意 ~最強の読み方~」