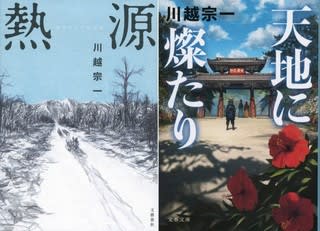北海道新聞 07/02 05:00
12日に開業するアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴空間(ウポポイ)」(胆振管内白老町)で、「年間入場者100万人」の目標達成と、新型コロナウイルス感染対策の両立に政府が頭を悩ませている。当面は事前ネット予約制として入場者を制限する考えだが、少しでも来場者を増やすため、予約制と知らず会場を訪れた客に当日券を販売することも検討。矛盾ともとれる対応に、100万人の目標は現実的ではない、との指摘が出ている。
政府は2015年10月に、ウポポイの年間入場者100万人の目標を決定。新型コロナの収束が一向に見通せない現状でも、入場目標を変更していない。
政府は感染対策として、消毒や検温に加え、「密」の状態を避けようと、入場者数を制限。日付指定の前売り券をネットで購入してもらう。混雑時に園内の各施設に入る場合は整理券も配り、入場者を通常の5割以下に減らす方向だ。
白老町の戸田安彦町長は予約制について「町民が来場客を安心して迎えるために重要」と評価し、熊谷威二・町商工会長は「経済活性化のため多く客に来てもらいたいが、不安もある」と明かす。
関係者によると、1日の入場者数の目標は平日約3千人、土日約5千人としていたが、それぞれ当面は、大幅に下方修正する。ただ、年間100万人は掲げ続け、政府は入場者を午前と午後の2回に分けるなど、効率的に受け入れる方法を検討。会場を直接訪れた客も混雑していなければ入場できるようにすることも模索する。
所管の国土交通省からは「年間100万人はもともと無理な数字。コロナ禍の中で頑張って達成する状況でもない」(幹部)との声が上がる。新潟大医学部の斎藤玲子教授(公衆衛生学)は「首都圏からの観光客がリスクになるため、大きな目標を掲げて都道府県をまたぐ移動を促す政策は控えるべきだ」と指摘する。(長谷川紳二、斎藤佑樹)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/436452
12日に開業するアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴空間(ウポポイ)」(胆振管内白老町)で、「年間入場者100万人」の目標達成と、新型コロナウイルス感染対策の両立に政府が頭を悩ませている。当面は事前ネット予約制として入場者を制限する考えだが、少しでも来場者を増やすため、予約制と知らず会場を訪れた客に当日券を販売することも検討。矛盾ともとれる対応に、100万人の目標は現実的ではない、との指摘が出ている。
政府は2015年10月に、ウポポイの年間入場者100万人の目標を決定。新型コロナの収束が一向に見通せない現状でも、入場目標を変更していない。
政府は感染対策として、消毒や検温に加え、「密」の状態を避けようと、入場者数を制限。日付指定の前売り券をネットで購入してもらう。混雑時に園内の各施設に入る場合は整理券も配り、入場者を通常の5割以下に減らす方向だ。
白老町の戸田安彦町長は予約制について「町民が来場客を安心して迎えるために重要」と評価し、熊谷威二・町商工会長は「経済活性化のため多く客に来てもらいたいが、不安もある」と明かす。
関係者によると、1日の入場者数の目標は平日約3千人、土日約5千人としていたが、それぞれ当面は、大幅に下方修正する。ただ、年間100万人は掲げ続け、政府は入場者を午前と午後の2回に分けるなど、効率的に受け入れる方法を検討。会場を直接訪れた客も混雑していなければ入場できるようにすることも模索する。
所管の国土交通省からは「年間100万人はもともと無理な数字。コロナ禍の中で頑張って達成する状況でもない」(幹部)との声が上がる。新潟大医学部の斎藤玲子教授(公衆衛生学)は「首都圏からの観光客がリスクになるため、大きな目標を掲げて都道府県をまたぐ移動を促す政策は控えるべきだ」と指摘する。(長谷川紳二、斎藤佑樹)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/436452












 ジョン・ウェインはハリウッドのタカ派だった(C)AF Archive/Mary Evans Picture Library/共同通信イメージズ
ジョン・ウェインはハリウッドのタカ派だった(C)AF Archive/Mary Evans Picture Library/共同通信イメージズ