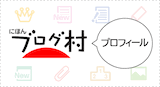雪囲い用の板を取り出してみたら トックリバチ の巣が着いていた。
3個まとまってついている徳利はまだフタが開いていない。
中には何が入っているんだろう・・・・餌と卵か幼虫 蛹 それとも成虫か。
割ってみると 餌を食べつくした幼虫が入っていた。これから蛹化するのだろう。
大きさはこれくらい。
球形の外観だが内部は球形ではなく くぼみのある細長い部屋になっている。
くぼみの部分には 黒い何かが残っている。
3個とも割ってみた。
幼虫の姿勢はまちまちだが くぼみの位置は同じ方向に作られていた。
板は立てて保管していた。くぼみは部屋の下側に作られた 幼虫のためのトイレではないだろうか。
以前に見つけた トックリバチ の巣も垂直の面に作られていた。
トイレの為にはその方が好条件なのだろう。
この板を使うと幼虫には気の毒だが巣はどうしても壊れてしまう。
雪囲いにはどうしても必要な板だからやむを得ない。3匹の幼虫は池の鯉に食べさせた。
80cmの大きな真鯉が4cmも大きな口を開けて小さな幼虫を飲み込んだ。
夜半に雨の音が止んで 障子が少し明るくなった。
月は明るいはずだから 雲が薄くなってきたらしい・・・・。
雪囲いの作業手順などを考えながらまた眠りに着いた。
朝になって障子を開けて見ると2cm程雪が積もっていた。
夜半の雨は 止んだのではなく 雪に変って音が消えたんだった。
田んぼでは 落穂が見えなくなって スズメ たちが戸惑っている。
勤労感謝の日だから工事現場はお休みらしい。
ツワブキ の花はもっともっと遅くなってから咲くものだと思っていた。
常春の島という 八丈島 でお正月に咲いていたから その頃が花期だと思っていた。
その ツワブキ が棚場ではちょうど見ごろになっている。
八丈島 とは違う魚沼の低温が開花を速めているのだろうか。
特徴のある実を着ける ヤシャビシャク の自生品は見つけにくい植物だ。
ブナ の大木にできた うろ が生息場所だから。
棚場で紅葉している ヤシャビシャク も雪の上の風倒木に着いていたものだ。
倒れていなかったら 絡みついていた イワガラミ に隠れて見つけられなかっただろう。
この実の中には小さな種子が詰まっている。
蒔くとかなりの発芽率で芽を出し その後の生育も順調に進む。
3・4年すると開花結実するから育てやすい樹といえるだろう。
飛び込みで芽生えた ユキヤナギ の紅葉が始まった。
この鉢の本来の主は オオミスミソウ なんだが姿を消してしまった。
来春には ひょっこりと花を咲かせるかもしれないが 今のところは行方不明。
先日 生け花 の展覧会を見せてもらった。
見事に紅葉した ユキヤナギ が生けられた作品に出会えた。
立ち止まって眺めていたら 花屋さんが スプレーですよ と教えてくれた。
jokichi の棚場の ユキヤナギ はスプレーではありません。