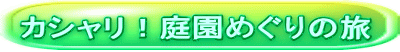【カシャリ!庭園めぐりの旅】11-hakodate02 北海道 函館公園2 園内散策
若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間か、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。
日本には「日本庭園」と呼ばれる庭園だけではなく、「イングリッシュガーデン」など、海外の庭園形式をした庭園も多数あります。寺社を訪れたときに、想定していなかったところに、庭園を発見することがあります。
下手の横好きで、【カシャリ! ひとり旅】を続けていますが、その一環で訪れた庭園を順次紹介してまいりたいと思います。
| 名所旧跡 グロマコン 経営コンサルタントへの道 仏教 仏像 |
北海道・函館 函館公園 2 園内散策
■ 函館公園 はこだてこうえん
豊かな草木に覆われた函館山のふもとにある函館公園は、日本で最も早い時期に設置された都市公園のひとつです。今も当時の姿をとどめる貴重な存在で、国登録文化財の登録記念物(名勝地)に指定されています。
「病人に病院が必要なように、健康な人間には休養する場所が必要」と、当時の函館駐在の英国領事リチャード・ユースデンが提言しました。それを受けて、市内の実業家4人が中心となって寄付金を集め、市民も全面的に協力し、着工から1年7カ月を経て、1879(明治12)年に開園しました。
ミニ遊園地や動物飼育施設もあり、春は花見、秋は紅葉狩り、夏は噴水広場で水遊びをする家族連れでにぎわいます。
函館公園が、桜の名所としても知られるようになったのは、1889(明治22)年から5年にわたって、地元の商人・逸見小右衛門が、函館公園を奈良県の吉野山のようにしたいという願いに始まります。
逸見自らの手でサクラとウメの木5280本を植栽、昭和初期までの大火でその樹木のほとんどが焼失しましたが、現在はソメイヨシノを中心に約400本のサクラの木が植えられています。
園内は起伏があるため、高低それぞれの視点から花を楽しめるのが魅力です。桜のシーズンには夜間に電飾が施され、露店も立ち並んで、花見客でにぎわいます。
秋にはサクラをはじめ、ツツジ、カエデなどが美しく紅葉し、色づく函館山との取り合わせも好評です。
園内には、噴水広場、博物館、ミニ遊園地「こどものくに」(乗り物系遊戯施設)、動物飼育施設などがあり、歴史的な建造物や碑も多いので、ゆっくりと散策したり、家族づれで楽しんだりすることができます。
公園内散策
奥に函館公園の遊園地がみえます
桜祭りの準備が始まっていました
奥に藤棚があります
藤棚下のせせらぎ
北海道 函館公園1 函館公園とは
| ◆ | 北海道・函館1 函館山 |
| ◆ | 北海道・函館2 函館ドックエリア |
| ◆ | 北海道・函館3 函館元町エリア・旧イギリス領事館・旧箱館奉行所跡 |
| ◆ | 北海道・函館4 函館元町公園・旧市庁舎・旧書庫 |
| ◆ | 北海道・函館5 函館元町公園・教会地区 |
| ◆ | 北海道・函館6 五稜郭・五稜郭タワー |
| ◆ | 北海道・函館7 函館 トラピスチヌ修道院 |
| ◆ | 北海道・函館8 湯の川温泉 <準備中> |
| ◆ | 北海道・函館9 大森浜・啄木小公園・石川啄木一族の墓 |
| ◆ | 北海道・函館10 立待岬 |
■ カシャリ! ひとり旅
- 【カシャリ!ひとり旅】 北海道
- 【カシャリ!ひとり旅】 宮城県
- 【カシャリ!ひとり旅】 山形県
- 【カシャリ!ひとり旅】 福島
- 【カシャリ!ひとり旅】 群馬県
- 【カシャリ!ひとり旅】 埼玉
- 【カシャリ!ひとり旅】 茨城
- 【カシャリ!ひとり旅】 東京散歩
- 【カシャリ!ひとり旅】 神奈川県
- 【カシャリ!ひとり旅】 山梨県
- 【カシャリ!ひとり旅】 静岡県
- 【カシャリ!ひとり旅】 京都
- 【カシャリ!ひとり旅】 兵庫
- 【カシャリ!ひとり旅】 北陸
- 【カシャリ!ひとり旅】 九州1 福岡
| ◆ | 北海道・函館1 函館山 |
| ◆ | 北海道・函館2 函館ドックエリア |
| ◆ | 北海道・函館3 函館元町エリア・旧イギリス領事館・旧箱館奉行所跡 |
| ◆ | 北海道・函館4 函館元町公園・旧市庁舎・旧書庫 |
| ◆ | 北海道・函館5 函館元町公園・教会地区 |
| ◆ | 北海道・函館6 五稜郭・五稜郭タワー |
| ◆ | 北海道・函館7 函館 トラピスチヌ修道院 |
| ◆ | 北海道・函館8 湯の川温泉 <準備中> |
| ◆ | 北海道・函館9 大森浜・啄木小公園・石川啄木一族の墓 |
| ◆ | 北海道・函館10 立待岬 |
■ カシャリ! ひとり旅