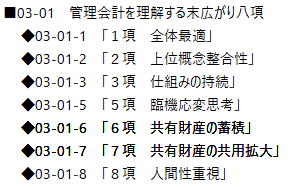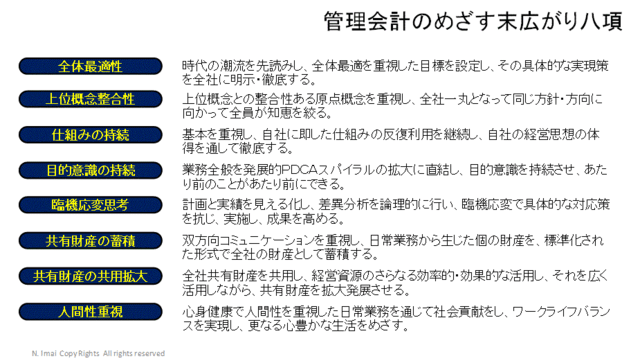■■【連載 経営トップ15訓】 第9訓 「従来の延長線上での発想や先入観に固執せず、建設的なプラス思考で取り組む」
 |
|
経営トップ15訓 ”当たり前”が実行できる
経営コンサルタント歴25年を経過した時点で、(特)日本経営士協会の理事長を拝命することになりました。その際に、自分自身を戒める意味で「理事長十戒」を作り、それを日々座右におきながら仕事をしてきました。 私の経営に対する考え方の基本は「当たり前のことが当たり前にできる」「暖かい管理ができる」、その様な企業作りのお手伝いをしています。 理事長歴も長くなり、そろそろ後任の選定やその人への傾斜引き継ぎを考える時期といえましょう。この十戒に加筆をして、企業や組織のトップ・管理職の方々に向けて焼き直したものを「トップ15訓」としてまとめてみました。経営トップの皆さんだけではなく、私自身にも必要なことなので「社員」という言葉と共に「会員」という言葉も使っています。 まだまだ内容的には不充分ですが、今後もこれをベースに推敲・改訂を重ねて参りますが、その第一版として茲にご披露させていただきます。トップの方々や管理職で日夜ご奮闘されている方に、少しでもご参考になれば幸いです。 |


| 第 9 訓 従来の延長線上での発想や 先入観に固執せず、 建設的なプラス思考で取り組む |
||||
| ■ 人間は本能的に保守的 どれ程革新的な人でも、現状の全てを変革しようとは考えていないでしょう。そこに落とし穴があって、従来の延長線上での発想となってしまいかねません。 経営コンサルタントとしてクライアントを訪問した折に、「あれ、この人は変なやり方をしているな」「なぜ、この人はこの業務をやっているのだろうか?」と奇異に感じることがあります。 それを問うと「これまで、このやり方で問題が起こったことがなかったから・・・」「先輩がやっていたので、そのまま引き継いでいます」という回答が返ってくることが多いのです。 また、私どもは先入観に固執するところがあるように思えます。「あの人は、○○大学を出ているので、あの人がやっていることは間違いなかろう」と考えて、その人の行動をチェックしないことがあります。 文書を書いた後、読み直し、訂正をした後で、再度確認をしているときに、それにもかかわらず変換ミスを見落としたり、誤字脱字に気がつかなかったりすることがあります。 「人間はミスを犯す動物である」ということを忘れてしまうと、部下が同じミスを繰り返したときに「何度同じミスをやるのだ」とついつい叱責をしてしまいます。 「人間はミスを犯す動物である」と諦めてはならないのです。現状を肯定してばかりいると、人間は進歩から見捨てられてしまいます。 同じミスを再び起こさないために、方法論を変えたり、チェック方法を改善したりと、いろいろな方策をとってもミスは起こりがちです。単純ミスほど、そこから脱することが難しいです。また、単純ミスほどチック方法が限定されてしまいます。 それは同じ思考回路でチックをするからです。企業においては、製造部門と検査部門とを別にするのは、思考回路が異なる人の目を通すことにより単純ミスの発生を防ごうとするからです。 ■ 「新幹線理論」で自分を見る 他の人や他の部署の意見を聞くなど、従来とは異なることをやることにより、気づきがあるでしょう。独善的な人は、同じミスのスパイラルの中にいて、それすら気がつかないことが多いのです。 これを「新幹線理論」と言います。 新幹線に乗ると、始めはその速さに驚きますが、やがて時間が経過して、車内で本を読んでいたり、パソコンに向かったりしているうちに自分が拘束で移動していることを忘れてしまいます。 登りと下りの列車が交差するときに、車窓を走る相手の列車を見て初めて、自分が拘束移動環境にいることを再認識させられるのです。 日常生活や業務上に於いても、気づきを得る契機をたくさん持つことが必要でしょう。例えば、講演会やセミナーに出席してみるのも良いでしょう。それらは「知識や情報の収集」と考えている人が多いかと思いますが、セミナー内容の大半は、どこかで聞いたことがあることが多いでしょう。 「つまらなかった」と言ってそれを結論にするのは「マイナス思考」です。 それでがっかりするのではなく、話の中から自分が新たな行動を起こす契機を見いだせるように意識して耳を傾けると、セミナーに参加した意義を見いだすことができるのです。 自分がマイナス思考をしているということは意外と気づかないものです。それどころか、「自分はマイナス思考する人間ではない」とい込んでいる人ほど、マイナス思考をしていることが多いのです。マイナス思考だと思って、自分自身がマイナス思考をしていないかどうかを鑑みる契機を捨ててしまっているのです。 過去からの延長線上でものを考えたり、マイナス思考をしていないのかどうか、常に自分自身に問いかけることが必要です。 |