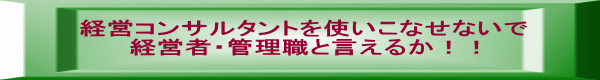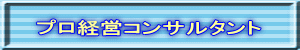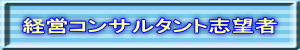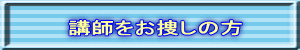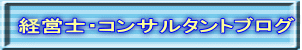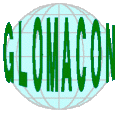■■【経済の読み方】何が起こった2016年5月を時系列に見る

世の中の動向は、アラカルト的に見ることも大切ですが、時系列的に見ると、また異なった面が見えてきます。
ここでは、これまでブログ掲載してきました内容を、月単位に、コンパクトにまとめてご紹介します。
※ 月により文字数が多くなりますと、分割掲載することがあります。

◆ 今週一週間を見るポイント 2016/05/30
G7が無事終了し、関係者はホッとされていると思います。しかし、テロというのはいつ、どこで起こるか解りません。G7厳戒態勢が緩んだところで発生することも懸念されます。引き続きその視点を持った軽快が必要だと思います。
安倍さんが消費税増税時期の延期を発表、その理由がリーマンショックという言葉を使い、しかもG7の”虎の威”を借りるようなやり方で顰蹙を買っています。G7首脳だけではなく、全世界、全国民が唖然とした唐突さを感じます。私は反自民を標榜しているわけではありませんが、選挙を視野に入れての国内向け発言と解してもらえるとは思いますが、日本のトップがこのような有様で、恥ずかしくなってしまいます。
今週は、世界経済フォーラム東南アジア諸国連合(ASEAN)会議がクアラルンプールで開催されます。参加国の対中対策が、何処まで足並みがそろうか、懸念が強く感じられます。
アメリカではベージュブックや雇用統計が発表されますし、ヨーロッパではECB定例理事会が開催されます。
国内でも雇用や労働力関連の数値が発表されます。経団連の定時総会後の発表も気になります。
5月29日(日)
※ 現在、手元にご紹介する情報がなく、ご不便をおかけします。
5月30日(月)
国際:中東和平協議促す国際会議
日本:商業動態統計(経産省)
5月31日(火)
日本:鉱工業生産・出荷・在庫指数速報(経産省)、労働力調査(総務省)、家計調査・有効求人倍率(厚労省)、住宅着工統計(国交省)
米国:個人所得・消費
6月1日(水)
国際:世界経済フォーラム東アジア会議開幕
日本:通常国会会期末、法人企業統計(財務省)、新車販売台数
米国:ベージュブック、新車販売台数
6月2日(木)
国際:OPEC定例総会
日本:マネタリーベース(日銀)、経団連定時総会
欧州:ECB定例理事会
6月3日(金)
国際:アジア安全保障会議
米国:貿易収支、雇用統計
6月4日(土)
その他:中国・天安門事件から27年
◆【一口情報】 知らないと怖い紫外線 2016/05/28
テレビを見ていたら、紫外線対策の間違いについて解説していました。知っているのと知らないのとでは大きく異なります。聞きかじりですが、簡単にまとめてみました。
◇ 紫外線は悪玉? 善玉?
紫外線は、光のスペクトルにおいて紫色の外側にあることからこの名前がつけられたことはよく知られています。いろいろな化学的な作用が大きいので「化学線」とも呼ばれます。
紫外線は、真夏の問題であって、いまの季節はあまり心配ないと考えている人が多いようです。
対策を充分に図らないと皮膚や目への影響はよく知られています。免疫系へ急性もしくは慢性の疾患を引き起こす可能あるようです。なぜ、紫外線がこのように人間にとって好ましくない作用をするのかというと、たんぱく質を変性させることに起因するそうです。皮膚に紫外線が照射されるとコラーゲン繊維を痛め、皮膚の加齢化を促進させてしまいます。
3月頃から徐々に紫外線が増え、4月には警戒量に達し、5月は真夏には及ばないまでも充分な予防策を講じないと夏と同じようなダメージを受けてしまいます。梅雨明けをピークに9月、近年は10月まで警戒期間が広がっているとも言われています。
「にっぱち」といって2月と8月は景気が落ち込むと言うことがよく言われます。このように季節によって同じような形で変動するのが、企業経営でも窺えます。例えば、売上高を月別集計するとほぼ例年一定のパターンになります。これを「季節指数」とか「季節変動指数」と言います。
売上計画など、年度計画を立案するときに季節指数を導入すると月次売上計画に対する達成率を合理的にはかることができ、営業パーソンの管理に利用することができます。(利用方法は当ブログのマーケティング講座で取り上げ予定)
紫外線も季節指数を持っています。この際、紫外線の教えを受けて、自社の季節変動指数の観点で見直しをしてはどうでしょうか。
◇ 誤解されているサングラスの濃淡
「紫外線」について当ブログで紹介しましたところ、「季節指数という知識としては当たり前のことを忘れていました」というコメントをいただきました。「当たり前のことが当たり前にできる企業作り」を標榜している私にとっては大変うれしいコメントでした。
太陽が発する紫外線には、UVA、UVB、UVCという波長によって3分類でき、の紫外線が含まれているが、そのうちUVAとUVBはオゾン層を通って地表にまで届いてしまいます。
これがくせ者で、特に眼にとってはUVBが悪いそうです。白内障になることがよく言われますが、そのほかにも雪山ではサングラスがつきものと言われるように「雪眼」と山男仲間でいわれる雪眼炎は急性作用があるだけに怖いです。
ガラスは、紫外線をあまり通さないことがよく知られています。サングラスは、さらに特殊材料をコーティングするなどしてUVカットを行っています。石英ガラスは、それそのものがUVカットになりますが、プラスチックのサングラスや窓ガラスは、フッ素化合物を使ったコーティングやフィルムを使ったりします。
昔は、偏光サングラスでUVカットをしていましたが、不便がありました。昔のデジタルカメラというのは、ファインダー部分にいまのように液晶を使っておらず、小型のブラウン管が使われていました。そのために、縦フレームで撮影しようとしますと、走査線方向と直角になると画像が全然見えなくなってしまいます。縦フレームで写真を撮るときには、一々サングラスをはずさないととれないという煩わしさがありました。
また紫外線は、反射光にも含まれるので正面からの光だけではなく下や斜めからの反射光にも気をつけなければなりません。紫外線を使った利用機器を使うときや雪山などでは、ゴーグル状の眼鏡をかけるのはこのためです。
以前、当ブログでも書きましたが、サングラスの色の濃さも誤解をしている人が結構います。色が濃いサングラスをかけると瞳孔が開いてしまい、かえって紫外線を取り込む量が増えてしまうからです。ちなみに色はグリーン系よりは黄色系の方が目には良いそうです。
何ごとにも欠点があるということを経営上でも知っておくべきです。濃すぎるサングラスは、過保護の欠陥があります。厳しく鍛えることにより人は育つとも言われます。
とはいえ、「過ぎたるは及ばざるがごとし」という格言を忘れてはいけません。
◇ ワイシャツは紫外線を反射するか?
紫外線について、「季節指数」と「色」について書いて来ましたが、この辺のことは私でも知っていることです。賢明なる読者の皆さんも「今更ブログに書くほどのことでもなかろう」と思われた方が多いと思います。
実は、これから書くことは、テレビで紫外線の番組を見るまでは私は知りませんでした。
「着る物と色」による紫外線対策です。中東で女性が黒い色のチャドルを身にまとうことはよく知られています。なぜ砂漠の暑い地域で黒色のチャドルを纏うかというと、紫外線対策効果があるからと思い込んでいました。
◆
今週一週間を診るポイント 2016/05/23
今週は、伊勢志摩でサミットが開催されます。すでに7部門において日本各地で関係者のトップによる分科会が開催されてきた集大成として、経済問題を中心に話し合われます。その中にはパナマ文書がらみの、税法の仕組みがインターネット時代に添っていないことを踏まえて討議がなされるのでしょう。
伊勢志摩サミットで、消費税率引き上げで消費税率引き上げも迫られることを踏まえて、安倍首相は態度を明確にしていません。景気関連数値が今ひとつ元気ない現状で、衆参同一選挙を強行するのかどうか、国民のためにではなく、与党の都合だけで判断する政治姿勢は一向に改善されませんね。
アメリカではGDP、ヨーロッパでは、EU財務省関連の会合が開催され、日本でも景気動向指数や消費者物価指数など、経済的な指標となる数値や内容が発表されます。桝添東京都知事の様なレベルの低い問題もクローズアップされています。
台湾で8年ぶりに政権を奪還した民進党の蔡英文総統は、中国が認めるよう迫っている「1つの中国」については言及を避けましたが、中国に一定の配慮も示しました。日本政府は、馬政権で後退した台湾との関係を早急に修復するべきです。国交が台湾とはありませんが、本土からの移民国民はともかく、台湾に昔からいる国民は日本びいきです。いろいろな手段を講じて蔡政権を支援すべきと考えています。<映像>
【今週の出来事】
5月22日(日)
※ 現在、手元にご紹介する情報がなく、ご不便をおかけします。
5月23日(月)
国際:世界人道サミット(24日まで)
日本:景気動向指数(内閣府)、貿易統計(財務省)
5月24日(火)
日本:三村日商会頭会見
欧州:ユーロ圏財務相会合
5月25日(水)
国際:国際オリンピック委(IOC)2020年東京五輪・パラリンピック調整委員会
日本:3カ月予報(気象庁)
欧州:EU財務相理事会
5月26日(木)
国際:伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)(27日まで)
日本:企業向けサービス価格指数(日銀)
5月27日(金)
国際:伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)最終日
日本:消費者物価指数
米国:GDP
5月28日(土)
※ 現在、手元にご紹介する情報がなく、ご不便をおかけします。
◆
外務省 サミット報告書冒頭(一部) 2016/05/21
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000158337.pdf
開発とあらゆる人々の能力向上(エンパワーメント)は,G7の一貫した優先事項である。説明責任と透明性は,G7として首脳決定の信頼性と有効性を維持する上で中核となる原則である。我々は,2009年のG8ラクイラ・サミットを受けて,個別の又は全体の開発関連コミットメントに対する進捗をレビューするために,3年毎に包括的な説明責任報告書を発出することに合意した。2010年のG8ムスコカ・サミット,2013年のG8ロックアーン・サミットにおいて包括的な説明責任報告書が発出された。今回の伊勢志摩進捗報告書は3回目の報告書である。
今回の報告書は,①援助と援助効果,②経済開発,③保健,④水と衛生,⑤食料安全保障,⑥教育,⑦平等,⑧ガバナンス,⑨平和と安全,⑩環境とエネルギーという10分野にわたる51コミットメントを扱っている。
◆
国家戦略としてアジアインフラ需要に本腰を 2016/05/18
アジアのインフラ需要は、年間8000億ドル(約85兆円)もあります。 橋、道路、港湾など、まだまだ不充分な国が多いのです。そのような中、中国や韓国などとの競争が益々厳しくなっています。
日本政府は2015年に、2020年までの5年間で総額1100億ドルをインフラ資金として供給する目標を掲げました。その実現に向けて、海外への投融資を担うJBIC(国際協力銀行)の機能を強化する法律を成立させました。今後、日本が主導してきているADB(アジア開発銀行)の重要性が増します。
しかしADBは、投融資にあたってプロジェクトが環境破壊を引き起こさないかなど、審査基準が厳しく、アジア各国の間では、資金需要に十分応えられていないという指摘があります。2015年の投融資などの承認額は162億ドルとアジアのインフラ需要の2%をカバーしているに過ぎません。
これまで中国主導のAIIB(アジアインフラ投資銀行)との協調を模索してきて、ようやく協調融資や技術協力などを行う方向に舵を取ることになりそうです。
AIIBは、まだ実績も少なく、ADBのような慎重な審査よりは実績づくりに重点をおいています。ADB単独では、リスクが大きい部分のリスク回避も可能となることから、今後の両者による協調融資はやむを得ないのかもしれません。
一方、中国・AIIBとしては、実績がないことから信用度が高まります。実績が出て来れば、まだ未加入の日本やアメリカの加入に繋がることもAIIBとしては期待しているでしょう。経験不足による投資ノウハウをADBから盗み取ることも可能です。
私は、ADBとAIIBとの棲み分けをキチンとし、ADBは従来通りの質の高い投資や、リスクはあるが将来性のある投資による、思い切った低金利で、アジア発展支援を進めていくようなコンセプトとすべきと考えます。 ◆
一週間を診るポイント 2016/05/15
フィリピン大統領選挙で「フィリピンのトランプ氏」が勝利を収めました。中国との関係を修復すると明言しています。台湾では、中国寄りの馬政権から、民進党の蔡英文氏が就任しますが、早速中国が圧力をかけてきました。 <詳細>
日本では、GDP、鉱工業関連数値、機械受注高、訪日外国人数が発表されますし、アメリカではCPIや住宅着工件数などの数値を受けてFOMC議事要旨の発表があります。いずれも予想通りなのかどうか、それが為替や株価にどの様に響くのかに関心が寄せられています。
オリンピック、タックスヘイブン、等々のキーワードも気になる一週間です。
5月15日(日)
※ 現在、手元にご紹介する情報がなく、ご不便をおかけします。
5月16日(月)
日本:企業物価指数(日銀)
5月17日(火)
国際:サッカーACL決勝トーナメント開始
日本:鉱工業生産・出荷・在庫指数確報(経産省)
米国:CPI、住宅着工件数
5月18日(水)
日本:GDP(内閣府)、石油製品価格調査(資源エネルギー庁)、訪日外国人数(日本政府観光局)
米国:FOMC議事要旨
5月19日(木)
日本:機械受注(内閣府)
5月20日(金)
国際:G7財務相・中央銀行総裁会議
日本:主要コンビニ売上高、粗鋼生産
その他:台湾総統就任式
5月21日(土)
※ 現在、手元にご紹介する情報がなく、ご不便をおかけします。
◆
トクホと機能性表示食品の違い 2016/05/14
朝日新聞に、トクホと機能性表示食品についての記事が掲載されていましたが、多くの方がご覧になったかと思います。
健康に良い食品でも、無許可で「この食品は胃がんに効果があります」などという表示はできません。しかし、食品の中には、明らかに健康に良い物が多数あります。
トクホとは、正式には「特定保健用食品」といい、1991年に始まりました。消費者庁の管轄下の消費者委員会や食品安全委員会による、有効性や安全性の審査にパスしますと表示が許されます。しかし、審査に数年、費用も億単位となり、大半の中小企業には縁の遠い存在です。
アベノミクスの経済成長戦略の一環として、2015年に始まったのが「機能性表示食品」に関する制度です。こちらは学術論文など、一定の科学的根拠を示すことができれば、届け出制で表示できます。食品に含まれる成分の健康への効果を、広告やパッケージに表示することができます。届け出から受理まで数カ月で済みます。
しかし、悪質業者が、無届けで表示しても一般の消費者には解らないこともあるでしょうから、われわれ庶民は騙されないようにしなければなりませんね。
◆ 駅で宅配を受け取れるようになります 2016/05/12
以前にも、私のブログでご紹介しましたが、JR東日本の駅で宅配物を受け取ることができるようになります。サービスは、6月に開始されますが、宅配業者からの連絡に基づいて、駅に設置された「宅配受取ロッカー」で受け取れる仕組みです。
宅配物を、自宅で誰かが受け取れることが可能なご家庭ではメリットはあまりないかもしれませんが、ひとりでお住まいの人にとってはありがたいサービスではないでしょうか。
日本郵便とヤマト運輸のサービスを受けられますが、利用できる駅は限られています。現在、利用できる駅候補としてあがっているのが、池袋、川口、蕨、大井町、鶴見、藤沢、平塚、豊田、下総中山、幕張、東所沢などだそうです。1年以内に100駅程度まで増やす計画とのとことです。 <詳細><映像>
◆
「赤プリ」跡地が複合ビル商業施設として一部開業 2016/05/10
東京の人以外ですと「赤プリ」という言葉にピンと来ないかもしれません。「赤プリ」は「グランドプリンスホテル赤坂」の愛称で親しまれていました。昭和初期に建てられ、旧朝鮮王室の邸宅として使われたこともある歴史的建造物があった地で、建物の一部は残されることになっています。
5年前に閉館し、地上36階建ての複合ビルとして再スタートします。商業施設やオフィス、ホテルなどが入る複合ビルと、別棟には賃貸マンションで高盛されます。
複合商業施設は、都内だけでも処々にあり、二番煎じどころか何番煎じです。地域的にも若者には馴染みのあまりないところですので、東京丸の内、新宿、渋谷、六本木、品川を初めとする競争の中で、うまく行くのでしょうか。
賃貸マンションにおいても、マンションの空き室問題が深刻な時代にニーズがあるのでしょうか。永田町に近いと言うことから、その需要が、われわれ庶民には計り知れない大きさがあるのかもしれません。 <映像>
◆ 一週間を診るポイント 2016/05/09
アメリカは、大統領予備選が最終版に入りますが、予備選での結果がクリントンvsトランプという形で固まったことから、本選挙に向けての選挙演説にどの様に切り替わるのでしょうか。財政収支の数値も発表されます。
イギリスは、エリザベス女王生誕90年の祝賀ムードいっぱいですが、EU離脱問題を抱えています。EUのGDP発表がありますが、難民問題がくすぶっています。
目をアジアに転じますと、フィリピン大統領選、中国のCPIやPPIなど重要な経済指数が発表されます。それらが先週の株価乱高下にどの様に影響するのでしょうか。
5月8日(日)
日本:大相撲夏場所初日
その他:中国貿易統計
5月9日(月)
国際: 日本:消費動向調査(内閣府)、勤労統計調査(厚労省)、金融政策決定会合(日銀)
その他:フィリピン大統領
5月10日(火)
日本:車名別新車販売台数
その他:中国CPI・PPI
5月11日(水)
日本:景気動向指数(内閣府)、石油製品価格調査(資源エネルギー庁)
米国:財政収支
5月12日(木)
日本:景気ウオッチャー調査(内閣府)、金融政策決定会合(日銀)、国際収支、企業倒産
欧州:英女王90歳の公式祝賀イベント(~15日)
5月13日(金)
国際:米大統領・欧州諸国首脳会議
日本:第3次産業活動指数(経産省)、黒田日銀総裁講演
米国:小売売上高
欧州:ユーロ圏GDP
5月14日(土)
その他:中国鉱工業生産・小売売上高
◆ 一週間を診るポイント 2016/05/02
今週は、安倍首相が欧州5か国とロシアを訪問します。5月26日から始まるサミットを成功させるためには、ヨーロッパ諸国の理解が求められます。とりわけECを引っ張っているドイツのメルケル首相との会談は重要です。プーチン大統領とも、北方領土問題がらみで重要なのですが、アメリカに遠慮をしすぎます。
円安傾向が続いてきたのですが、ここに来て円が戻してきました。日銀総裁のちょっとした発言で、為替が乱高下するという状況は決して好ましいとは思いません。行き過ぎを押さえるために為替操作がなされていることはよく知られています。それを規制しようというアメリカ財務省の監視強化のために「監視リスト」の動きも行き過ぎと考えます。<映像>
5月1日(日)
国際:G7エネルギー相会合
日本:安倍首相欧州・ロシア訪問(~7日)
その他:中国製造業PMI
5月2日(月)
国際:ASEANプラス3(日中韓)財務相・中央銀行総裁会議閉幕、アジア開発銀行(ADB)年次総会開幕(~5日)、日仏・日伊首脳会談
日本:新車販売台数
5月3日(火)
日本:憲法記念日(祝日)
米国:新車販売
5月4日(水)
日本:みどりの日(祝日)
米国:貿易収支
5月5日(木)
国際:日ベトナム外相会談
日本:こどもの日(祝日)
5月6日(金)
国際:安倍首相ロシア訪問
日本:マネタリーベース(日銀)
米国:雇用統計
5月7日(土)
※ 現在、手元にご紹介する情報がなく、ご不便をおかけします。
◆ 鶏むね肉をおいしくする料理ノウハウ 2016/05/01
NHKの看板番組のひとつ「ためしてガッテン」が「ガッテン」として、毎週水曜日NHK総合TVで午後7時30分から放送されています。
4月27日は、鶏むね肉の料理法についてでした。山男料理を山でつくることくらいはしたことがあるものの、平素、台所に立つことのない私には、料理法の番組になど見る気にもなりませんでした。
ところが、鶏むね肉というのは、高タンパクで低脂肪と、ヘルシーな食品ですので、冒頭をちょこっと見ました。
鶏むね肉といいますと、パサパサな食感で、今ひとつ味の深みに欠けている気がします。ショウガ、重曹、ヨーグルトなどを使って、むね肉を柔らかく調理するウラ技があるそうですが、どの程度の人が利用しているのでしょうか。
この番組で紹介されたのは、マイタケのタンパク質分解酵素を利用する方法で、出演者の言葉ですので、割り引いて見なければなりませんが、「唇に触れただけでも柔らかさを感じる」ほどだそうです。
調理法もそれほど難しくなさそうで、結局最後まで見てしまいました。もちろん、料理をするのは妻です。
■■ 経営コンサルタントへの道 ←クリック
経営コンサルタントを目指す人の60%が閲覧


![]() 前日までのバックナンバー ←クリック
前日までのバックナンバー ←クリック![]()
![]() 2016/07/25
2016/07/25











 【
【