■【お節介焼き情報】 江戸っ子1号の活動から学ぶ

当ブログで「江戸っ子1号」の話を紹介しました。
江戸っ子1号は、民間企業が共同で作った深海探査機です。
江戸っ子1号の構成は、上から順に通信球、トランスポンダ、回路球、照明球、カメラ球となっており、船から深海にフリーフォールで沈めます。水中では、1分間に約50~60mずつ沈みます。
沈む様子と着底は、船上から機体についているトランスポンダへ音波を飛ばし、跳ね返ってくるスピードによって深度を割り出すことで確認することができます。
浮上時は、船からの音波信号を電流に変え、錘を切り離すことで観測を終了した機体は自らの浮力で海面へ浮上します。海面へ浮上した機体は、GPSで座標を確認し、船で回収します。
*
NHK解説委員の今井純子氏が「脱下請け体質への課題」と題して論評していましたので、その要旨を紹介します。
江戸っ子1号に取り組んでいる社長さん達は、決して道楽だけでやっているわけではありません。苦境にあえいでいる中小・零細の企業が、下請けから脱却するにはどうしたらいいのか、氏は3つのヒントを挙げています。

【異業種との連携】
中小企業の多くが個々にもっている高い技術を活かし切れていません。その理由の一つが部品や素材の会社ですので、それ単独では商品になりません。単独の高い技術を、ほかの分野の会社と連携することで、製品という形にまで昇華することが可能なのです。

【産官学の連携】
江戸っ子1号の開発には、当初から、海洋研究開発機構、芝浦工業大学、東京海洋大学というような官学を巻き込んでいます。
大規模なコンピューターによる解析などは、中小企業ではとてもできません。しかし、大学がもっている設備を使えばこれが可能です。その結果を利用して工場(こうば)ですばやく試作品を作ることが可能となります。
海洋研究開発機構が、専門的な知識や実験の支援をしています。
このような連携が町工場だけでは難しい技術の開発にもつながりました。

【コーディネーター役の存在】
ここで不可欠なのが、コーディネーター役の存在です。
今回は、地元の中小企業を支援している信用金庫がアイディアを提供し、大学や機構に橋渡しました。中小企業だけでは、官学との関係を持つことは困難であり、プロジェクトの発足もできなかったでしょう。
日々の操業に追われている町工場に代わって、実験の段取りなど、事務局の役割も果たしました。

【まとめ】
日本のものづくりと雇用を支えてきた多くの中小・零細の企業が消えていくことになれば、日本の競争力の土台が崩れることにつながりかねません。
まずは、経営者が、前向きに挑戦すること。それが大前提ですが、やる気のある経営者をみつけて、体質の転換を支援する。その態勢づくりを、国や金融機関は、急いでほしいと思います。

【コメント】
単に製品を開発するだけであれば、地元の信用金庫だけでも済むかもしれませんが、開発した製品を「商品化」するとなると、限界があります。このときに必要なのが経営コンサルタントといえます。

◆ 心で経営 論語や菜根譚をもとに経営者のあるべき姿を説く

【心de経営】シリーズは、「経営は心deするもの」という意味になります。それとともにフランス語の前置詞であります「de(英語のof)」を活かしますと、「経営の心」すなわち、経営管理として、あるいは経営コンサルタントとして、企業経営をどの様にすべきか、経営の真髄を、筆者の体験を通じて、毎月新しいブログを発信いたします。

【筆者紹介】 特定非営利活動法人日本経営士協会 藤原 久子 先生
北海道札幌市出身、20年間の専業主婦を経て、会計事務所に約4年半勤務。その後平成元年7月に財務の記帳代行業務並びに経理事務員の人材派遣業の会社を設立し、代表取締役として現在に至る。従業員満足・顧客満足・地域貢献企業を目指し、企業の永続的発展を願う。
平成22年には横浜型地域貢献企業の最上位を受賞、続いてグッドバランスの受賞により、新聞、雑誌の掲載をはじめ、ラジオやWebTV(日本の社長100・神奈川県社長t v)に出演したりして、各種メディアで紹介されている。
 ■ ご挨拶
■ ご挨拶 自社の経営に当たりまして、何かと忙しい経営者に安心して事業に専念してほしいとの想いと、そして忙しい経営者に、私たちからは「もっと心の通いあうサービス提供を」という原点を忘れてはならないと常に考えております。また、「顧客第一主義」と「企業は人なり」の精神を揺るぎないものとして持ち続けることも大切です。
その信念に「学び」をプラスして更なる人間的魅力を形成してはじめて、従業員やお客様から信頼されるのです。そのためにも、まず自分自身を磨くことが大切です。
人にはそれぞれ自分なりの生き方があります。経営者様をはじめ、これから経営者として歩み始めるみなさまや経営コンサルタント・士業の気づきや学ぶ機会になれば、これほどに嬉しいことはございません。
*
■ 【心 de 経営】ブログのバックナンバーを閲覧するには
下記URLのいずれかををクリックしてください。











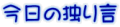
















 since 1951 特定非営利活動法人・日本経営士協会
since 1951 特定非営利活動法人・日本経営士協会




