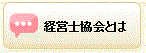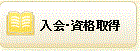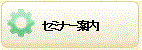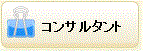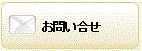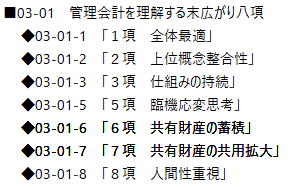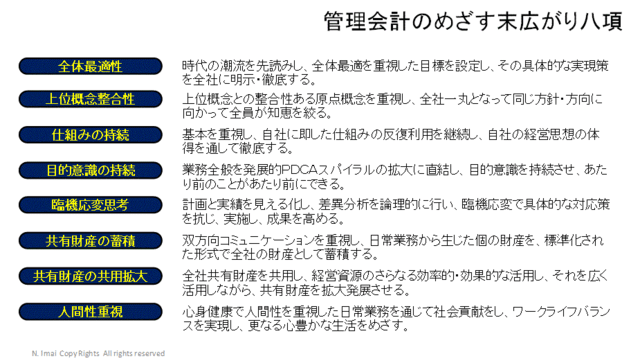■■【経営コンサルタントのお勧め図書】165 「ランチェスター戦略」の核

「経営コンサルタントがどのような本を、どのように読んでいるのかを教えてください」「経営コンサルタントのお勧めの本は?」という声をしばしばお聞きします。
日本経営士協会の経営士・コンサルタントの先生方が読んでいる書籍を、毎月第4火曜日にご紹介します。

■ 今日のおすすめ
A;『ランチェスター戦略』 (編著:NPOランチェスター協会 中経文庫)
B;『社長のためのランチェスター式学習法』(著者:竹田 陽一 あさ出版)
C;『ランチェスター法則のすごさ』(著者:竹田 陽一 中経出版)

■ 「ランチェスター戦略」の有用性は(はじめに)
ランチェスター戦略は、近年ではソフトバンクの孫正義氏、H・I・Sの澤田秀雄氏等が創業時に経営に応用し、成長したことは良く知られていることです。彼らは、ランチェスター戦略のどこに有用性を見出したのでしょう。言い換えれば、紹介本のどこに焦点を当てるべきなのでしょう。以下で見てみたいと思います。
ここで、一言触れておきたいことがあります。紹介本を三つ挙げました。こんなややこしいことをしたくないのですが、A紹介本(以下協会説またはA本という)とB、C紹介本(以下竹田説またはB、C本という)が、ランチェスター戦略の一番肝心な弱者戦略と強者戦略の定義あるいは解釈が異なるのです。協会も竹田氏もランチェスター戦略の第一人者とされる人(人々)です。ご判断は読者の皆様にお任せしますが、異なることだけは、知って置いて頂くと良いかなと思い、敢えて、二つの説の違いを以下でご紹介いたします。

■ 「ランチェスター戦略」の核はここだ
【ランチェスター戦略で最も知られている「意味を持つ占有率」】
世界で始めて、市場占有率(自社営業範囲内)とその占有率の持つ意味を具体的に示したのは、ランチェスター戦略を生み出した、「田岡、釜田理論」です。
市場占有率とその意味を以下に記します(詳細、計算根拠はC本をお読みください)。
① ウルトラスーパー強者(A本では「上限目標値」):73.88%以上のシェアを有する。
② スーパー強者(A本では「安定目標値」):一位で、41.7%以上かつ二位との間に1.68倍以上の差をつけている。(73.88/26,1=2.83。2.83の平方根=1.68。2.83を第一法則〈一次法則:弱者法則〉下の射程距離、1.68を第二法則〈二次法則:強者法則〉下の射程距離と呼ぶ。射程距離以内だと市場の均衡を崩せ、射程距離を越えると市場の均衡を崩せないとするランチェスター理論の一つ。)
③ 強者(A本では「下限目標値」):一位で、26.1%以上かつ二位との間に1.68倍以上の差をつけている。
④ 中間者(A本では「上位目標値」):15,6%~26,0%
⑤ 弱者のA(A本では「影響目標値」):9.4%~15,6%
⑥ 弱者のB(A本では「存在目標値」):5.6%~9.4%
⑦ 弱者のC:3%~5.6%(A本では触れていない)
⑧ 番外(A本では「拠点目標値」):3%未満
これらの占有率は各々自社の現状の力を現すと共に、次に狙うランク目標を示します。3%未満の番外は、市場から撤退すべきかどうかの判断をすべきポジションとされています。更に言えば、特定のセグメント(地域、商品、顧客等)に於けるシェアを念頭に置いたときに、これらの占有率は意味を持ってきます。
【ランチェスター戦略は弱者が強者に勝つための戦略理論】
ランチェスター理論は元々弱者が強者に勝つための戦略論です。
竹田説は強者の定義を上記①②③とし、それ以外は弱者とします。1000社の内「強者の経営戦略」を行える条件を満たしているのは0.5%、残り99.5%は「弱者の経営戦略」をとるべしとしています。「弱者の経営戦略」として、小さくてもナンバーワンになれる得意分野を見つけ実現する。そこを起点にし、ナンバーワンの領域を広げて行く13の戦略・戦術(いわゆる「差別化戦略」。細かくは、「①ナンバーワンになれる商品、地域、客層を探す②攻撃目標と競争目標の分離③差別化④小規模1位主義、部分1位主義⑤商品や営業の細分化⑥⑦⑧⑩一点集中⑨直接販売⑪軽装備・軽投資⑫継続性、ステップ・バイ・ステップ⑬自社の戦略情報の漏洩防止管理」をあげています。詳細はB本をお読みください。)を掲げています。
一方協会説は、「弱者の戦略(差別化戦略)」と「強者の戦略(ミート戦略)」が並んで出てきます。「弱者の戦略」とは、弱者が自分よりもシェアがワンランク上の競争相手(頭上の敵)の市場を奪い、小さくともナンバーワンになれる得意分野を見つける戦略と言います。「強者の戦略」は弱者が自分よりもシェアがワンランク下の競争相手(足下の敵)の市場を奪い、得意分野がナンバーワンになるための基盤強化を図る補助戦略と位置づけます。「弱者の戦略(差別化戦略)」と「強者の戦略(ミート戦略)」を同時並行的に行うべしとします。(私にはその様に読み取れました。)
経営資源の乏しい弱者が、二つの異なった戦略を並行的に行う戦略は現実的でしょうか。弱者はあくまで弱者として「差別化戦略」を実行すべしとする竹田説が「ランチェスター戦略」の基本ではないでしょうか。
更に注目しておきたいことは、弱者は強者から第二法則(二次法則:戦力=質×兵力数の二乗)で攻められ、弱者が強者を攻めるときは、経営資源が乏しいので、第一法則(一次法則:戦力=質×兵力数)で攻めなければならないと言うことです。弱者が強者を攻めるには、2.83倍以上の力を集中して攻めなければ強者に勝てないというのが「ランチェスター戦略」の理論でもあることです。そこには「戦略・戦術」に加え、「物理的・時間的・継続的」努力がなければ、勝利は実現しないこと現しています。
【弱者のための代表的戦略「地域戦略」】
A本では「ランチェスター戦略」の三つのキーワードとして①ナンバーワン主義②セグメンテーション③ステップ・バイ・ステップを挙げています。それを実現する代表的戦略として、「地域戦略」(あるいは「特定のセグメント戦略」と言っても良い)を掲げています。
「地域戦略」で成功するための5つの原則を掲げています。参考に出来る内容ではないでしょうか。
① 一点集中の原則(一位になれる重点領域、エリアの決定)
② 足下の敵攻撃の原則(競争目標:頭上〈ランク上〉の敵、攻撃目標:足下〈ランク下〉の敵の中から攻めるライバルを絞り込む)
③ 地盤強化の原則(まずエリアをしっかり固める)
④ ナンバー・ワン・キープの原則(大口顧客やリーダー格顧客を確保する)
⑤ 固定化の原則(離脱客をなくし、リピーターを増やす)

■ 「ランチェスター戦略」を経営に応用する(むすび)
「ランチェスター戦略」の核は何かを見てきました。「ランチェスター戦略」はどちらかと言うと馴染の薄い経営戦略論ではないでしょうか。「ランチェスター戦略」の核の部分を押さえ、その核の理論とその他の経営理論を組み合わせて使うことで、経営に有用なツールとして使えるのではないでしょうか。

【酒井 闊プロフィール】
10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。
企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。
http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/2091.htm
http://sakai-gm.jp/
【 注 】
著者からの原稿をそのまま掲載しています。読者の皆様のご判断で、自己責任で行動してください。

■■ 経営コンサルタントへの道 ←クリック
経営コンサルタントを目指す人の60%が見るというサイトです。経営コンサルタント歴35年の経験から、経営コンサルタントのプロにも役に立つ情報を提供しています。