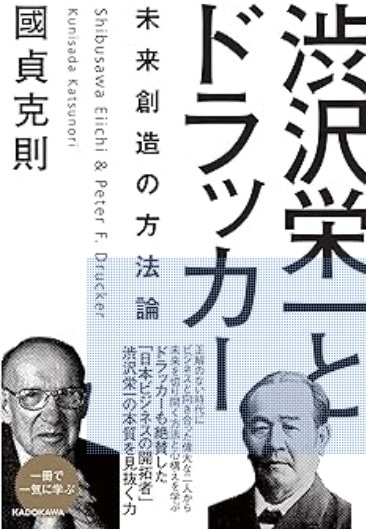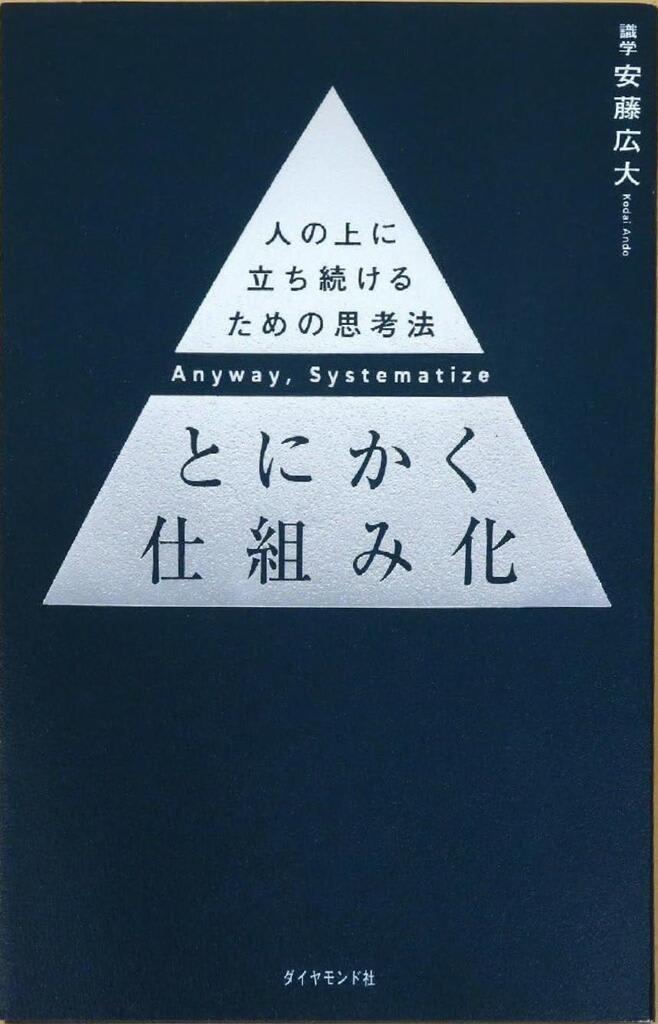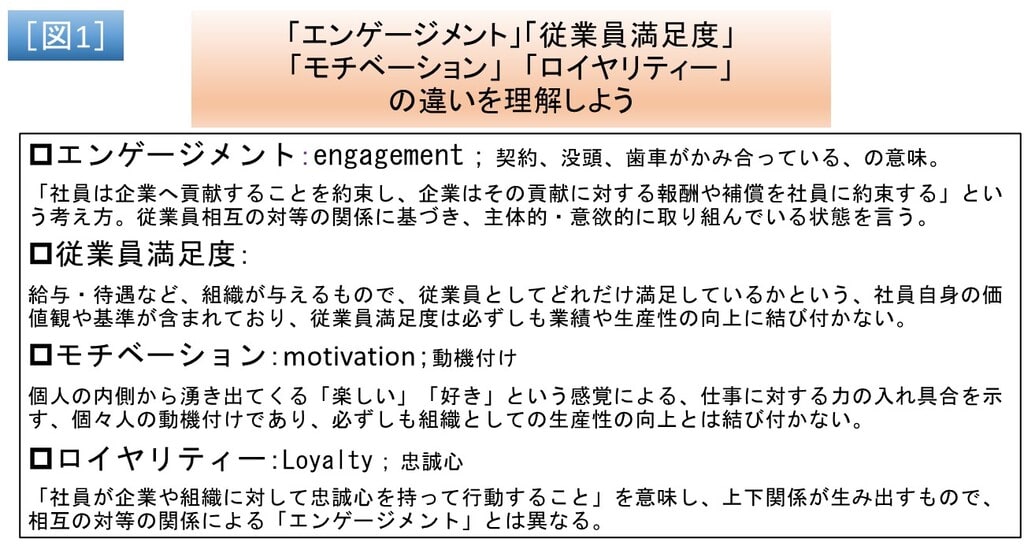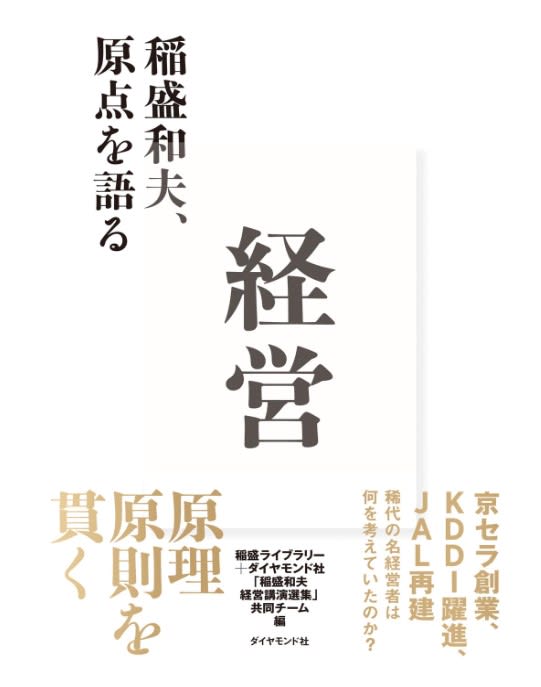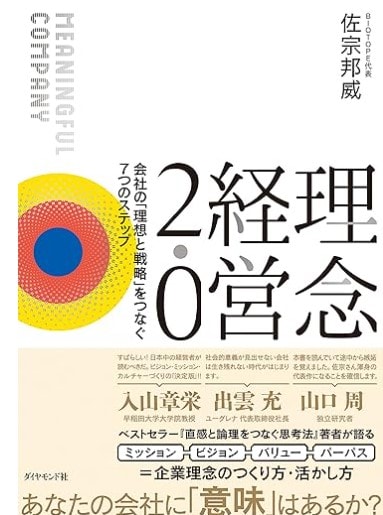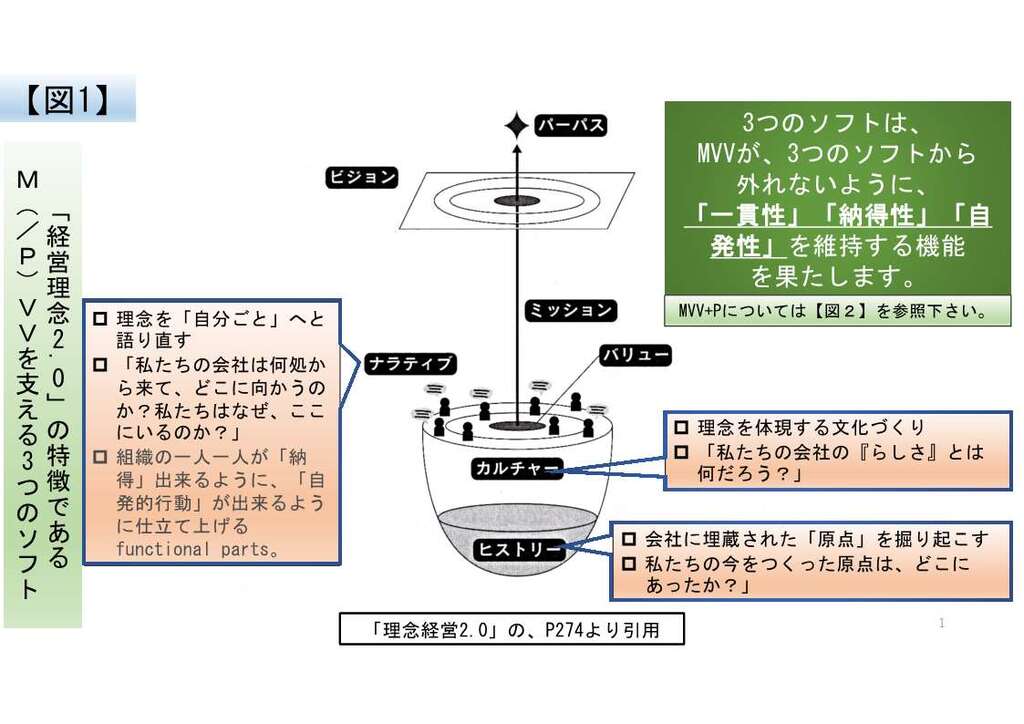【経営コンサルタントのお勧め図書】 2025年の日本の論点 日経大予測
【経営コンサルタントのお勧め図書】 2025年の日本の論点 日経大予測
『日経大予測2025「これからの日本の論点」』
発売日 : 2024/10/26 単行本(ソフトカバー) : 360ページ
ISBN-10 : 4296121189 ISBN-13 : 978-4296121182
寸法 : 21 x 14.8 x 2.3 cm
![]()
■ 2025年の「日本の論点」に注目してみよう(はじめに)
紹介本は毎年日本経済新聞社から新年に向けて出版される恒例の本です。
2025年版で留意して置きたい事は、2024年10月25日に発刊されており、11月5日に投開票された米大統領選挙におけるトランプ氏圧勝の事象が織り込まれていないことです。
2025年1月20日にスタートする、トランプ政権の政策、つまりウクライナ戦争対応、中東戦争対応、気候変動対応、対中対応などを注視する必要があります。
2025年版「日本の論点」は、「日本は現状維持すら危ういのか」「押さえておきたいビジネスの勘所」「世界を巻き込む米欧中露の対立」の3Chapter、22論点に亘って日本経済新聞の専門記者22人が2025年の予測を示しています。
それでは22論点の中から、注目論点を、Chapterに沿って、次項で紹介します。
![]()
■ 2025年の注目論点
【日本のGDP、世界第5位に、覚醒なくして成長なし-論点6-】
「ジャパン・アズ・ナンバーⅩ」という表記を最近見かけます。このⅩの推移を見てみましょう。Ⅹに「ワン」が入った時代は、1968年、当時の西ドイツをGDPで上回り、米に次ぐ世界第2位の経済大国に躍り出た頃です。
1979年にエズラ・ヴォーゲルの著者『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(Japan as Number One: Lessons for America)が出版されました。そこでは、日本が1955年~1973年にかけ平均10%を超える経済成長を遂げた時代の経済的・社会的な成功を収めた要因を分析し、アメリカをはじめとする他国が学べる教訓を提示しています。
その成功要因としてヴォーゲルが挙げているのは、教育制度(日本の教育水準の高さ、競争的な受験制度など)、官民協力(通商産業省と企業の連携)、企業文化(人間中心などの日本的経営による労働者の高いモチベーション)、社会的安定(良好な治安や強いコミュニティ意識)です。
しかし、今の日本は、「ゆとり教育」、「日本企業より外国企業を利する経産省の脱炭素政策」、「『働き方改革』による働かない改革」、「日本人の仕事への熱意保有者の比率は5%と145カ国中最下位」、「日本の犯罪件数は、過去最低の2021年57万件が、22年60万件、23年70万件と20年振りに増加し治安が悪化」など、教育・産業政策・企業文化・社会的安定の全ての分野で、エズラ・ヴォ―ゲルの示した成功要因(上記)に逆行しているように思えます。この結果、一人当たりGDP世界ランキング(IMF)では、ピークは2位(2000年)でしたが、直近(2023年)では韓国にも抜かれ34位です。予測では、2024年には台湾にも抜かれます(日経2024.12.18電子版)。
そのヴォーゲルは、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の出版から27年後の2006年11月11日の「週刊ダイヤモンド」で、失われた17年からの日本再興の要件として、個々人の仕事への熱意と、それをリードする、社会への真の責任意識を持ち、党派や利害関係を超越した、リーダーの出現を掲げます。(2024.2.21 DAIAMOND onlineの記事より)
「論点6」は、この「Ⅹ」が、2010年には中国に抜かれ3位に、2023年にはドイツに抜かれ4位になり、更にこの先、2050年にはインドとインドネシアに抜かれ6位に、2075年にはパキスタン・エジプト・ブラジル・英国などに抜かれ12位になるとのゴールドマン・サックスの予想を引用し、『今こそ「政・官・民の覚醒」により「Ⅹ」を小さくする時』と主張します。
2025年こそ、社会への真の責任意識を持ち、党派や利害関係を超越した、政・官・企業のリーダーが出現し、日本の社会・経済を覚醒させ、失われた30年から脱出する年となることを期待したいですね。
【会社脳が企業の競争力を左右、生成AIが企業経営を一変させる-論点11-】
「論点11」は、次のような指摘をします。「2025年は生成AIを『試す』という段階を過ぎ、本格的に経営に『生かす』ための知恵を問われる年になる」と。
この生成AIの象徴的な存在が、生成AIの一種である、LLM(Large Language Models-大規模言語モデル-)のオープンAI社のChatGPTです。2022年11月にプロトタイプを公開し、2か月で利用者が1億人に達しました。
2024年5月のChatGPTのユーザーは23億人です。ChatGPTは膨大な学習データ・情報から最適なアウトプットを生成できる点が特徴であり、また、企業の独自のデータや知見をAPI(application programming interface)で連携して活用することで、経験の浅い従業員でも、一定以上のアウトプットを作成できるようになります。この様な特徴を生かし、「業務自動化による人手不足の解消・コスト削減」「業務サポートによる品質・スピードの向上」「社内知見の共有・業務の標準化」「マーケティングの最適化・費用対効果向上」「顧客体験のパーソナライズ・自動化」「新規商品・サービスの創出」などの分野で活用することが可能です(AI総研H・Pより)。
また、AppleとChatGPTの連携も注目されています。2024年6月Apple社はSiriとChatGPTを連動させた生成AI「アップル・インテリジェンス」を発表し、2024年10月からiPhone等のOSに組み込みます(日本語版は2025年以降)。
ChatGPTなど(他にはGoogle Gemini、Perplexity、Microsoft Copilotなど)の生成AIに対する評価の一例をあげましょう。星野リゾートの星野代表は次のように評価します。「生成AIは、観光産業を変革する、嘗ての3つの変革(①周遊型から滞在型②インバウンド③スマートフォンでの顧客獲得などのIT化)に次ぐ4つ目の大きなチェンジとなるばかりでなく、生成AIとのブレーンストーミングにより、従業員の創造性を刺激する良きパートナーであり、人力による業務をAI化することで経営戦略にかかわる業務に従業員のエネルギーを振り向けることを可能にする」と。
電子情報技術産業協会によれば、日本における生成AI市場の需要見通しを、2023年1,180億円、2025年6,879億円、2030年1兆7774億円(7年で15倍)と予測しています。
また、「論点11」は、2025年以降、この生成AIの企業版LLM「会社脳」が広がる可能性を指摘します。具体例としてパナソニックホールディングの例を挙げます。パナソニックはグループ内の製品情報、技術情報などの社内データによるパナソニック専用のLLMを構築し、研究開発や設計・製造、営業などの多くの部門で社員が活用できる仕組みを目指します。つまり、世の中に存在するデータ全体を見ると、ChatGPT等のインターネット上のオープンデータによるLLMは20%に過ぎず、残りの80%は企業などの組織内にあります。2025年は、この残りの80%の生成AI化により、企業経営を一変させる時代と指摘します。「企業版LLM」に注目していきましょう。
【プーチンの逆襲、侵略戦争から外交戦へ-論点22-】
「世界を巻き込む戦争の足音-論点2-」の中で次のように指摘します。「中露朝の枢軸を背景に、ウクライナ戦争を舞台に、欧州は準戦時状態に入り、中東では全面戦争の危機がくすぶり、アジア太平洋では朝鮮半島、東・南シナ海での緊張が高まり、世界を巻き込む戦争の足音に対峙している」と。
また、「論点22」の「プーチンの逆襲、侵略戦争から外交戦へ」では、プーチンが目指す、「多極世界」外交政策による、「米一極世界」を突き崩す、新たな世界秩序の形成に焦点を当てています。
論点22の記者は、プーチンの新たな世界秩序形成への外交戦略を「三層構造」戦略と定義しています。一層目は、ユーラシアを横断するような反米枢軸国(注1)、二層目は、ユーラシア大陸全体に新しい秩序を広げようと目する、上海協力機構-SCO-(注2)、三層目は、中南米の国々を巻き込んだ、よりグローバルな枠組みの拡大BRICS(注3)です。
一方、ロシアの足元では、集団安全保障機構-CSTO-(注4)からは、アルメニアが離反し、ソ連崩壊後に結成した独立国家共同体-CIS-(注5)からは、2009年ジョージアが、2018年にはウクライナが脱退し、茲許、モルドバが離反の意向であり、カザフスタンはロシアとの距離を置きはじめており、逆風が吹いています。
最近では、2024年12月8日、ロシアがバックアップしていた、54年続いた、シリアのアサド政権が崩壊しました。加えて、2024年12月27日には、CSTOのメンバーである、キルギス・ウズベキスタンの総延長523キロの巨大鉄道プロジェクトが、永年、ロシアが主導権を主張し「頓挫」していましたが、ロシアがウクライナ侵攻の影響で投資余力がなく、しぶしぶ中国主導を承認し、中国主導の下、着工しました(2025.1.9.JETRO記事)。この様に、ロシアはウクライナ侵攻の代償として、旧来の「勢力圏」を喪失しつつあります。(注6)
記者は、『プーチンは、この逆風に負けず、これらの「三層構造」の結束を強め、反米を目指す、「多極世界」への世界戦略を諦めることはない』と指摘します。
さて、このような流れの中での注目は、2025年1月20日にスタートするトランプ政権後の世界情勢の動向に注目です。
ここで、論点2や論点22とは異なる、最近のネット上の情報を見てみましょう。ネット情報によれば、トランプ政権スタート後、「24時間以内」が「6か月以内」に後退したものの、合意内容は兎も角、ロシアとウクライナは停戦すると予測します。
さらに、トランプは、ウクライナ停戦後には、お得意のディールで、ロシアに対する制裁を緩めることで、ロシアのイランに対する影響力を利用し、一方、イスラエルにはアメリカが影響を及ぼし、中東紛争を終結させると予測します。
また、中東紛争の終結を予測してか、2024年12月、インドとUAEが会談し、2023年9月のG20ニューデリーサミットで、インド、米国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、フランス、ドイツ、イタリア、欧州連合(EU)が参加を表明し、覚書に署名した、「インド・中東・欧州経済回廊(IMEC)」プロジェクトが、一時中東紛争から関係国の協議が遅れていましたが、ここにきて、具体的推進で合意したのです(注7)。
『ロシアの「足元」で吹く「逆風」』に加え「IMECプロジェクト」など、今後の地政学的変化は見逃せません。
いずれにしても2025年の注目論点です。
(注1) 反米枢軸国:中露、イラン、ベラルーシ、北朝鮮の5ヶ国
(注2) 上海協力機構-SCO-:中露、インド、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、パキスタン、イラン、ベラルーシの10ヶ国
(注3) 拡大BRICS:中露、ブラジル、インド、南アフリカ、エジプト、イラン、エチオピア、アラブ首長国連邦、エチオピア、インドネシアの11か国から成る国際会議。更に、ベラルーシ、キューバ、ボリビア、マレーシア、ウズベキスタン、カザフスタン、タイ、ウガンダ、トルコ、アルジェリア、ベトナム、ナイジェリアなどが加盟希望。
(注4) 集団安全保障機構-CSTO-:ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタンの6か国。2024年6月にアルメニアが脱退表明。
(注5) 独立国家共同体-CIS-:ロシア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、トルクメニスタンの10か国。CISは貿易・投資協定の側面があり、アルメニアはCSTO脱退表明後も留まる意向。
(注6) 本欄の『ロシアの「足元」で吹く「逆風」』に登場した国々を、Google Map上〔図1〕に表示しました。〔図1〕は下記URLを参照ください。
http://www.glomaconj.com/joho/keiei/sakai20250128-1russia.jpg
↑ 拡大
(注7) IMEC(インド・中東・欧州経済回廊)のルート図は〔図2〕を参照。(詳細情報は2025.1.14日経電子版)〔図2〕は下記URLを参照ください。
IMEC:India-Middle East-Europe Economic Corridorの略
http://www.glomaconj.com/joho/keiei/sakai20250128-2IMEC.jpg
↑ 拡大
![]()
■ 2025年は変化の年(むすび)
2025年は、生成AI、AI時代のエネルギー問題、中露vs欧米の関係などに於いて大きな変化が見込まれます。注目していきましょう。
![]()