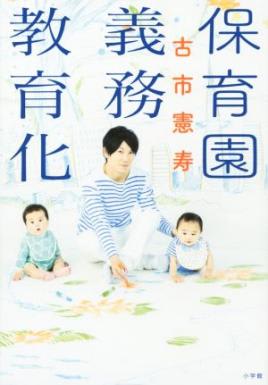終って着替えてから結局4人でいつもの「しげ寿司」へ。
とりあえず、まずはビール で乾杯。
で乾杯。
つまみは最初はカツオのたたき。

これはショウガ醤油で食べます。ニンニクはついていない?ついていませんでした。
ビールはすぐになくなってもう2本。
次の肴は、森の熊さんの定番のイカゲソの七味焼き。

森の熊さんに聞くと必ず頼む一品です。
またまたビールはなくなるので今度は焼酎を出してもらいます。

まだだいぶ残っているので水割りでいただきます。
今度は私のリクエストで、蝦蛄を。

家でもたまに茹でるのですが、蝦蛄は甲羅というか皮というかを取るのがめんどくさい。ハサミで両縁を切って剥がすのですが、手がびしょびしょになるし誰かが剥いてくれたらといつも思っていて、ここはちゃんとむき身が出てくるので幸せ。
同時にこれまた森の熊さんのリクエストでマグロのほほ肉焼き。本当はカマ焼きがよかったのですが、この日はあいにくいいのがなかったので、勧められるままにこれに。

焼き物もう一つ、サヨリの干物。白身で頼りないような味ですが美味しい。

サヨリはサイパンで潜っていて群れで泳いでいたよな~今は昔の話です。
焼酎がそろそろなくなった頃、大将がサービスでコハダの骨の素揚げを出してくれました。

骨煎餅ですが、これは肴に最適。美味いすね。
これが出てきたらもう少し飲まないとと焼酎を1本下ろします。
大将の狙い通りでした。
箸休めに酢だこももらいます。

〆はさんまの押し寿司。

これだけではと森の熊さんが言いたそうなので、さらにお好みの太巻きも。

最後にナシが出てきます。

焼酎はまだまだ残っていますのでまた次回。

お勘定は13284円。一人3千円で足らないのは基金から出しておきました。まあ、焼酎はほとんど残っていますので良しとしましょう。
とりあえず、まずはビール
 で乾杯。
で乾杯。つまみは最初はカツオのたたき。

これはショウガ醤油で食べます。ニンニクはついていない?ついていませんでした。
ビールはすぐになくなってもう2本。
次の肴は、森の熊さんの定番のイカゲソの七味焼き。

森の熊さんに聞くと必ず頼む一品です。
またまたビールはなくなるので今度は焼酎を出してもらいます。

まだだいぶ残っているので水割りでいただきます。
今度は私のリクエストで、蝦蛄を。

家でもたまに茹でるのですが、蝦蛄は甲羅というか皮というかを取るのがめんどくさい。ハサミで両縁を切って剥がすのですが、手がびしょびしょになるし誰かが剥いてくれたらといつも思っていて、ここはちゃんとむき身が出てくるので幸せ。
同時にこれまた森の熊さんのリクエストでマグロのほほ肉焼き。本当はカマ焼きがよかったのですが、この日はあいにくいいのがなかったので、勧められるままにこれに。

焼き物もう一つ、サヨリの干物。白身で頼りないような味ですが美味しい。

サヨリはサイパンで潜っていて群れで泳いでいたよな~今は昔の話です。
焼酎がそろそろなくなった頃、大将がサービスでコハダの骨の素揚げを出してくれました。

骨煎餅ですが、これは肴に最適。美味いすね。
これが出てきたらもう少し飲まないとと焼酎を1本下ろします。
大将の狙い通りでした。
箸休めに酢だこももらいます。

〆はさんまの押し寿司。

これだけではと森の熊さんが言いたそうなので、さらにお好みの太巻きも。

最後にナシが出てきます。

焼酎はまだまだ残っていますのでまた次回。

お勘定は13284円。一人3千円で足らないのは基金から出しておきました。まあ、焼酎はほとんど残っていますので良しとしましょう。










 中止。
中止。 ました。何とかテニスはできそうです。
ました。何とかテニスはできそうです。 瑞穂公園テニスコートへ。
瑞穂公園テニスコートへ。 です。
です。

 して試合に。
して試合に。
 。
。 みたいで、歳も歳だから悪くなるといけないので、途中で帰るとか言い出す。
みたいで、歳も歳だから悪くなるといけないので、途中で帰るとか言い出す。 でした。
でした。
 のまま帰ることになってしまいました。
のまま帰ることになってしまいました。