ばびろんまつこって知らなかったけど、見てみたら
写真の感じやツイの内容がかなり木嶋佳苗っぽいね。
顎のラインと胸元アップとか…
「骨」と話してみたい。
内臓とかには話しかけていたのに
骨にはそうしていなかった。
山形ビエンナーレ2016にむけて、五行を五味(あまい、からい、すっぱい、にがい、しょっぱい)で表す和菓子を試行錯誤中。他には麹、古代米、当帰茶、そして土偶。坂本大三郎さん監修&佐藤慎太郎さん実作だから、ただならぬ祭菓子になりそう…。 pic.twitter.com/yqBW3knMV4
@mana_ephiora 北原みのりさんのやつかな?非常に興味深いですね。
猫又、猫股(ねこまた)
江戸時代以降には、人家で飼われているネコが年老いて猫又に化けるという考えが一般化し、山にいる猫又は、そうした老いたネコが家から山に移り住んだものとも解釈された。 pic.twitter.com/u6ysEQvv4B
秋になると必ず茸の本を読みたくなる。そうやって少しづつ茸の本が増えていく…。『亡命ロシア料理』は茸には魂があって…なんて書いてあり、めっけもの、な感じの面白い本だった。 pic.twitter.com/96ZcscELkK
『天災から日本史を読みなおす』 武士の家計簿がおもしろくて同著者の別の本を手にとってみた。地震、津波などの災害をフィールドワークや古文書から読み解いている。井戸の水が枯れる、蛇がつく地名、とかよく耳にする事柄は本当らしい。日本、何回もこんなこと繰り返していたのか
「ネコ地蔵」ってアイルー村の話かと思っていたら本当にあるんだな。
新宿区西落合にある真言宗豊山派自性院。
江古田ヶ原の戦で太田道灌が一匹の猫に救われたことから猫寺という愛称で親しまれ、毎年2月には猫地蔵まつりが開催されると。 pic.twitter.com/SWD8Du5j3m
武甲山には日本武尊信仰の地、すなわちオオカミ信仰が息づいています。ダンプや大型トラックがひしめく採石場を経て、登山口である生川に回り込むと、武甲山御嶽神社の「一の鳥居」に行きつきます。昭和12年奉納の鳥居前に4体のオオカミ像。 pic.twitter.com/VmLjr2dp9V
先月から定期購読している『月刊住職』11月号を購入。今月は「鬼怒川決壊でお寺が避難所になる」「どのお寺でもできる必ず成功する灯明イベントの方法と実践に学ぶ」「お寺の屋根にチタンが増えている」「増えた寺を圧迫した幕府」などに興味津々。 pic.twitter.com/D8QLmvOUAM










 原キョウコ @body_wisdom
原キョウコ @body_wisdom 宮本武典 @miyamototo
宮本武典 @miyamototo
 日本妖怪図鑑 @nihon_youkai
日本妖怪図鑑 @nihon_youkai
 野村麻里 @nomuramari
野村麻里 @nomuramari
 nomad 777 @biosphere0054
nomad 777 @biosphere0054
 大野一雄・稽古の言葉 @ohnokazuo_bot
大野一雄・稽古の言葉 @ohnokazuo_bot 平金魚 @kingyoya123
平金魚 @kingyoya123 Tapkaara @Tapkara
Tapkaara @Tapkara
 いきうめ @dilettante_k
いきうめ @dilettante_k
 名言bot @meigenbot
名言bot @meigenbot 閑古堂 @1969KANKODO
閑古堂 @1969KANKODO







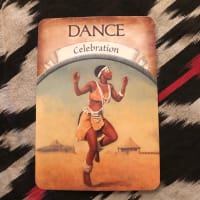










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます