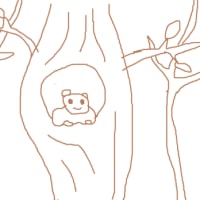1923とその前年に生まれた司馬遼太郎さんとドナルド キーンさんの対談の本を読みました。中央公論の嶋中鵬二さんという人にそそのかされて、五十代のお二人があれこれと話をされるというものでした。
私はおもしろかった。でも、例によって何にも頭に定着しないのです。すべて流されてしまう。だから、あわてて思いついたところをメモして、メモしたとたんに忘れてしまうけれど、何かのとっかかりにはなるだろうって、ブログに載せてたりします。
二人とも、あれこれわかってらっしゃるんでしょう。わからないのは私だけです。でも、ついて行きたくて本を買い、のこのこ読んでいる。もう60年前に話された内容です。そして、私はお二人よりも年寄りになっています。なのに、頭はスッカラカンだし、どうしようもありません。
自虐にならないようにします。とりあえず、メモしてみます。

日本には、身を捧げるようなものすごい宗教はあるのか、ということで、二人にもそんなに宗教的なものはないという点で一致しているんです。
(キーンさん)日本人が長い歴史のなかでいちばん巧妙にしたことは、外国文化のなかからもっとも日本にふさわしいものを選択することだった。
たとえば徳川時代の日本人の生活からいうと、生まれたときに、生まれたことをまず神道の神々に告げ、そして結婚式も神道ですが、ふだんの生活は儒教で、死ぬときは仏教的な法事がおこなわれた。しかもその三つの宗教、厳密には儒教は宗教じゃないでしょうけれども、ともかくまったく原理的に違うものでしょう。
まあ、日本人の宗教への態度は、節操がないというのか、適当に使い分けているというのか、本当に信じているのか、何だかあやふやなところがありますね。ちっとも信仰を大事にしていないように見える。
本人の中では、どれも大事にしていて、それなりに信じているつもりではあるけれど、根幹のところが何だか弱い。

それぞれに矛盾しているものです。神道によりますと、人間が生きているこの世界は、いちばんいいところです。死んでからは、黄泉(よみ)という穢(きた)ならしい汚れの多いところへすべての人は行く。
イザナギさんが亡くなった奥さんのイザナミさんに会いに行ったら、奥さんは亡者になっていて、逃げて帰って来る場面がありました。あんなに愛し合った二人なのに、奥さんがそんなになったら、ダンナは逃げるんだから、夫婦の愛だって、宗教と同じように移ろいやすいものなのだ、奥さんの顔が崩れていようが、久しぶりに会えるということは、もうイザナギさんはキレイな奥さんの姿を求めてたなんて、神話の世界でも私たちはズッコケてしまうのです。
死んだら、そんなとんでもないところに行く、という話なんか聞きたくなくなってしまう。
仏教では、この世の中は娑婆(しゃば)であって、穢(けが)れ多いところである。死んでから清い浄土へ行く。
儒教のほうは、この世の中以外に世の中はない(笑)。
儒教は現実を見つめることが大事で、死後の世界などは存在しない。それは事実だと思うし、死んだら何にもない、というはわかります。痛くもないし、感情もないし、愛する者への気持ちも消滅する。その人のことばやモノは存在するから、この世にある人は、亡くなった人をモノを通して思う。
仏教の「浄土(きよい土地)」というのは、甘い響きがあります。この世にある私たちは、亡くなった人たちが極楽で私たちのことを思ってくれている、そう思うと、何だかホッとする。
死後の世界に関していえば、仏教の考え方に魅力があるじゃないですか!

三つともまったく矛盾しあっているんです。日本人はその三つの宗教を同時に信じられるので、たいしたものだと思います。
冷静な見方で行けば、日本の人々の宗教観というのは、あやふやで、何を信じているのか、わからなくなることはありますね。
とても中途半端な世界の中に私たちはいるようです。よその人たちの宗教観でいくと、まるで違うみたいです。