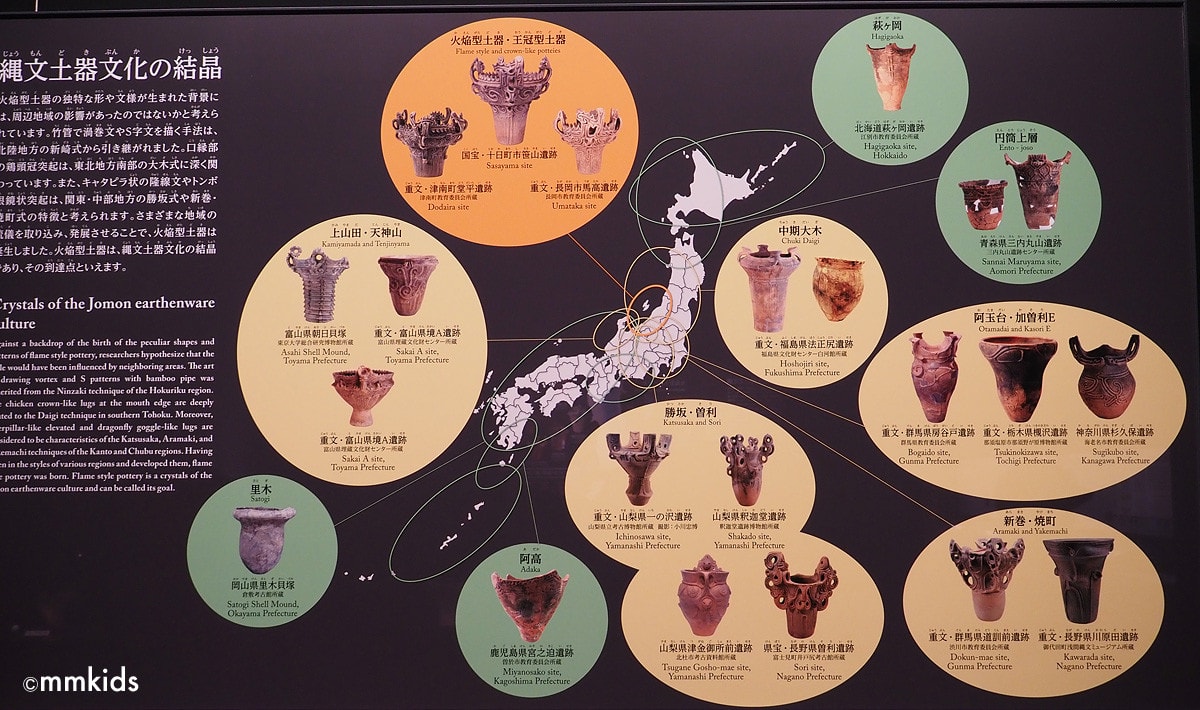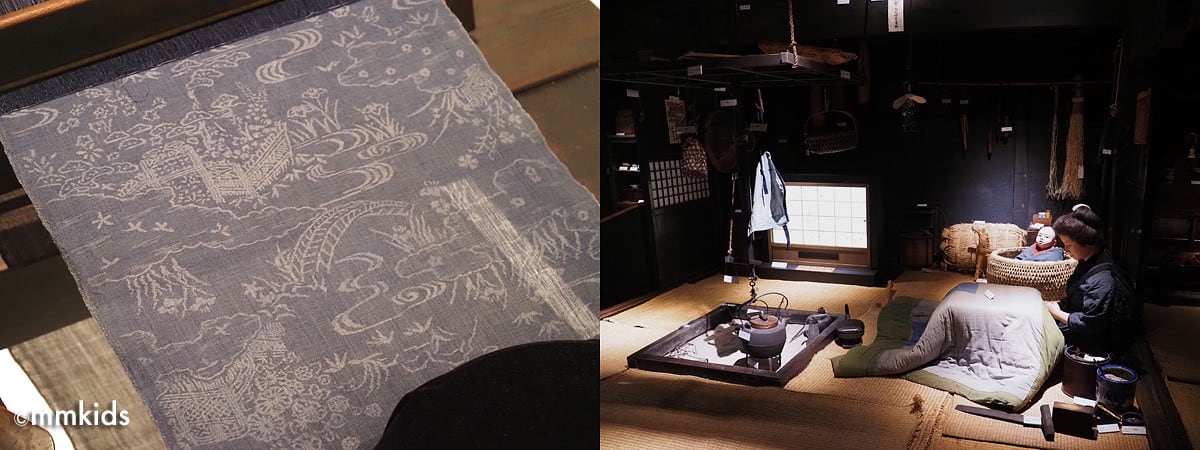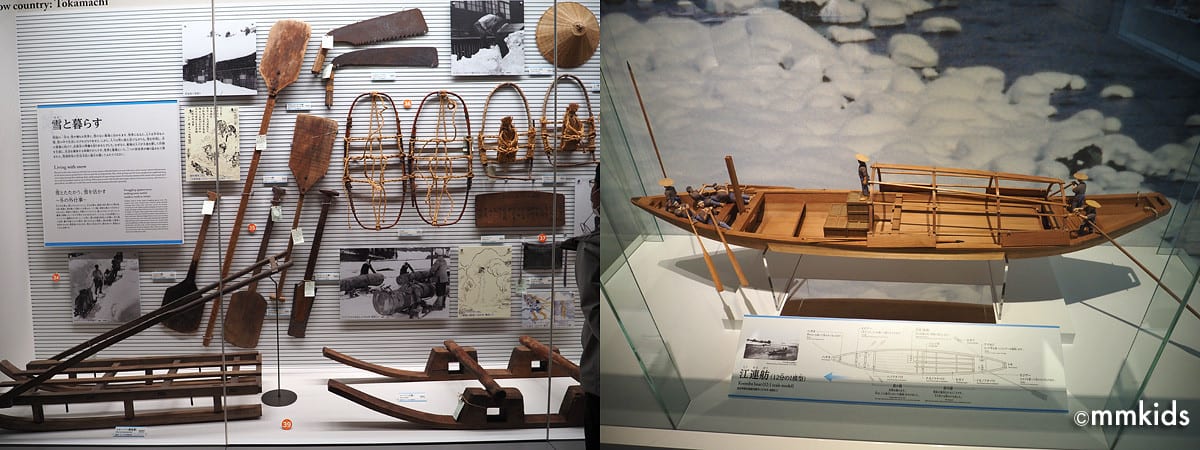十日町市博物館を後にして向かったのは、山手線や新幹線を動かすJR東日本の信濃川発電所の宮中取水ダム。

宮中取水ダムは昭和14年に新潟県十日町市(旧中里村)に建設され、沈砂池で土砂を沈殿させた後、水路トンネルを通り調整池に入り、電力の需要に応じて千手発電所、小千谷発電所、小千谷第二発電所へ送水され、発電が行われています。千手・小千谷・新小千谷の合計最大出力は44万9,000キロワットで、JR東日本で消費する電力量の4分の1に当たります。この電力で、上越線や首都圏の山手線、東北・上越新幹線などの電車を動かしています。

昨年の10月に訪れた時は、一番向こうの三つしかゲートが開いていませんでしたが、今回は前日に大雨が降ったのですべて開いていました。水も濁っていて轟音が響きます。幅は、330.8メートル。重力式のコンクリートダムです。

JR信濃川発電所管内鳥瞰図。訪れたのは、一番左上の宮中取水ダムです。小千谷発電所までは水路トンネルで運ばれます。

水圧がかかっているので、もの凄いスピードで流れていきます。すごい迫力でゾワゾワします。

大雨で大量の流木やゴミが流れ着いています。綺麗なサッカーボールはどこから流れてきたのでしょう。ペットボトルなどプラスチックゴミが多いですね。

昔はこの魚道がなかったので、信州まで鮭が遡上しなくなりました。ダムができる前は、秋になると上田や松本まで数万匹の鮭が遡上したそうです。2010年より中魚沼漁業協同組合の協力のもと、「新潟水辺の会」との共催により、宮中取水ダム下流河川敷でサケの稚魚の放流を実施しているそうです。しかし、上流にある東電の上流の西大滝ダムがネックになっているようです。千曲市の土口水門で、鮭が釣れたという話は聞かないですね。ここでも東電が癌ですか。

ダムは二酸化炭素(CO2)を排出しないクリーンエネルギーとして、その存在意義はますます高まっています。田中康夫元県知事が脱ダム宣言をしましたが、不要なダムだったり、経費の捏造だったりゼネコンの利権の温床になっていたからです。環境的に造ってはいけないダムは、海外では爆破されたりしています。ただ、治水や灌漑、発電で必要なダムもあるのです。少なくとも原発より遥かに安全でクリーンです。

取水口のゲート。このじぶたれた感じがなんともいい。

沈砂池。ここで土砂を沈殿させた後、圧力トンネルで発電所に送ります。

(左)宿泊地の野沢温泉に向かいます。温泉街の最上部にある麻釜。昔は麻を茹で皮を剥いたので麻釜と。現在は卵を茹でたり野菜を洗ったり。(右)共同浴場の大湯。共同浴場はあちこちにあります。

(左)この後、健命寺に行ったのですが、それは次の記事で特集します。その道すがらにあったカラムシ(苧麻)の群生地。縄文人は、これの繊維を使って布を織っていました。(右)宿泊した清風館の風呂。相当古いです。浴槽は男湯はひょうたんの形。内装はボロボロで、鏡や照明が変なところに付いてます。お湯は熱めですが最高です。
ところで、この宿は長野県民割で予約したのです。他の高級旅館はすべて売り切れていました。ところが、レベルが3に下がったのに、長野県はこの県民割を無期限延期にしたのです。我々は清津峡に行くことを決めていたので、割引がなくても予約しましたが、周りの旅館、特に高級旅館はキャンセルの嵐だったでしょう。実際に歩いてみると、長野県ナンバーはなく、県外ナンバー(首都圏も)ばかりでした。それも少なめで温泉街は閑散としていました。本当に長野県は阿部県知事は何を考えているのでしょうか。宿泊業者や土産物店は、カンカンでしょう。

(左)夕食です。高級旅館みたいにお品書きの付くお洒落な会席料理ではありませんが、仕出しではなく手作りです。馬刺し、カレイとキノコのホイル焼き、油揚げの山菜チーズ焼き。小田巻き蒸し。豚しゃぶ。蕎麦サラダ。和え物。野沢菜漬け。(右)根曲がり竹の焼き物とワラビ。これにヤマウド、タラの芽、山葡萄の葉、コシアブラの天ぷら。お腹いっぱいでご飯はキャンセルしました。

(左)朝食です。この時期の信州の定番、根曲がり竹とサバの水煮と玉ねぎの味噌汁。ハムとサラダ。サバ塩焼き。ヤマゴボウの漬物と梅干し。ヤマウドの和え物。ナメコと舞茸のおろし和え。豆腐サラダ。温泉卵。焼海苔。メロン。充分すぎる量です。味噌汁とナメコと舞茸のおろし和えが美味でした。(右)向こうの二人は二日酔いか?

(左)翌朝。清風館の裏側です。いい感じに鄙びています。(右)麻釜の隣の土産物屋。彼は塩漬けのコゴミを買いました。私は古漬けの野沢菜漬けを。もう色が変わって乳酸菌たっぷりです。このすんき漬みたいになった酸味のある野沢菜漬けが大好きです。そのままで。蕎麦にのせて。炒めてチャーハンに。おやきの具に。ここの亭主が、観光客もいないので暇だからとどくだみ茶をごちそうしてくれました。野沢温泉の最近の裏話をしてくれました。勉強になりました。ゼンマイは100グラム2000円以上と高価ですが、その理由も分かりました。この下にある土産物屋より自家製の希少なものが売られています。秋はキノコが並ぶでしょうね。オススメ。

(左)野沢温泉を愛した高野辰之記念のおぼろ月夜の館に寄りました。彼の書斎の復元。(右)ステンドグラス。「春がきた」「春の小川」「紅葉」「故郷」「朧月夜」と、彼の小学唱歌は、ほぼ誰もが歌えますね。

(左)小布施に向かう途中で中野に立ち寄りました。古い商店街で見つけたカクアゲ商店。味のある素晴らしいお店です。銚子産のサバの水煮缶詰が3つで499円。大きな切身の三種の魚の粕漬けが500円。お持ち帰りの海鮮丼も魅力的でした。また訪れたい。(右)昼は、近くの金太楼で。私はあんかけ揚げ焼きそばを。無化調でやさしい旨味のあるやきそばでした。地元の常連の人は、皆味噌ラーメンを頼んでいました。一番安くて一番早く出てきます。味もいいのでしょう。さて、北斎館に向かいましょう。
●JR東日本信濃川発電所・東京電力信濃川発電所。都民はこれがないと通勤通学も生活もできません 2020(妻女山里山通信)
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

宮中取水ダムは昭和14年に新潟県十日町市(旧中里村)に建設され、沈砂池で土砂を沈殿させた後、水路トンネルを通り調整池に入り、電力の需要に応じて千手発電所、小千谷発電所、小千谷第二発電所へ送水され、発電が行われています。千手・小千谷・新小千谷の合計最大出力は44万9,000キロワットで、JR東日本で消費する電力量の4分の1に当たります。この電力で、上越線や首都圏の山手線、東北・上越新幹線などの電車を動かしています。

昨年の10月に訪れた時は、一番向こうの三つしかゲートが開いていませんでしたが、今回は前日に大雨が降ったのですべて開いていました。水も濁っていて轟音が響きます。幅は、330.8メートル。重力式のコンクリートダムです。

JR信濃川発電所管内鳥瞰図。訪れたのは、一番左上の宮中取水ダムです。小千谷発電所までは水路トンネルで運ばれます。

水圧がかかっているので、もの凄いスピードで流れていきます。すごい迫力でゾワゾワします。

大雨で大量の流木やゴミが流れ着いています。綺麗なサッカーボールはどこから流れてきたのでしょう。ペットボトルなどプラスチックゴミが多いですね。

昔はこの魚道がなかったので、信州まで鮭が遡上しなくなりました。ダムができる前は、秋になると上田や松本まで数万匹の鮭が遡上したそうです。2010年より中魚沼漁業協同組合の協力のもと、「新潟水辺の会」との共催により、宮中取水ダム下流河川敷でサケの稚魚の放流を実施しているそうです。しかし、上流にある東電の上流の西大滝ダムがネックになっているようです。千曲市の土口水門で、鮭が釣れたという話は聞かないですね。ここでも東電が癌ですか。

ダムは二酸化炭素(CO2)を排出しないクリーンエネルギーとして、その存在意義はますます高まっています。田中康夫元県知事が脱ダム宣言をしましたが、不要なダムだったり、経費の捏造だったりゼネコンの利権の温床になっていたからです。環境的に造ってはいけないダムは、海外では爆破されたりしています。ただ、治水や灌漑、発電で必要なダムもあるのです。少なくとも原発より遥かに安全でクリーンです。

取水口のゲート。このじぶたれた感じがなんともいい。

沈砂池。ここで土砂を沈殿させた後、圧力トンネルで発電所に送ります。

(左)宿泊地の野沢温泉に向かいます。温泉街の最上部にある麻釜。昔は麻を茹で皮を剥いたので麻釜と。現在は卵を茹でたり野菜を洗ったり。(右)共同浴場の大湯。共同浴場はあちこちにあります。

(左)この後、健命寺に行ったのですが、それは次の記事で特集します。その道すがらにあったカラムシ(苧麻)の群生地。縄文人は、これの繊維を使って布を織っていました。(右)宿泊した清風館の風呂。相当古いです。浴槽は男湯はひょうたんの形。内装はボロボロで、鏡や照明が変なところに付いてます。お湯は熱めですが最高です。
ところで、この宿は長野県民割で予約したのです。他の高級旅館はすべて売り切れていました。ところが、レベルが3に下がったのに、長野県はこの県民割を無期限延期にしたのです。我々は清津峡に行くことを決めていたので、割引がなくても予約しましたが、周りの旅館、特に高級旅館はキャンセルの嵐だったでしょう。実際に歩いてみると、長野県ナンバーはなく、県外ナンバー(首都圏も)ばかりでした。それも少なめで温泉街は閑散としていました。本当に長野県は阿部県知事は何を考えているのでしょうか。宿泊業者や土産物店は、カンカンでしょう。

(左)夕食です。高級旅館みたいにお品書きの付くお洒落な会席料理ではありませんが、仕出しではなく手作りです。馬刺し、カレイとキノコのホイル焼き、油揚げの山菜チーズ焼き。小田巻き蒸し。豚しゃぶ。蕎麦サラダ。和え物。野沢菜漬け。(右)根曲がり竹の焼き物とワラビ。これにヤマウド、タラの芽、山葡萄の葉、コシアブラの天ぷら。お腹いっぱいでご飯はキャンセルしました。

(左)朝食です。この時期の信州の定番、根曲がり竹とサバの水煮と玉ねぎの味噌汁。ハムとサラダ。サバ塩焼き。ヤマゴボウの漬物と梅干し。ヤマウドの和え物。ナメコと舞茸のおろし和え。豆腐サラダ。温泉卵。焼海苔。メロン。充分すぎる量です。味噌汁とナメコと舞茸のおろし和えが美味でした。(右)向こうの二人は二日酔いか?

(左)翌朝。清風館の裏側です。いい感じに鄙びています。(右)麻釜の隣の土産物屋。彼は塩漬けのコゴミを買いました。私は古漬けの野沢菜漬けを。もう色が変わって乳酸菌たっぷりです。このすんき漬みたいになった酸味のある野沢菜漬けが大好きです。そのままで。蕎麦にのせて。炒めてチャーハンに。おやきの具に。ここの亭主が、観光客もいないので暇だからとどくだみ茶をごちそうしてくれました。野沢温泉の最近の裏話をしてくれました。勉強になりました。ゼンマイは100グラム2000円以上と高価ですが、その理由も分かりました。この下にある土産物屋より自家製の希少なものが売られています。秋はキノコが並ぶでしょうね。オススメ。

(左)野沢温泉を愛した高野辰之記念のおぼろ月夜の館に寄りました。彼の書斎の復元。(右)ステンドグラス。「春がきた」「春の小川」「紅葉」「故郷」「朧月夜」と、彼の小学唱歌は、ほぼ誰もが歌えますね。

(左)小布施に向かう途中で中野に立ち寄りました。古い商店街で見つけたカクアゲ商店。味のある素晴らしいお店です。銚子産のサバの水煮缶詰が3つで499円。大きな切身の三種の魚の粕漬けが500円。お持ち帰りの海鮮丼も魅力的でした。また訪れたい。(右)昼は、近くの金太楼で。私はあんかけ揚げ焼きそばを。無化調でやさしい旨味のあるやきそばでした。地元の常連の人は、皆味噌ラーメンを頼んでいました。一番安くて一番早く出てきます。味もいいのでしょう。さて、北斎館に向かいましょう。
●JR東日本信濃川発電所・東京電力信濃川発電所。都民はこれがないと通勤通学も生活もできません 2020(妻女山里山通信)
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。