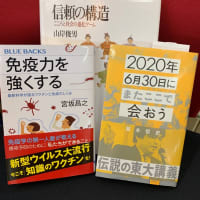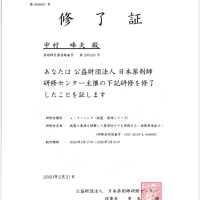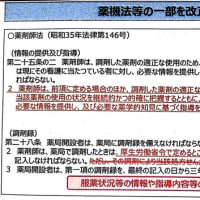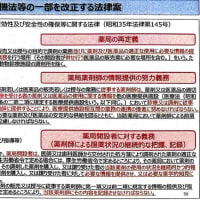サプリメント同士、サプリメントと医薬品、サプリメントの疾患に対する影響などを考える時、どのように考えていけば良いのか論理的に考えてました。
ちょうど、北海道薬剤師ネットワークのMLで、CYPの代謝からの飲み合わせ,副作用の予見の話題が出てましたので。
<坂田先生、ヒントを頂きまして感謝しております>
そこで、薬の飲み合わせの理論的な流れを再確認し、それがどのようにサプリメントに当てはめる事が出来るか、自分の整理を兼ねて書いてみます。
<体内動態>
1)消化器官からの“吸収”
2)血中から臓器・組織への“移行”
3)肝臓などでの“代謝・分解”
4)血中から肝臓・腎臓などからの“排泄”
今、調剤などで薬の相互作用を考える時、3)のCYPとの関連を見ていく事が主流になってます。
ですが、サプリメントの場合、
1)ですと
ミネラル(サプリメント)と医薬品のキレート形成
PHに影響を与える物(アルカリ飲料など)
油性成分のサプリメント
物理的(繊維質などで)に吸着させる働きがあるサプリメント
胃・腸の通過時間に影響する物
腸管膜にサプリメントの成分のリセプター、キャリアーのあるケース(この分野の研究は非常に遅れてます)
2)の場合は
アルブミン、α1-酸性糖タンパクなどとの血中での結合
臓器特異性・移行性
BBBの通過のし易さ(油性、Pタンパク)
(この分野の研究は少ないです)
3)では、
セントジョーンズワートのCYP
(このごろサプリメントによっては、CYPの代謝を調べてくる物も少しずつ増えてきてます)
4)で
腎、胆汁排泄への影響。
尿路感染に使いますサプリメントでクランベリーがありますが、尿を酸性にします。
ですから、高尿酸の治療等に注意が要ります。
また、代謝経路によっては、成分の濃縮もあり、それも影響が出るかと思います。
ちょうど、北海道薬剤師ネットワークのMLで、CYPの代謝からの飲み合わせ,副作用の予見の話題が出てましたので。
<坂田先生、ヒントを頂きまして感謝しております>
そこで、薬の飲み合わせの理論的な流れを再確認し、それがどのようにサプリメントに当てはめる事が出来るか、自分の整理を兼ねて書いてみます。
<体内動態>
1)消化器官からの“吸収”
2)血中から臓器・組織への“移行”
3)肝臓などでの“代謝・分解”
4)血中から肝臓・腎臓などからの“排泄”
今、調剤などで薬の相互作用を考える時、3)のCYPとの関連を見ていく事が主流になってます。
ですが、サプリメントの場合、
1)ですと
ミネラル(サプリメント)と医薬品のキレート形成
PHに影響を与える物(アルカリ飲料など)
油性成分のサプリメント
物理的(繊維質などで)に吸着させる働きがあるサプリメント
胃・腸の通過時間に影響する物
腸管膜にサプリメントの成分のリセプター、キャリアーのあるケース(この分野の研究は非常に遅れてます)
2)の場合は
アルブミン、α1-酸性糖タンパクなどとの血中での結合
臓器特異性・移行性
BBBの通過のし易さ(油性、Pタンパク)
(この分野の研究は少ないです)
3)では、
セントジョーンズワートのCYP
(このごろサプリメントによっては、CYPの代謝を調べてくる物も少しずつ増えてきてます)
4)で
腎、胆汁排泄への影響。
尿路感染に使いますサプリメントでクランベリーがありますが、尿を酸性にします。
ですから、高尿酸の治療等に注意が要ります。
また、代謝経路によっては、成分の濃縮もあり、それも影響が出るかと思います。