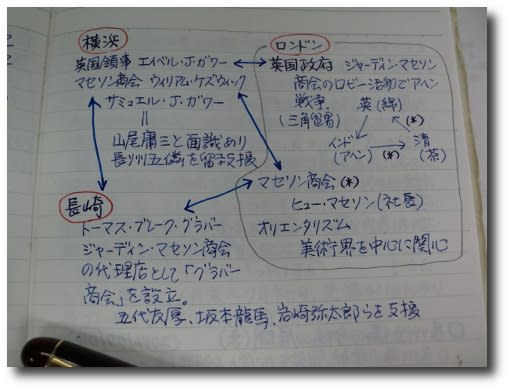長州藩から英国へ密航留学して来た五人のサムライ青年たちの世話役となったヒュー・マセソンの証言(*1)によれば、
私は彼らにふさわしい処に下宿させ、教育への準備に取りかかった。極めて幸運なことに、ユニヴァーシティ・カレッジの化学教授で、のちに英国協会(*2)の会長となったウィリアムソン博士にお願いし、彼らを博士の家に下宿させてもらうことができた。教授と相談の上、私は彼らが多少なりとも英語が学べ、しかも真に良い教育(a really good education)の基礎づくりの準備ができるクラスに入れるようにとり計らった。この点で、ウィリアムソン博士の助言はたいへん貴重なものであった。(後略)」
とされています。
たしかに、現代においても、外国人留学生を受け入れるには、いきなり正課の講義に放り込むようなことはせず、まず一定期間の語学や日常生活習慣、礼儀作法などの訓練を行った後に、本人の希望を聞きながら、受講科目を相談するのが標準的なやり方だろうと思います。たぶん、これは洋の東西、時代を問わず、必要な段階なのだろうと思われます。
では、ウィリアムソン博士とエマ夫人が住む自宅はどこにあったのか。犬塚孝明氏の著書(*1)では、プロヴォスト街(Provost Road)の「ごく小さな家」とあり、そこはアデレード街(Adelade Road)の北側に位置し、プリムローズ・ヒル(Primrose Hill)の駅にも近く、ハムステッド(Hamstead)と呼ばれる地域で、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンまでは約3キロほどの道のり(p.87)と紹介されています。
そこで、Google の「地図」で「London Provost Rd.」で検索してみると、
<iframe src="https://maps.google.co.jp/maps?q=London+Provost+Rd.&ie=UTF8&hl=ja&hq=&hnear=Provost+Rd,+London,+%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9&ll=51.544547,-0.157372&spn=0.010209,0.013905&t=m&z=14&brcurrent=3,0x0:0x0,0&output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="350"></iframe>大きな地図で見る
現在のプロヴォスト街の地図が表示されます。さらに、縮尺を変更してズームインしてみると、これらの位置関係が確かめられますし、Provost Rd. のストリートビューを見ると、洒落た住宅街ではあるけれど、大邸宅が並ぶ街ではないことがよくわかります。昔と今と、街の様子が同じとは限りませんが、少なくとも周囲を圧する大邸宅があった街ではなさそうです。
ウィリアムソン博士自身は、おそらくは中産階級、それも召使いを何人も抱えているような恵まれた中産階級ではなく、当時の化学の社会的位置づけからみても、せいぜい召使いを一人雇える程度の経済的背景だったではないかと思われます。そこに、サムライ留学生の支払う学費や下宿料が、研究費や化学会会長としての交際費などに役立ったのではないか。
東洋のサムライ青年たちを下宿させることについては、ヴィクトリア時代の慣習で夫の意志が強く働いたとはいえ、夫人の了解も必要だったことでしょう。幸いなことに、教授自身がギーセン大学のリービッヒの研究室で、多国籍な学生たちと生活した経験があり、オーギュスト・コントの下で学び、人種や国籍や宗教、習慣などの偏見から自由であったこと、いわばコスモポリタン的な意識が濃厚であったことが大きいでしょう。また、エマ夫人も、教授の身体的なハンディキャップ(*3)を承知で結婚しているわけで、夫の見識に理解と共感を示していた、進歩的な女性だったのではないかと想像しています。あるいは、過去にヨーロッパの他国の学生を受け入れたこともあったのかもしれません。
(*1):犬塚孝明『密航留学生たちの明治維新~井上馨と幕末藩士』
(*2):王立協会のことか。
(*3):ウィリアムソン教授のこと~「電網郊外散歩道」2014年6月