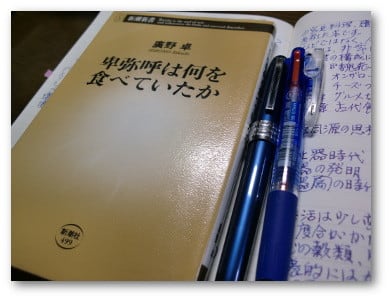
2012年12月に刊行された新潮新書で、廣野卓(ひろの・たかし)著『卑弥呼は何を食べていたか』を読みました。表題のほか、大和王朝の宮廷料理、遣魏使の弁当など、古代の食卓について考察した本です。権力をめぐる騙し合いや殺し合いなどではなく、人々が何を食べていたかに関する内容は、非常に興味深いものがあります。
本書の内容は次のとおりです。
タイトルの「卑弥呼は何を食べていたか」については、『魏志倭人伝』の記述から、米とアワなど雑穀類、クリ、シイ、トチなど堅果類、サトイモ、蔬菜、魚貝類などを挙げています。むしろ、遣魏使の使節が食べた魏の宮廷料理のほうがずっと詳しいです。このあたり、タイトルが内容にそぐわない面があり、「古代の食生活を探る」みたいな題のほうが当たっているようです。
とはいいながら、調理技術的に、先土器時代の「焼く・炙る」から、土器の発明により「煮る・煮詰める・蒸す」ことが可能になり、さらに金属器が使われるようになって、「油で揚げる、炒める」ことが普及していくというあたりは、世界史的な視点が面白いです。
また、古代から現代まで、食生活は少しずつ変わってきていますが、共通点も多くあります。食べている魚種はタイを好むなど現代とほぼ同じようなものですし、鎌倉時代の説話集『古事談』に
との記述が残るのだそうで、なんだか共感していまいます(^o^)/
また、時代によって米に依存する度合いがかなり違ってきており、昔のほうがアワ、ヒエ、クルミ、トチなどの雑穀類・堅果類が幅広く食べられており、脚気予防などの観点からは栄養的に偏らずむしろ好ましいようです。しかし、食料の安定的な供給確保の面では現代のほうがだいぶ安心感があるみたい。
本書の内容は次のとおりです。
第1章 『魏志倭人伝』に卑弥呼の食を探る
第2章 オンザロックを味わった仁徳大王
第3章 チーズづくりを命じた文武天皇
第4章 グルメな長屋王
第5章 古代食と現代食
タイトルの「卑弥呼は何を食べていたか」については、『魏志倭人伝』の記述から、米とアワなど雑穀類、クリ、シイ、トチなど堅果類、サトイモ、蔬菜、魚貝類などを挙げています。むしろ、遣魏使の使節が食べた魏の宮廷料理のほうがずっと詳しいです。このあたり、タイトルが内容にそぐわない面があり、「古代の食生活を探る」みたいな題のほうが当たっているようです。
とはいいながら、調理技術的に、先土器時代の「焼く・炙る」から、土器の発明により「煮る・煮詰める・蒸す」ことが可能になり、さらに金属器が使われるようになって、「油で揚げる、炒める」ことが普及していくというあたりは、世界史的な視点が面白いです。
また、古代から現代まで、食生活は少しずつ変わってきていますが、共通点も多くあります。食べている魚種はタイを好むなど現代とほぼ同じようなものですし、鎌倉時代の説話集『古事談』に
イワシは体に良いけれど、宮家や貴族の食には供しない。サバは卑しい食べ物だけれど天皇にお出しする。後三条天皇(第71代・平安時代末期)は、サバの頭にコショウを塗り、炙って常に口にされていた(p.146)
との記述が残るのだそうで、なんだか共感していまいます(^o^)/
また、時代によって米に依存する度合いがかなり違ってきており、昔のほうがアワ、ヒエ、クルミ、トチなどの雑穀類・堅果類が幅広く食べられており、脚気予防などの観点からは栄養的に偏らずむしろ好ましいようです。しかし、食料の安定的な供給確保の面では現代のほうがだいぶ安心感があるみたい。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます