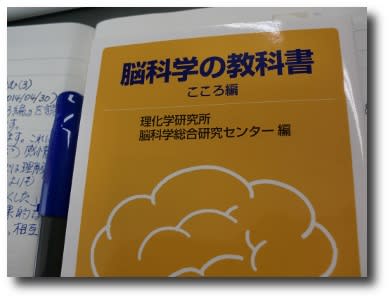良く晴れた五月の空の下、昨日はサクランボ果樹園の草刈りに従事し、夜は仲良し同窓生の会に出席して楽しく飲みました。にもかかわらず、今朝は早朝から果樹園の防除作業を行い、朝風呂に入り、昼寝をして、本日のメイン・イヴェントである山形交響楽団第237回定期演奏会に出かけました。
本日の曲目は、「ナポレオンに寄せる頌歌」と題し、
1. シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」
2. ドヴィエンヌ/フルート協奏曲 第7番 ホ短調 南部さやか(Fl.)
3. ベートーヴェン/交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」
飯森範親指揮、山形交響楽団
というものです。「未完成、エロイカ」という有名二曲に、珍しいドヴィエンヌの第7番の協奏曲を組み合わせるという、実に老獪な(^o^)プログラミングでありまして、期待の回です。
恒例の音楽監督のプレトークで、新しい楽器の寄贈を受けたことが紹介されました。これは、加藤総業(株)の社長さんから、スイスのバーゼル市にある金管楽器工房のE管ナチュラル・トランペット二本をいただいたとのことです。このことにより、対応できる曲目の幅がぐっと広がることになります。
さて、最初の曲はシューベルトの「未完成」交響曲です。楽器編成は、左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(8)、正面奥にフルート(2)、オーボエ(2)、その後ろにクラリネット(2)、ファゴット(2)、さらにその奥にホルン(2)、トランペット(2)、最後列にはコントラバス(3)とトロンボーン(3:うち1はバス・トロンボーン)、その右にバロック・ティンパニとなります。このうち、ホルンとトランペットはナチュラル・タイプを採用しており、トロンボーンも古楽器タイプだそうです。コンサートマスター席には犬伏亜里さんが座りますが、プログラムによれば本日のメンバーは少し変化があり、チェロの小川さんの代わりに客演の富岡廉太郎さん、オーボエのトップは佐藤麻咲さんの代わりに客演の松岡裕雅さん、また先月末をもって退団した高橋あけみさんに代わって、ファゴットのトップには客演の武井俊樹さんが座ります。
第1楽章:アレグロ・モデラート。はじめに、チェロのトップとコントラバスによって、例の暗~く重苦しい旋律が歌われます。弦のトレモロに乗って、クラリネットとオーボエが主題を提示します。二本のホルンの響きの調和感!赤と青の色で区別しているらしいトランペットも、新しい楽器(E管)が加わったことによって可能になったものなのでしょうか。そして、とっても暗いんだけれど、美しい音楽が展開されていきます。ゆっくりめのテンポで、力のこもった劇的な表現です。曲の終わりの充実感が、すごいです。
第2楽章:アンダンテ・コン・モート。コントラバスのピツィカートを背景に、ファゴットとトランペットがppで弦楽を導き入れます。これに木管が加わってきて、それぞれの楽器の素晴らしい響きに魅了されているうちに全奏、繰り返されて再び全奏。いいなあ、ほんとに久しぶりに「未完成」を聴きました。
ここで、ステージ上の配置を若干並べ替えます。「フランスのモーツァルト」と呼ばれることもあるというドヴィエンヌのフルート協奏曲は、楽器編成をぐっと縮小して、ほとんど室内オーケストラという雰囲気です。具体的には、第1ヴァイオリン(6)、第2ヴァイオリン(6)が対向配置、これにチェロ(3)、ヴィオラ(4)、コントラバス(2)の6-6-4-3-2 という弦楽セクションとなり、ホルン(2)、オーボエ(2)に、ファゴット(1)が加わります。
独奏者の南部やすかさんが登場、髪をアップにまとめ、アイヴォリーのドレスの上半身に金色のラメ?が入っています。立ち姿は、うーん、形容する語彙が貧弱で申し訳ありませんが、ギリシャ神話のニンフのようです(^o^;)>poripori
演奏が始まると、飯森さんは指揮棒なしで、柔らかに優雅に、でもリズムをはっきりと指揮しています。第1楽章:アレグロは、なるほど「フランスのモーツァルト」と呼ばれる理由がわかりました。途中、だいぶ高齢らしいおばあちゃんが、何やらポリ袋のようなものをガサガサして困りました。第2楽章:アダージョ。フルート・ソロがなんとも素晴らしい!テクニックも音も、お見事の一言です。第3楽章:アレグレット・ポコ・モデラート。規模を縮小した室内オーケストラの編成が実に効果的で、フルートの独奏とバランスがとれて、ホールの大きさにもよく合います。この曲も初めて聴きましたが、なかなかチャーミングな曲です。例のおばあちゃんも、近くの男性のお客さんがそっと注意してくれたらしく、静かにしておりました。ああよかった。
15分の休憩の後は、いよいよ「エロイカ」の番です。編成がまた変わり、8-8-5-5-3 の弦楽部に加えて、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(3),Tp(2),Timp.となります。ホルンとトランペット、トロンボーンはナチュラルな古楽器タイプ、ティンパニもバロック・タイプです。
第1楽章:アレグロ・コン・ブリオ。最初の2音の明快さ!これで「エロイカ」の音楽にぐぐっと引き込まれます。演奏は速めのテンポで進みます。客演の奏者の方々も、ひたすら音楽に没頭している様子。第2楽章:アダージョ・アッサイ。いわゆる葬送行進曲ですが、あまりねっとりした葬送でないのが嬉しい。赤と青を持ち換える方式のトランペットは、ここでは赤のほうです。オーボエが聴かせどころですし、バロック・ティンパニもスカッとした抜けの良い打音を響かせます。気合の入った指揮、演奏で、弦だけのところも、インテンポで明瞭なリズムが効果的に感じます。第3楽章:スケルツォ、アレグロ・ヴィヴァーチェ。弦の澄んだ音色にオーボエとフルートが印象的ですが、さらに三本のホルンのぞくぞくするような響き合いが素晴らしい!第4楽章:フィナーレ、アレグロ・モルト。編成を絞ったオーケストラの、澄んだ音、冴えた響きを堪能しつつ、今回はさらに低弦部隊が力を発揮して、力感のある音楽を実現したように感じられました。あまりテンポを速めなかったために、例の「酔っ払いの旋律」(^o^;)は演歌っぽくはならず、力強さがありましたし、オーボエ、クラリネット、ファゴットの木管アンサンブルはとてもステキでした。これに弦が加わるところは、なんとも胸キュンになります。そうこうするうちに、一気にフィナーレへ。
演奏が終わって、音楽監督が客席に話をしました。これから東京と大阪で「さくらんぼコンサート」を予定しており、親戚・知人など、心当たりの方面に案内を願いたい、との内容でした。今回は、母の日の演奏会とあってか、自由席に空席が目立ちました。次回は、ぜひ大勢のお客様が入場されるように願いたいものです。


そうそう、ファン交流会でフルートの南部やすかさんのお話を聞きました。外見はキュートな妖精のような印象でしたが、お話をすると大人の落ち着きが感じられます。パンフレットによれば、この三月に長男を出産されたばかりなのだそうです。山響の印象は、やはり「温かい」オーケストラだ、とのこと。飯森さんは、エロイカでのホルンの健闘を讃えるとともに、新しいトランペットを寄贈していただいたことへの感謝の言葉でした。「近代への梯」と大した次回の定期演奏会(7月19/20日、ワーグナー「ジークフリート牧歌」、リスト「ピアノ協奏曲第1番」、バルトーク「ルーマニア民族舞曲」、ストラヴィンスキー「かるた遊び」)も楽しみです。